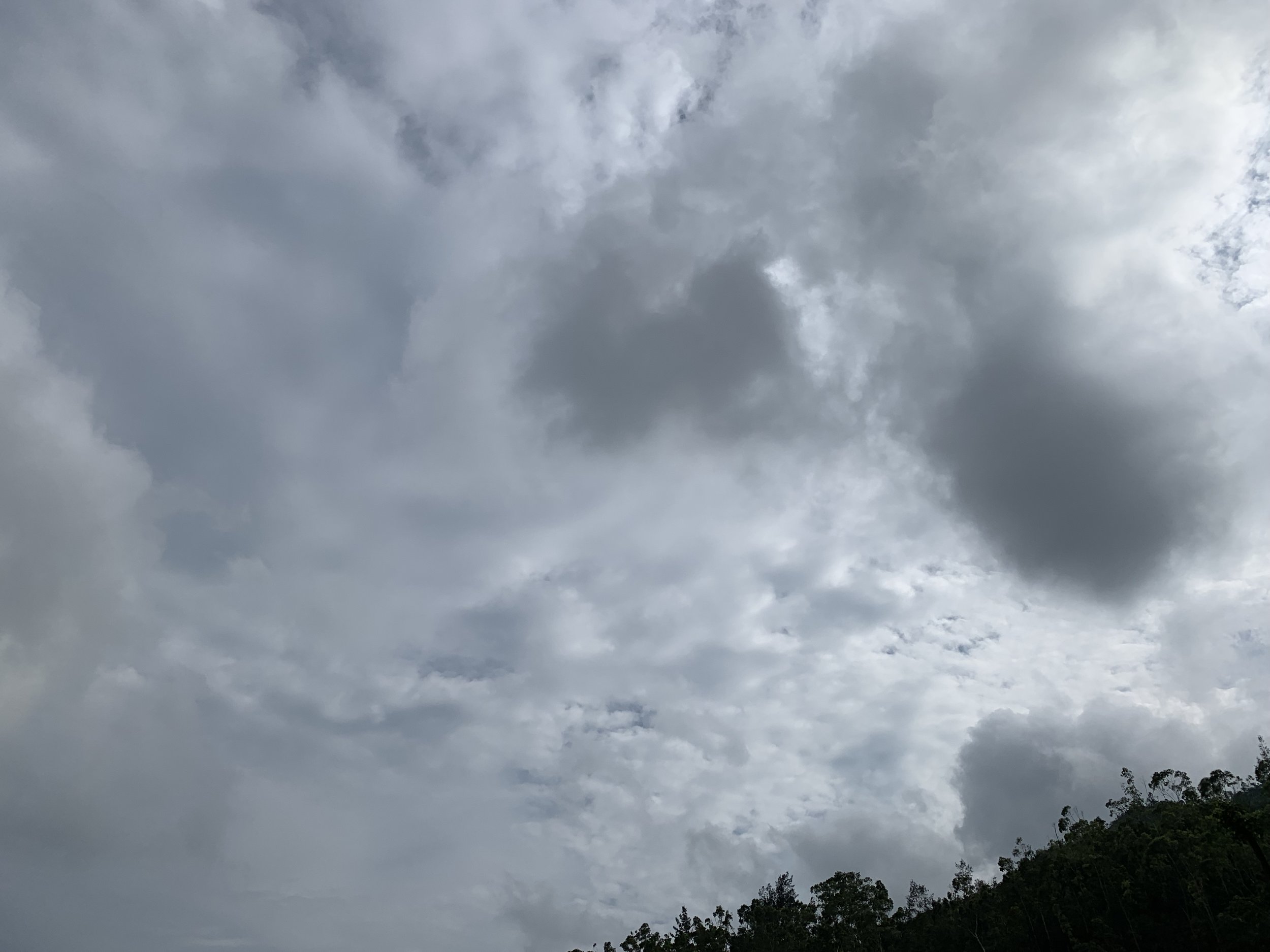矢沢永吉がツアーを一年休んだとき。- 休んだことによる「発見」。
「ほぼ日刊イトイ新聞」の創刊21周年記念企画、矢沢永吉x糸井重里の対談が興味深い。
「ほぼ日刊イトイ新聞」の創刊21周年記念企画、矢沢永吉x糸井重里の対談が興味深い。
たとえば、その「第3回:やってたら、落ち着くの」(2019年6月8日配信開始)のなかで、歌手の矢沢永吉が「一年ツアーを休んだときのこと」を語っている。話の文脈は、第3回のタイトル「やってたら、落ち着くの」にあるように、なぜ、こうして歌手としてやりつづけているのかという問いへの応答である。
矢沢永吉が歌手として「いちおう食べれる」ようになってから、ハッピーじゃないことに気づく。まもなく70歳になる矢沢は、「俺は、金じゃなくて、やりたくてやってる。…やってたら、落ち着くの」と語る。
やることの大きさではなく、それぞれの人なりに「じぶんがやりたいことが、落ち着くことが、あるか、ないか」が大切なんだと、糸井重里と「ほぼ日」の乗組員たちをまえに語るのである。
そんな発言を聴きながら、糸井重里が、「一年ツアーを休んだこと」がよかったのではないかと、問いを投げかける。
それに対して、矢沢永吉は、こんなふうに、興味深い応答をしている。
矢沢 あのときはね、なんだ、俺、気づいたら、走って走って、転がって転がって、行って行って、これじゃまずいなと思ったのよ。ただひたすらに機関車のように走って、そうじゃなくてさ、どこかの街をこう歩いていると、ちょっとあぜ道があったり、横丁があったりして、ちょっと入ってみたいなぁって思ってひょいと曲がってみたりして、これが生きてるってことじゃない?…
「道」が呼びかけてくる。それは、実際の街にあるあぜ道や横丁でありながら、心の奥深くにたたずむ<道>であるかもしれない。「生きられていないじぶん」が、心の奥深くから、呼びかけてくる。そんなふうに、ぼくはいったん読みながら、先をつづける。そして、その先が、とても興味深いのだ。
矢沢永吉は、こう語り続ける。
矢沢 で、ちょっと、今年はツアーやめる、と。やめて、逆にその横丁みたいなとこ、ちょっと覗いてみて、入ってみたらどうなるのか、発見があるかもしれないと思ったんですね。…すると、どうなったか?…なんにも発見がないことがわかった。
一年ツアーを休んで、横丁に入ってみて、「発見」を期待したけれど、そこには「なんにも発見がないこと」がわかる。矢沢は、あくまでも「ぼく」のこととして、また器用でない「ぼく」のこととして、この経験を伝えている。「そうなんだよ、人生ってそんなもんなんだよ!」、と。
糸井重里も、周りで聴いている人たちもみな、笑う。矢沢永吉も期待したように、糸井重里も、周りで聴いている人たちも、それから読者も、「発見」を期待してしまう。どんな「発見」があったのだろうと。でも、矢沢にとって、そこに「発見」はなかった。
「発見」がなかったことを聞いて、人はそれぞれに、いろいろと応答するかもしれない。「休み」の効果や「横丁」の呼びかけについて、いろいろと語るかもしれない。そのことについて、矢沢永吉は積極的に口をはさむことはしないだろう。
ぼくが思うのは、それでも、なんにも発見がないことが「わかった」ということ自体に、矢沢永吉にとっての「意味」があっただろうし、そこを転回軸として、「やりたくてやってる」という方向につきぬけてゆくことができたのではないかということである。
「そうなんだよ、人生ってそんなもんなんだよ!」と矢沢永吉が言うとき、そこには投げやりがあるのではなく、そんな人生を、そんな人生だからこそ、その過程を味わいつくしてゆくのだというところに走りぬけていく力としての潔さがあるように、ぼくにはきこえる。
山の「歩きかた」に凝縮された<教え>。- ニュージーランドの山との/山での出会い。
ニュージーランドの山をひとりでめぐっているときに、ぼくは、ぼくの「生きかた」を深いところで照らす<教え>を得た。山小屋で出会ったスウェーデン出身の女性に受けたその<教え>は、それまでじぶんが疑問視してきたことに直接に光をあてた。
ニュージーランドの山をひとりでめぐっているときに、ぼくは、ぼくの「生きかた」を深いところで照らす<教え>を得た。山小屋で出会ったスウェーデン出身の女性に受けたその<教え>は、それまでじぶんが疑問視してきたことに直接に光をあてた。
正確には、彼女が「生きかた」を説いたのではない。彼女は、ぼくに問いを投げかけたのであった。
「ジュン、あなたは道中何を見てきたの?」
流暢な英語で、彼女の真摯な声がぼくにまっすぐにとどいた。ほんとうにまっすぐな響きであった。
1996年のこと。大学2年を終え休学し、ワーキングホリデー制度を活用してニュージーランドに住むことになったぼくは、最終的に9ヶ月ほどの滞在となったうちの後半に、ニュージーランドを旅した。最初はニュージーランド徒歩縦断に挑戦し、その挑戦が中途で「挫折」したのちは、南島の山々を歩いていた。
ニュージーランドの山々はとてもよく管理されていて、トレッキングのコースに沿って山小屋がうまい具合に配置されている。これらの山小屋を移動してゆくことで、コースを完了することができるようになっている。
そんなコースのひとつを選んで歩いていたぼくは、あるとき山小屋を早朝に出発し、歩みを進め、昼過ぎには次の山小屋に到着したのであった。
つぎの「山小屋」という目的地に着くことができたぼくは、山小屋でゆっくりしていたのだけれど、夕方あたりになって、一人のトレッカーが到着したのであった。休暇でスウェーデンから来ているという彼女は、ぼくと言葉を交わすなかで、冒頭の問いをなげかけたのであった。
「ジュン、あなたは道中何を見てきたの?」
そんな問いを投げかけながら、彼女は、道中で楽しんできた、道の脇に咲く花や草木、また彼女をむかえる鳥たちがどれだけ素晴らしかったかを話してくれた。彼女が投げかけた問い、彼女の「歩きかた」とその楽しみかたに、ぼくの心の深いところに照明があてられたようであった。その光は、ぼくの「生きかた」までをも照らすほどの、まっすぐな光であった。
問いを投げかけられたぼくは、つぎ’の山小屋という「目標」に目を向けて道中をかけぬけてきてしまっていたから、返す言葉を失ってしまった。道中まったく見てこなかったわけではないけれど、道の両脇に咲く花や草木たちとすごす時間は、なるべく効率的に短縮されてしまったかのようであった。
彼女の問いとことば(とその響き)は、今でも、ぼくのなかで光源として輝きを放ちながら、ぼくの「生きかた」に光をあてている。
…「近代」という時代の特質は人間の生のあらゆる領域における<合理化>の貫徹ということ。未来におかれた「目的」のために生を手段化するということ。現在の生をそれ自体として楽しむことを禁圧することにあった。…
見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』(岩波新書、2018年)
見田宗介(社会学者)は、「近代」という時代の特質をこんなふうに書いている。
この特質は、ぼくの心身にきざみこまれていた特質である。ぼくは、「つぎの山小屋」という「未来におかれた目的」のために、現在の楽しみ(花や草木たち!)を禁圧していた。「つぎの山小屋」が達成されることに、ぼくは「充実」を得ようとしていたわけである。それはそれなりに「充実」であっただろう。
けれども、ニュージーランドの自然それ自体、それから道中に出会ったスウェーデン出身の女性の「歩きかた=楽しみかた」は、ぼくの「生きかた」へのアンチテーゼであり、「現在の生をそれ自体として楽しむこと」というまっすぐなテーゼであった。
「しあわせは…」( 相田みつを)。- 香港の小道を歩きながら。
詩人であり書家の相田みつを(1924-1991)のことばに、よくとりあげられる、次のことばがある。
詩人であり書家の相田みつを(1924-1991)のことばに、よくとりあげられる、次のことばがある。
しあわせは
いつも
じぶんの
こころが
きめるみつを
ここでは「ことば」だけをひろったけれど、ぜひ、相田みつをの「書」を見てほしい。「書」のなかに、その一文字一文字、あるいは余白に、書を見る人それぞれに「何か」を感じるだろう。
ここ香港のレストラン(というより大衆食堂)で遅めのお昼をとった帰り道に、木漏れ日が射すなかを歩きながら、ふと、相田みつをのこのことばが思い浮かんだのであった。
このことばにはじめて触れたのはいつだったか。20年以上まえ、相田みつをの存在とことばをはじめて知り、読んだときにも、このことばに出会っていたような気もするけれど、定かではない。確かなのは、2010年に、東京フォーラムの相田みつを美術館での出会い(あるいは再会)である。
母が亡くなった喪失感のなかで、たまたま東京国際フォーラムの近くを歩いていたとき、なぜか、ぼくは相田みつを美術館にひきつけられたのだ。そして、そこで出会った相田みつをのことばたちに、ぼくは、ほんとうに支えられたのである。
そんなことばたちのひとつに、このことばがあった。
このことばは「あたりまえ」のことだと言われれば、そうかもしれない、とぼくは応える。
ぼくにとっては、ひとことひとこと、「しあわせ」も、「いつも」も、「じぶん」も、「こころ」も、そして「きめる」も、自明のことではないのだけれど、まずはそう応えるだろう。けれども、これらひとことひとことをいったん置いたとしても(日常意識でふつうにとらえたとしても)、この「あたりまえ」が実際にはすんなりと日常にはいっていかないところに、いろいろと考えさせられるのである。
「あたりまえ」のことであっても、頭ではわかっていても、あるいは心の奥深くにおいてわかっていても、いつのまにか、じぶんではない他者やモノに、じぶんの「しあわせ」が依存してしまっていたりすることがある。
相田みつをの「書」を見てみると、最後の「きめる」の文字が相対的に細めで、字がかすれている。わかっていても、「きめる」という動詞を日常に展開させることのむつかしさが、この文字の揺らぎにあらわれているように、ぼくには見える。
木々がゆれ、その先に海の存在を感じながら、ふと、相田みつをのこのことばがぼくの心に浮かんだのは、ようやく、このことばが語る経験をぼくが日常のなかで感覚し、生きはじめたからかもしれない。
それは、相田みつをの細く少しかすれた「きめる」の文字のように、決して力強いものではない。でも、生きる経験を積み重ねてゆくなかで、より深く感じるようになってきていることを、ぼくは思う。
「人生はかくも単純で、かくも美しく輝く」(村上春樹)。- アイラ島独特の生牡蠣の食べ方を一例に。
シングル・モルト・ウィスキーの「聖地」である、スコットランドのアイラ島での旅をつづった、村上春樹のエッセイ『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)。この本のなかで、ボウモア蒸溜所のマネージャーであるジムが、島でとれる生牡蠣の食べ方(あるいは、シングル・モルトの飲み方、とも言える方法)を村上春樹に教えるところがある。
シングル・モルト・ウィスキーの「聖地」である、スコットランドのアイラ島での旅をつづった、村上春樹のエッセイ『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)。この本のなかで、ボウモア蒸溜所のマネージャーであるジムが、島でとれる生牡蠣の食べ方(あるいは、シングル・モルトの飲み方、とも言える方法)を村上春樹に教えるところがある。
島独特の食べ方とは、生牡蠣にシングル・モルトをかけて食べる、という仕方である。「一回やると、忘れられない」という、この食べ方を、村上春樹は実際にレストランで試してみることにする。
レストランで生牡蠣の皿といっしょにダブルのシングル・モルトを注文し、殻の中の牡蠣にとくとくと垂らし、そのまま口に運ぶ。…それから僕は、殻の中に残った汁とウィスキーの混じったものを、ぐいと飲む。それを儀式のように、六回繰り返す。至福である。
人生とはかくも単純で、かくも美しく輝くものなのだ。村上春樹『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)
この箇所に触発されて、アイラ島ではないけれども(ぼくはまだアイラ島に行ったことがないがいずれ訪れてみたい)、生牡蠣にウィスキーをかけて食べる、という仕方を、これまでに幾度か、実際にやってみた。
確かに、一回やってみると忘れられない。なんともいえない風味と味わいが口のなかに残るのである。これが、アイラ島で、しかもそこでつくられるシングル・モルトであったらと想像すると、「至福の時」が思い浮かぶのである。
でも、このエッセイのこの箇所がぼくの記憶に残った理由は、この食べ方に加えて、村上春樹の言明にあった。「人生とはかくも単純で、かくも美しく輝くものなのだ」という、言明である。「生牡蠣にシングル・モルトをかける食べ方」はひとつの例として、ぼくのなかに根をはったのは、「人生とはかくも単純で、かくも美しく輝くもの」ということであった。
そのような見方で人生を見渡してみると、「かくも単純で、かくも美しく輝くもの」に充ちていることに気づくことがある。もちろん、人の生はそんな気づきがあったり、気づきから遠ざかったり、また深く気づいたりと、なかなかシンプルにいかないものだったりする。あるいは、頭ではそうとわかっていても、実感がわかなかったりする。さらには、「単純」ではない方向に生きていって、思っていたものが見つからないと嘆いたりする。
それでも、やはり気づくときがある。「人生とはかくも単純で、かくも美しく輝くものなのだ」ということを。
「生牡蠣にシングル・モルトをかける食べ方」よりもいっそう単純なこと、たとえば、朝の凜とした空気に身体をさらすこと、好きな人(たち)とことばを交わすこと、水をのむこと、などなどの、いっそうシンプルなことのなかに、ぼくたちは、人生が「かくも単純で、かくも美しく輝くもの」である実体を見出すのである。
最近はじぶんのまわりの整理整頓をすすめ、モノを減らしていっているのだけれど、そのプロセスのなかで、いっそうシンプルなものごとのなかに「かくも単純で、かくも美しく輝くもの」を見つけ出すようになってきていることを、ぼくは感じる。あるいは、逆に見れば、シンプルなものごとのなかに「かくも単純で、かくも美しく輝くもの」を見つけ出すなかで、整理整頓がすすみ、モノを減らすことができているのかもしれない。
とても疲れているときに、やはり本をひらく。- 心に灯を灯し、あたためる。
とても疲れているとき、思っている仕方では休まらないことがあるものである。寝不足があきらかであれば寝れば元気になるものだけれど、寝ても何か疲れがとれないことがあったりするものである。そんなとき、逆に身体を動かすことで疲れがとれることもあるし、たとえば、読書をすることで疲れがいやされるようなこともある。
とても疲れているとき、思っている仕方では休まらないことがあるものである。寝不足があきらかであれば寝れば元気になるものだけれど、寝ても何か疲れがとれないことがあったりするものである。そんなとき、逆に身体を動かすことで疲れがとれることもあるし、たとえば、読書をすることで疲れがいやされるようなこともある。
疲れ方にもよるけれど、読書をすることで疲れをとる、という方法をぼくは採用することが結構ある。読書に疲れたときも読書で疲れをとる、という方法を採ることだってある。
読書がー仕事のように感じる人にとっては、ありえない方法かもしれないけれども、ぼくにとっては、読書がそんな役割も果たしてくれるのだ。
もちろん、どんな本でもよい、というわけではない。
数冊の本を、だいぶ前に書いたブログ「ひどく疲れた日にそっと開く本 - 言葉の身体性とリズム」で、ぼくは挙げた。そこで挙げた、下記の本は、今でもぼくにとって特別な本たちである。
村上春樹『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)
見田宗介『宮沢賢治 存在の祭りの中へ』(岩波書店)
真木悠介『旅のノートから』(岩波書店)
ここ2週間ほど、『旅のノートから』はぼくの座右に(字のごとく「座右」に)置かれ、ときおりぼくは、真木悠介(社会学者)のことばの世界に降り立ってきた。真木悠介の「18葉だけの写真と30片くらいのノート」からなる『旅のノートから』は、真木悠介にとって「わたしが生きたということの全体に思い残す何ものもないと、感じられているもの」として書かれたことばたちである。
同じように、見田宗介(真木悠介)のパースペクティブを通して宮沢賢治の生を見晴るかした『宮沢賢治』。「同じように」というのは、この名著『宮沢賢治』において、「わたしが生きたということの全体に思い残す何ものもないと、感じられているもの」という視点が、「宮沢賢治」になげかけられているように、ぼくは感じるからである。(宮沢賢治は病に倒れて、志の途中で「挫折」したのだと考えている人には、見田宗介先生による「宮沢賢治」を一読されることをおすすめする。)
「わたしが生きたということの全体に思い残す何ものもないと、感じられているもの」に彩られたことばたちが、ぼくがじぶんの内側に灯を灯すのを手伝ってくれるのかもしれない。だからか、『旅のノートから』を本棚に戻してから、いつのまにか、ぼくは『宮沢賢治』を手にとっていた。
それから、今日もとても疲れていたところ、ぼくは、村上春樹の『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』を手に取ることにしたのであった。
村上陽子さんの写真(おそらく。少なくとも「カバー写真」は村上陽子撮影)を見ているだけでも心がやすらぐのだけれど、スコットランドとアイルランドの旅に触発された村上春樹のことばのリズムに、しずかに身をゆだねる。
村上春樹は語る。ことばがウィスキーであったならウィスキーのグラスを交わすように人と人はわかりあうことができるけれど、人はことばがことばでしかない世界で、ことばの「限定性」に限定されながら生きている。でも、「例外的に」と、村上春樹はつづける。「ほんのわずかな幸福な瞬間に、ぼくらのことばはほんとうにウィスキーになることがある」(前掲書)と。
ここのところぼくはウィスキーもお酒もほとんど(まったく)飲まなくなったけれど、村上春樹の差し出してくれることばを、まるでウィスキーのグラスを傾けるように味わい、心身をあたためている。
ユングの深い洞察と鮮烈なことば。- ユングへの「予感」。
いつか読むことがわかっている本、いつかはわからないけれどいずれ読むだろうと予感のする本、読みたいと思いつつどこかで「まだ」と思う本、「そんなことごちゃごちゃ言っている暇があれば今にでも本をひらけばいいじゃないか」という声が聞こえつつもじっと「時」が熟すのを待っている本。
いつか読むことがわかっている本、いつかはわからないけれどいずれ読むだろうと予感のする本、読みたいと思いつつどこかで「まだ」と思う本、「そんなことごちゃごちゃ言っている暇があれば今にでも本をひらけばいいじゃないか」という声が聞こえつつもじっと「時」が熟すのを待っている本。
ぼくにとってそのような本に、心理学者カール・ユングの著作がある。膨大な著作群である。(Carl Jung『The Collected Works』第1巻から第18巻がまとめられたデジタル版があるのだけれど、ページ数で1万ページほどにもなる。)
少し読み始めたことがあるのだけれど、ぼくの側が「準備」できていないし、どこかまだその「時」ではないような気がして、本を閉じてしまった。
けれども、カール・ユングとその精神分析の学びを「閉じた」わけではない。心理学者の河合隼雄(1928ー2007)、ユング派の分析家ロバート A. ジョンソン(Robert A. Johnson、1924-2018)など、ぼくが尊敬してやまない知性たちを通じて学んできた。
本だけに限らず、カール・ユングに特化したポッドキャスト(英語)でもさまざまな知見にふれることができるため、ときどき聞いたりしている。
でも、ぼくのなかで「まもなく、正面から読み始める」予感がわいてきている。
そんな予感を感じさせるのに充分な「震え」を、ユングの分析手法をとりいれている実践家の著書を読んでいるときに出会ったユングのことばに、ぼくは感じたのである。
When an inner situation is not made conscious, it happens outside as fate.
- Carl Jung, Aion: Researches into the Phenomenology of the Self
内的な状況が意識化されないとき、それは外部にて運命(fate)として起こるのである。
とても鮮烈である。ユングの生涯の後年に出版された本のなかに出てくることばだ。
ユング自身の分析と説明の全体にふれたわけではないので、ここではこの細部には立ち入ることはしないけれども、引用されたこのことばを目にしたとき、ぼくの内部で、ほんとうに「震え」が起きたのであった。
そんな「震え」のなかに、まもなくカール・ユングの著作群に向き合う「予感」をぼくは感じる。
「When an inner situation is not made conscious, it happens outside as fate. 」。ほんとうに核心をついた深い洞察とすごい表現である。
「取り越し苦労」をしない。- 「未来」を消極的に決めつけないこと。
思想家・武道家の内田樹は、内田樹の師匠の師匠である中村天風の「七戒」(怒るな、恐れるな、悲しむな、憎むな、妬むな、悪口を言うな、取り越し苦労をするな)にふれながら、そのなかの「取り越し苦労」をとりあげて語っている。
思想家・武道家の内田樹は、内田樹の師匠の師匠である中村天風の「七戒」(怒るな、恐れるな、悲しむな、憎むな、妬むな、悪口を言うな、取り越し苦労をするな)にふれながら、そのなかの「取り越し苦労」をとりあげて語っている。
「取り越し苦労」がそんなに危険なものなのかどうか、最初のうちはわからなかったのが、だんだんとわかってきたのだという。
内田 …ある程度年をとってくるとだんだんわかってくるわけですよ。取り越し苦労で、かなり危険なものだということが。これは怒りや嫉妬と同じくらい人間の心身を蝕む有害なものなんです。取り越し苦労って、要するに、時間を先取りすることだから。…未来というのは何が起こるかわからないから未来なのに、それをわかったつもりになって、その上、…マイナスの要素だけを確実に起こることだと思い込んで苦しむわけですから。取り越し苦労って、無限の可能性の中から限定した不幸な選択肢だけをよりのけて、「これが私の未来だ」と思い込むということですよね。…
内田樹・池上六郎『身体の言い分』(毎日新聞文庫、2019年)
たしかに、「ある程度年をとってくるとだんだんわかる」ということがある。年がすべてでは決してないけれど、年が教えてくれるものごともある。「取り越し苦労」の有害性についても、経験の積み重ねが教えてくれるところもある。
ビジネスなどでは最悪の事態を想定して対策を立てることがあるけれども、「取り越し苦労」は、悪い事態の想定がその道をふみはずして、起こる未来の「思い込み」のふかみにはまってしまうところである。
なお、中村天風自身のことば(『中村天風一日一話 元気と勇気がわいてくる哲人の’教え366話』PHP研究所)を見ておくと、「取り越し苦労の害」というところで、「百害あって一利なし」というように取り越し苦労にふれている。取り越し苦労をすればするほどに、心の消極的反映が運命や健康に悪い結果となってあらわれるのだ、と。
では、どうすればよいか。
「方法」はさまざまにあるだろうけれど、まず取っ掛かりとして、「取り越し苦労」の<異様さ>を、客観的にながめてみること。
「無限の可能性の中から限定した不幸な選択肢だけをよりのけて「これが私の未来だ」と思い込む」というように、一歩立ち止まって「取り越し苦労」のあり様をながめてみると、その思い込みの<異様さ>が明るみに出てくるようだ。自分のことでなく、他者の「取り越し苦労」を見つめてみることで、「思い込み」のあり様が見えてくる。
もちろん、頭でその<異様さ>がわかっても、実際に心配の連鎖を断ち切ることは容易ではない(こともある)。
実際に断ち切っていく方法も、いろいろな側面からいろいろに試されるところであるけれども、ここでひとつ挙げておくとすれば、<方法としての思い込み>である。
「取り越し苦労」は「消極的で不幸な思い込み」であるのと同じく、その逆の方向に、「積極的で幸福な思い込み」をつくってしまうことである。方法として意識化されている思い込みだ。それを支えるのは、人が語る「物語」の力である。人には、物語を語る力があるのである。
一度でうまくいくものではないかもしれない。ここでも、時間と経験を味方につけてゆくことである。
憶い起こせば、海のある風景。- <海の風景>に耳をかたむける。
それなりの年数を生きてきたなかで、自分の住んできた「場所」をふりかえってみる。より正確には、ここ香港で海をながめて、いろいろとかんがえていたら、世界のいろいろな<海の風景>がぼくのなかで重なってきた。そこでふりかえってみると、確かに、<海の風景>が幾重にも重なっているのを、じぶんの内面に見る。
それなりの年数を生きてきたなかで、自分の住んできた「場所」をふりかえってみる。より正確には、ここ香港で海をながめて、いろいろとかんがえていたら、世界のいろいろな<海の風景>がぼくのなかで重なってきた。そこでふりかえってみると、確かに、<海の風景>が幾重にも重なっているのを、じぶんの内面に見る。
<海の風景>。ぼくはそこに特別な感情をもちあわせているようだ。
世界のいろいろなところを旅したり、暮らしてきたりしたなかで、それぞれの<海の風景>の記憶が、ぼくのなかで重なっているのを深く感じる。思えば、<海の風景>にぼくは惹かれてきたようでもある。意識的に選んだわけではないのだけれども、ぼくの深いところにある憧憬や願望がかたちになった結果かもしれないと考えてみることもできる。
ぼくの生まれ故郷は浜松で、やはり「浜」に面している。家から、海の「浜」まではだいぶ距離があるのだけれども、どこかで「浜」から吹く風を感じているようなところがあったかもしれないと思う。
その浜松を離れ、大学に通うために移った東京も海に連なっている。
大学1年のときのはじめての海外は、上海であった。それも、横浜からフェリー(鑑真号)にのって、海をわたり、上海に到着した。翌年は、はじめての飛行機による海外であったが、ここ香港に降り立った。香港から広州へと行き、そこから向かったベトナムも、海に連なるところであった。旅の途中の<海の風景>(ニャチャンの砂浜などの風景)がぼくの記憶に残っている。
それからワーキングホリデー制度を利用して住んだニュージーランドも、いつも<海の風景>があり、また海に限らず、<水に祝福された風景>とでもいうべきところであった。
大学を卒業して、最初に赴任した場所は、西アフリカのシエラレオネ。首都フリータウンは海に面している。シエラレオネにつづいて赴任した東ティモールも、海に囲まれた島である。首都ディリは海の香りがただよっている。
それから、ここ香港。「港」と言われるように、暮らしのなかに海がある。毎日、ぼくは海の存在をこの身体に感じながら生きている。
こんなふうにしてこれまでをふりかえってみると、ぼくの周りにはいつも<海の風景>があったこと、そしてそこには特別な感情が生きていることを感じる。でも、そのことを「ことば化」することはむつかしい。<海の風景>に触発される気持ちは、ぼくの深奥からやってくるようなものにも感じる。そんな深奥からひっぱりだしてきて「ことば」にしようとした途端に、気持ちとことばの大きなギャップを感じてしまう。
だから、「ことば」に<あらわそう>とするのではなく、「ことば」が<あらわれる>のを待つのがひとつの仕方である。
そんなことをかんがえていたら、「助け舟」のような存在を、ぼくは憶い起こしはじめる。
例えば、小説家・詩人のD・H・ロレンス(1885-1930)、哲学者・思想家のカール・シュミット(1888-1985)、解剖学者の三木成夫(1925-1987)など。ロレンスも、三木も、カール・シュミットも、この大地に生きながら<海の存在>をまなざしながら思考を深め、ことばを紡いだ。
<海のある風景>に身をおきながら、彼らの「ことば」にふたたび耳をかたむけようと、ぼくは思う。そんな「ことば」たちを導きの糸としてどんなところに行くことができるのか、いまから楽しみである。
人間を「鏡」に映す。- 「人間ではない存在」に照らされる<人間>。
「ただ生きる」ということ。それは、なんとなく生きていくというのではなく、むしろ、<生きる>ということの経験のひとつひとつを味わい、経験しつくしてゆく生きかたである。呼吸をすること、食べること、家族や友人と話をすること、身体を動かすこと、このようななんでもないことを味わいながら生きること。
「ただ生きる」ということ。それは、なんとなく生きていくというのではなく、むしろ、<生きる>ということの経験のひとつひとつを味わい、経験しつくしてゆく生きかたである。呼吸をすること、食べること、家族や友人と話をすること、身体を動かすこと、このようななんでもないことを味わいながら生きること。
このような「なんでもないこと」が、人が人として生きるうえでの<歓び>であることを、「人間ではない存在」を通して気づいてゆく。そんな気づきを誘発する装置として、例えば映画やドラマなどがある。
映画やドラマで「人間ではない存在」(たとえばエンジェル)が<人間になる/人として生きる>というようなストーリーが描かれることがある。映画『City of Angels』(1998年)でニコラス・ケージが演じるエンジェルがそんな存在であり、最近では、アメリカのテレビシリーズ『Lucifer』の登場人物たちが挙げられる。
「人間ではない存在」を軸として、<人間である>、<人として生きる>ということはどういう経験であるかを逆照射させてくれる装置だ。「人間ではない存在」が人として「ただ生きる」ことのひとつひとつのなかに、人でなければ経験できないものごとを鮮烈に体験してゆく。なんでもないような、ひとつひとつの出来事が、まるで奇跡のように体験されるのである。
このような「架空の存在」を方法とすることもひとつだけれども、それらとはまったく逆に、現実の「ロボット」という人間ではない存在から、「人間の生きる」ということに光をあてていくこともひとつである。
ロボット工学者の石黒浩は、工場などで使われるロボットではなく、「人間と関わるロボット」をモチーフとしてきた。人間が日常生活を営むなかで、人間のように作動するロボットである。
そのプロセスでは、「人間とは何か?」が問われる。
人間の日常は複雑そうに見えながらも、たとえば朝起きて、電車に乗って仕事場に行き、そこで人と話をしながら書類を作成するなどして、ふたたび電車に乗って家に帰ってくる、といったパターンをとりだしてみると、三つに分けられるのだと石黒は語る(石黒浩『ロボットとは何かー人の心を映す鏡』講談社現代新書、2012年)。
● 移動すること
● 人と関わり人と話をすること
● 決められた作業をすること
これらのなかで「移動すること」と「決められた作業をすること」は工場のロボットもするけれど、大きく異なるのは「人と関わり人と話をすること」となる。ここに石黒の関心も、ロボットの可能性も、それから難しさがある。難しいのは、工場のロボットは「目的」をもってタスクを遂行していくのに対し、人と関わるロボットは、予測不能な人間と関わってゆくことになるからだ。
「面白さ(関心)」と「可能性」、それから「難しさ」が、人間の予測不能性に関わることは、当たり前に聞こえるかもしれないけれど、<人間とは何か>という質問に対する応答の核心をつくところでもある。
石黒浩は、この研究についてつぎのように書いている。
…日常生活とは、人間が活動する場であり、そこで働くものはロボットでも人間でも、人間を意識する必要がある。すわなち、「人間と関わる機能」を作ることが、研究の中心的な課題になる。この研究を、人間とロボットの相互作用(ヒューマン–ロボットインターラクション)と呼ぶ。
この「人と関わるロボット」の研究開発のもっとも大きな特徴は、ロボットの開発と人間についての理解を同時に進めなければならないという点である。石黒浩『ロボットとは何かー人の心を映す鏡』(講談社現代新書、2012年)
「人間ではない存在」、ここでは「人と関わるロボット」を通して、<人間とは何か>が追求されてゆく。本の副題が直接に示しているように、人を映す「鏡」として、ロボットが存在している。
「人と関わるロボット」や「人工知能」などはさしあたりテクノロジーの発展のなかに位置づけられるけれども、他方で、近代・現代を生きてきた人間がその豊かな生を追い求めながら、そのプロセスや先端で出会うことになる問いたち、<人間とは何か>、<人が生きるとは>などを入り口としてひらかれてきた分野かもしれないと、ぼくは思ってみたりする。
「ただ生きる」ということ。- 生きるために生きること。
「ただ生きる」、ということ、そのむつかしさについて、真木悠介(社会学者)が書いている。
「ただ生きる」、ということ、そのむつかしさについて、真木悠介(社会学者)が書いている。
なんのために生きているんだろう、という問いは、じぶんが生きるという「物語」のどこかで、ひとそれぞれに違った仕方でおとずれる。そんな問いをふつふつと内面で燃やしていたころに、ぼくはこの文章に出会った。
詩人の山尾三省(1938-2001)の本、『自己への旅』(聖文社、1988年)の「序」として書かれた文章(「伝言」)で、その後、真木悠介のとても美しい著作『旅のノートから』(岩波書店、1994年)に収録された。
真木悠介がはじめて屋久島にわたり、山尾三省の仕事場に泊まったときのことが書かれている。
ある晩に、『自己への旅』の本にも登場する神宮君がやってきて、「オキナワに絶対に行く、そこで漁師をするんだ」とくりかえし語っていたことにふれながら、翌朝、山尾三省と向き合っているとき、「神宮君はどうしてオキナワに行くのかな」と半分ひとりごとのように真木悠介が言ったところで、こんな応答があったのだという。真木悠介はつぎのように書いている。
「神宮君は、ふつうに生きる、ことをしたいのね。ただ生きる、ということを、したいのよね」
水屋の方から、順子さんの声がした。
わたしはどこかで、よくわかった、という気がした。ただ生きる、ということをしたい。
するともういちど、わからなくなった。ただ生きる、とは、どう生きることか? ふつうに生きる、とは、じっさいに、どういうことか? 三省も順子さんも、神宮君も、ただ生きること、ふつうに生きる、ということを求めて、屋久島に来たのだと思う。
ふつうに生きる、ことのむつかしさ。今の世の中で、ただ生きる、ということの、むつかしさ。
…真木悠介『旅のノートから』(岩波書店、1994年)
「ただ生きる」ということをする。確かに「わかる」ようで、わからない。
「ただ生きる」ということは、なんとなく生きていくというのではなく、<生きる>ということの経験のひとつひとつを味わい、経験しつくしてゆく生きかたである。呼吸をすること、食べること、家族や友人と話をすること、身体を動かすこと、このようななんでもないことを味わいながら生きること。
映画やドラマで「人間ではない存在」(たとえばエンジェル)が<人間になる>というストーリーが描かれることがある。それは、<人として生きる>ということはどういう経験であるかを逆照射させる視点だ。人間ではない存在が人として「ただ生きる」ことのひとつひとつのなかに、人でなければ経験できないものごとを鮮烈に体験してゆく。ひとつひとつの出来事がまるで奇跡のように体験される。
ところで、「なんのために生きているのか」という問いは、生きることの「意味」への渇望である。生きていることに「意味」を与えてくれる「目的」への指向性である。ぼくたちは、目標や目的、意義や意味によって、日々の生を賦活することができる。
けれども、より思考を深めてゆくと、人は「生きるために生きている」のだということへといきつく。ぼくはそう思う。
「なんのために生きているのか」という切実な問いは、<生きる>という経験が(そのひとつが、それらのいくつかが、あるいはほとんどが)、なんらかの事情で、損なわれていることからくるものでもある。
真木悠介がふれている、今の世の中で「ただ生きる」ということのむつかしさは、こんなところとも関連していると思う。それにしても、今の世の中、「ただ生きる」ということは、確かにむつかしい。
ただ生きること。生きるために生きること。そんな地点から、じぶんの「生きる」を眺め返してみると、異なった風景が見えてくる。
香港で、急に「暑さ」がやってきて。- 「トランジション(移行期)」には心身を落ち着かせること。
5月の香港はこんなに暑かっただろうかと思うほどに、ここのところ香港は暑い。日中は33度ほどまで気温が上がり、夜も28度ほどである。湿気もあって、すでに「夏」を過ごしているかのようである。
5月の香港はこんなに暑かっただろうかと思うほどに、ここのところ香港は暑い。日中は33度ほどまで気温が上がり、夜も28度ほどである。湿気もあって、すでに「夏」を過ごしているかのようである。
今日はそんな暑さに自然が反応してか、雨がときおり降りそそいで、夜は暑さがやわらいでいる。
香港では、「暑さ」も、冬の「寒さ」も、突然にやってくることがある。ようやく冬が過ぎたかなと思っていると急に暑くなったり、あるいはまだ暑いなぁと思っていると急に寒くなったりするのである。
香港に来て12年にもなるので、そんな「急な季節の変わり目」に向けて気持ちの準備はしているのだけれど、それでも身体はやはり少しびっくりしてしまうようだ。今回もこの「暑さ」で、夜中に目が醒めてしまった。
エアコンはここ5年以上も家では使っていないから、扇風機をつけたりしてなんとかやりくりしてきた。それでも暑かったりするのだけれど、そんなこんなで過ごしていると、心身ともに、暑さに慣れてきたようだ。
季節の変わり目はこんなふうに急な「移行」をもたらしたりすることがある。そんなとき、過剰に反応して、暑さ対策や寒さ対策をとったりしてしまうことがある。けれども、いつも思うのだけど、その「ある程度の期間」を越えると、心身の調整が効いてきてふつうになるときが、やがてやってくる。過剰反応する必要はなかったりするのだ。
これは「季節の変わり目」だけに言えることではない。
ぼくたちの「人生の変わり目」、住む場所が変わったり、学びや仕事が変わったりするときも、いろいろなことが変わることから、人は心身ともに過剰反応してしまうことがある。いろいろなもの・ごとの「トランジション(移行期)」にである。
生きることの経験を重ねてきたなかでぼくが思うのは、季節の変わり目と同じように、「ある程度の期間」を越えると、やがてふつうになるときがやってくるものだ。ここでいう「ふつう」とは、日常化して、慣れることである。
もちろん、そうなったからといって、個人それぞれに特有の問題・課題が解決するというわけではない。でも、はじまりには「すごく大変だ」と思っていたことが、やがてそこまでは思わなくなるものだ。
だから、ぼくたちが「トランジション(移行期)」を迎えるとき、「ある程度の期間」をはじめから見据えて、時間を味方につけること。ぼくたち自身の「心身の調整機能」を信じること。そうして、心身を落ち着かせること。
香港の暑い日々を迎えながら、そんなことを、ぼくは思う。
よりミニマルな生きかたを求めるプロセスでの学び。- 「やってみないとわからないことがある」という学び。
モノを減らしながら、よりミニマルな生きかたを求めるプロセスでの「学び」は、ほんとうに多様で、思っている以上に厚みがある。
モノを減らしながら、よりミニマルな生きかたを求めるプロセスでの「学び」は、ほんとうに多様で、思っている以上に厚みがある。
人は「自分が何者か」ということを、たとえば所有するモノによって意味づけてゆくことがある。明確に意識していなくても、いつのまにか、モノが「自分」をかたちづくり、終わりのない所有への欲動が作動する。あるところまではこの方法はうまくいくかもしれないけれど、そのような生きかたのなかで、<自分>が見えなくなってゆく。
だから、モノを減らしてゆくことは、<自分>をふたたび取り戻してゆくプロセスとも言えるのだけれど、モノによって支えられてきた「自分」がそこに存在しているから、モノを減らしてゆくことは怖かったりするし、ただモノだけでなく、内面の「何か」を失ってしまうような感覚にとらわれることもあるのである。
そのような感覚を経験しながら、そのプロセスは、そこに飛びこむ者たちに、多様で厚みのある「学び」をもたらしてくれることになる。
どんなモノに囲まれ、どのようなモノが隠れていて、それらがどのようにしてそこに存在しているのかなど、プロセスのひとつひとつに立ちどまって耳をすましてみると、それらは必ずや「何か」を教えてくれるものである。
今は使っていないけれど棚にしまわれているモノ、使っているけれど粗末にあつかってしまっているモノ、歓びを感じないけれどそこにあるモノ。あるいは、それらのモノの置かれかた、などなど。それらのモノを通して、それらのモノを入り口として自分の内面に降り立ちながら、そこで感じたり、考えたりすることに目をこらし、耳をすます。
そこに、「自分」と「世界」とのつながりかたの輪郭があらわれるのである。
そこまで書いて、べつのブログでふれた山本七平の(1921-1991)ことばが浮かんでくる。日本人の「働く」ということに見られる精神構造についてであるが、これと同じ精神が、上述のような態度にも見られるのかもしれないと、自分の精神を括弧に入れる。
…日本人が働くのは経済的行為ではなく、「仏業の外成作業有べからず。」と同じ、一切を禅的な修行でやっているにほかならない。農業即仏行であり、サラリーマン即仏行であり、働くことはすべて仏行、メーカーが物を作り出すのは一仏の分身として世界を利益するため、またセールスマンは巡礼である。みなが、それによって、貪、瞋(しん)、痴の三毒から解放されて成仏するためにやっている…。
山本七平『日本資本主義の精神ーなぜ、一生懸命働くのか』(1979年)※電子書籍版(PHP文庫)
ここで、禅とエコノミック・アニマルが「同じ発想」からきているのだと山本七平は語っているが、「片づけ」のプロセスにも同じ発想が生きているのだろうか。「片づけ」を機能だけで見るのか、あるいはそこに修行を見出すのか。
ところで、よりミニマルな生きかたを求めるプロセスでの学びを得てきたなかで、より深く感じたのは、「やってみないとわからない」ことである。このことをすべての事象に適用しようとは思わないけれども、「やってみないとわからないことがあるのだ」ということである。
ヘルマン・ヘッセの名著『シッダールタ』で、シッダールタは「教え」だけにうずもれるのではなく「経験したいんだ」という気持ちを抱いて「世界」に旅立っていったけれど、物質的によりミニマルな生きかたも、経験してみることである。
そこには何もないかもしれないし、自分にとって大切な「何か」が存在しているかもしれない。存在と不在の振れ幅をふくめての、経験ということである。
「自分」をバージョンアップさせてゆく。- たとえば、海外で暮らしてゆくなかで。
「自分」であること。一貫性をもった振る舞いかたで、どこにいっても、どんなときも「自分」をもっていること。確固とした「自分」であること。そのような、不動で、確固とした、強い個人像のようなものが有効であり、また強く信じられることがある。
「自分」であること。一貫性をもった振る舞いかたで、どこにいっても、どんなときも「自分」をもっていること。確固とした「自分」であること。そのような、不動で、確固とした、強い個人像のようなものが有効であり、また強く信じられることがある。
その有効性も感じながら、海外でそれなりにながく暮らしてきて思うのは、むしろ、これと逆のありかた、柔軟で、一見すると個がないように見える振る舞いの有効性である。
ぼくたちは、ある文化のなかで生まれ、育てられるなかで、その文化や環境に適合性のある仕方で教育され、そのように振る舞うことが期待され、ときには反感をもちながらも、期待に応えるように振る舞い、生きてゆく。
でも、国際化やグローバル化のなかに身を投じることでより明確にわかってくるのは、そのようなある文化のコードは、ぼく(たち)の人間性の一面にすぎないということである。ある文化で高く評価される一面が、他の文化にいけば、まったく評価されないということがある。「謙虚さ」などは、わかりやすい例かもしれない。日本で大事にされるある種の謙虚さが、異文化のなかで負の側面となって現れることにもなるのだ。
そんな状況にでくわすときは、自分の振る舞いの「自明性」に疑問がなげかけられるときでもある。これまで「A」と教えられ、Aの振る舞いを身体にきざんできたのが、あるときそれと反対の「Z」も大切で、環境や状況によっては有効なんだということを体験していく。
自分にとってデフォルト「A」の振る舞いに対して、反対の振る舞いかた「Z」を学んでゆく。Aを捨ててしまうのではなく、Aも残したままでZもとりこんでいく。AもZも自分の振る舞いかたとして、そのいわば人間の特質の<全体性>を獲得していく。
<全体性>を獲得した個人は、環境や状況に応じて、どちらにも柔軟に振る舞うことができる。そんなふうにして「自分」をつくっていく。そして、それは反対の振る舞いを排除しないという仕方で、<多様性>にひらかれていく仕方でもある。
柔軟に主体を変えてゆく構えは、あたかも、日本的な「主体」であるようにも見える。日本では、「主語」は置かれる立場などによって変わるし、また「主語」がその<場>に投じられて消えてしまうこともある。
けれども、ぼくが経験から思うのは、一度、その日本的な主体から<出ること>が大切なのだということである。つまり、確固とした「主体」を、いつも変わらない「主語」(I)で生きてみることである。
そのうえで、どちらも自由に行き来できるようなところに、バージョンアップさせてゆくことである。
「学び方」を学ぶこと。- 修業としての「トイレ掃除」の本質。
思想家・武道家の内田樹の『日本辺境論』(新潮新書)というきわめてスリリングな本のなかで、内田樹は、師弟関係における「トイレ掃除」について書いている(「便所掃除がなぜ修業なのか」)。
思想家・武道家の内田樹の『日本辺境論』(新潮新書)というきわめてスリリングな本のなかで、内田樹は、師弟関係における「トイレ掃除」について書いている(「便所掃除がなぜ修業なのか」)。
弟子から見て「無意味だと思われる仕事」、たとえばトイレ掃除などを、師弟関係を師弟関係として発動させてゆくために、師は弟子にあたえる。一般に語られる話の形では、弟子は修業に直結するような、もっと有用なことを求めたくなる。師に向かってそんなことを頼むことはできない、というのがよくある形だけれど、なかには、師に向かって頼んでしまう、という展開の話もあるだろう。いずれにしと、師弟関係におけるトイレ掃除は、師弟関係を語る際によく語られてきたものである。
トイレ掃除そのものに「意味」を見出してゆくというように語られることもあるけれど、内田樹は、よりファンダメンタルに、「学び方」を学ぶ、ということへの道筋を見ている。
「もっと有用なことを…」という弟子ではなく、黙々とトイレ掃除をする弟子には「感情」の変化がやがておとずれる。その変化のうつりゆきは、態度と感情の矛盾のなかで、「無意味なこと」をしている自分を合理化しようとする、心の安定化作用のうちに見て取られることになる。
黙々とトレイ掃除をする弟子は、つぎのような変化を経験していくことになると、内田樹は書いている。
…「…先生はあまりに偉大なので、そのふるまいが深遠すぎて、私には『意味』として察知されないだけである」というかなり無理のある推論にしがみつくようになります。「私は意味のあることをしている」という「正しさ」を立証するために、「私には何に意味があるのか、よくわかっていない」という「愚かさ」を論拠に引っ張り出す。おのれの無知と愚鈍を論拠にして、おのれを超える人間的境位の適法性を基礎づける。それが師弟関係において追い詰められた弟子が最後に採用する逆説的なソリューションなのです。
「私はなぜ、何を、どのように学ぶのかを今ここでは言うことができない。そして、それを言うことができないという事実こそ、私が学ばなければならない当の理由なのである」、これが学びの信仰告白の基本文型です。
「学ぶ」とは何よりもまずその誓言をなすことです。そして、この誓言を口にしたとき、人は「学び方」を学んだことになります。…内田樹『日本辺境論』新潮新書
こうして「学び」の誓言をし、「学び方」を学んだものは、どんなものや人からも学びを引き出せるようになる。師から「何か」を学ぶということよりも、「学び方」を学ぶことで、弟子の学びの翼は飛翔する。翼を獲得することで、どこまでも飛んでゆくことができる。
トイレ掃除の「意味」ということにとどまらず、それよりもファンダメンタルな次元において、「学び方」を体得してゆく。このうつりゆきに、師弟関係における修業の本質がやどっている。
もちろん、今の時代はしかし、「無意味なこと」に不寛容なところをもちあわせているようだ。それがよいのかわるいのかということは簡単に言うことはできないけれど、「学びの信仰告白の基本文型」をどのように手にすることができるのか、ということは肝要なことであると、ぼくは思う。
問題のありかとしての「世間の目」をわきまえる方法。- 山本七平が受けた訓言から。
著書『「空気」の研究』でよく知られている山本七平(1921-1991)の『日本資本主義の精神ーなぜ、一生懸命働くのか』(1979年)をとりあげて、ここのところブログを書いた。『日本資本主義の精神ーなぜ、一生懸命働くのか』のほかに、本のタイトルにひかれてぼくの「本棚」にならんでいる山本七平の著作に、『無所属の時間』(1978年)がある。
著書『「空気」の研究』でよく知られている山本七平(1921-1991)の『日本資本主義の精神ーなぜ、一生懸命働くのか』(1979年)をとりあげて、ここのところブログを書いた。『日本資本主義の精神ーなぜ、一生懸命働くのか』のほかに、本のタイトルにひかれてぼくの「本棚」にならんでいる山本七平の著作に、『無所属の時間』(1978年)がある。
そのなかに「世間の目」というエッセイが収められている。山本七平は出版社を経営していたことはあまり知られていないのではないかと思われるけれど、その山本七平が出版をはじめたときに、本の箱の大メーカーT製函所の社長から言われた言葉からはじまるエッセイだ。
そのT製函所の社長は、山本七平につぎのように語る。
「ちょっと調子がよいと、世間は、実態の三倍も四倍も調子がよいと見るものですよ。そしてちょっと調子が悪いと、世間は、実態の三倍も四倍も調子が悪いと見るものですよ。そりゃ、世間がどう見ようと世間の勝手てことは、理屈としてはいえますよ。しかし案外自分のことは自分ではわからないもので、世間の目で自分を見てしまうことが多いんですよ。それが失敗のもと、問題はここですな。ここさえちゃんとわきまえていれば、大丈夫です」。…
山本七平「世間の目」『無所属の時間』(1978年)※PHP研究所、電子書籍版(2013年)を参照
経験と実感と振り返りから生成されてきた言葉であることが感じられ、ここには世界で生きてゆくための知恵がある。
理屈ではわかっていながら、どうしても「世間の目」で自分を見てしまう。自分のことは自分ではわからない、という迷宮にまよいこみながら。
「世間の目」ということで、山本七平はマスコミの報道がそれにあたること(また程度の差はあれそうであるしかないこと)を述べたあとで、「海外からわれわれを見る目」、および「われわれが海外を見る目」も同じであることへと、知恵を展開させる。
日本や日本社会を徹底的に見つめてきた山本七平ならではの「視点」が重なられるわけである(日本や日本社会を見つめるうえでは、時間的あるいは空間的に、べつの国や社会を思考にもちこむ必要がある)。
それにしても、阿部謹也(1935~2006)がかつて「世間とは何か」と問うたように、「世間」はそれだけで興味深いキーワードである。
山本七平は「ちゃんとわきまえる」方法についての質問を忘れない。「ちゃんとわきまえるには、どうしたらいいんですか」と山本七平が尋ねると、社長は、「簡単なことですよ」と言いながら、つぎのように応答されたのだという。「…一人におなんなさい。一人の時間をつくって、自分で自分のやっていることを、一つ一つ点検すりゃそれでいいんですよ。それだけですよ。」と。
それは聴いてみれば、たしかに「簡単なこと」でありながらも、「なるほど」とうなずかされる方法である。
そして、「一人の時間」をつくることができるか、また「一つ一つ点検する」ことがうまくいくかどうかは、もう一歩も二歩も先のことだとも思うのである。
「世間の目」は、ぼくたちの日常のさまざまなところにはいりこんでいて、この「自分」のなかにも内面化されている。一人になっても、「世間の目」は追いかけてくることもあるのだ。
だから、どのようにして「一人の時間」をもち、どのように「一つ一つ点検する」のかということも問われてくる。
その仕方はさまざまにあるだろうけれど、ぼくの経験と実感から言えば、「今いる空間」の外に出て、一人の時間をもち、異なる時間の流れのなかで「自分」の一つ一つを点検することが方法として挙げられる。端的に言えば、「異文化」の体験である。旅であれ、移住であれ、異なる文化の環境を、ぼくたちは豊饒に生かしてゆくことができる。ぼくはそう思う。
ポール・マッカートニーに生きつづける<ビートルズの精神>。- 『Get Enough』(2019年)の響きのなかに。
同時代のなかで、ポール・マッカートニー(Paul McCartney)がつくり歌う曲を聴くことができるのは、ぼくにとってしあわせなことである。
同時代のなかで、ポール・マッカートニー(Paul McCartney)がつくり歌う曲を聴くことができるのは、ぼくにとってしあわせなことである。
ビートルズはぼくが生まれるまえに解散してしまったし、ジョン・レノンはぼくがビートルズとその4人を知るまえにこの世を去ってしまったから、同時代において、ポール・マッカートニーの曲を聴くことができることは歓ばしいことだ(もちろん、リンゴ・スターも曲をつくり歌いつづけてくれている。が、ここは、ポール・マッカートニーの話である)。
さらに、76歳(1942年生まれ)のポール・マッカートニーが、いまでも<ビートルズの精神>でもって、<新しい試み>をつづけていることには勇気づけられるのである。
今年2019年の1月1日にシングル曲が世に放たれているなんて知らなかったぼくは、その『Get Enough』という曲を聴いたとき、ひどく心が揺さぶられた。「ポール・マッカートニー」的なメロディーを色調とする曲なのだけれど、それは、思いもしなかった(現代的な)仕方でアレンジがほどこされていたからである。
そこでは、「Auto Tune」のテクノロジーによって、ポール・マッカートニーの歌声が変声されているのだ。ビートルズが時代をきりひらいたよう革新性はないけれども、(ぼくの知るかぎり)ポール・マッカートニーの曲づくりにおいて<新しい試み>である。
そしてなにはともあれ、そのことが、時代をきりひらく革新性よりも、ある意味において(ポール・マッカートニー自身にとっても、聴く人たちにとっても)大切なことであったように、ぼくは思う。
そのポール・マッカートニーは当初、Auto-Tuneを使うことで反感をかうのではないかと懸念していたようなのだ。けれども、新しい技術を積極的に受け入れるビートルズの精神にもとづき、<新しい試み>へとふみきったという(※参照:Wikipedia「Get Enough (Paul McCartney song)」)。
ぼくは個人的に反感をもたない。もたないどころか、ポール・マッカートニーの声の新鮮さと深みを感じるのである。
数々の名曲(「Yesterday」「Let It Be」「Hey Jude」など)をつくってきたポール・マッカートニーが型にはめられた「ポール・マッカートニー」におしこめられるのではなく、<ビートルズの精神>によってひらかれてゆく方向性に、ぼくは惹かれる。
正直に言えば、(あの)「ポール・マッカートニー」に期待してしまう気持ちもないわけではない。どこかで、「Yesterday」や「Let It Be」や「Hey Jude」などを超える曲がでてくることを期待し、望んでいる。けれども、それ以上に、ポール・マッカートニーがどのように(またどこに)「ポール・マッカートニー」を超えでてゆくのかに、あるいは「ポール・マッカートニー」を生ききるのかに、ぼくは関心があるのである。
そんなことを思いながら、『Get Enough』の響きに耳をかたむける。そこに、<ビートルズの精神>を聴きとりながら。
「資本主義の精神」について。- マックス・ヴェーバーが注目する<ベルーフ>としての職業。
じぶんの生きかたをまなざし、考えるとき、ただ「じぶん」だけをまなざすのではなく、「じぶん」を歴史(時間)と地理(空間)のなかに位置づけることが必要である。どんな時代に、どんな場所に生きているのか。
じぶんの生きかたをまなざし、考えるとき、ただ「じぶん」だけをまなざすのではなく、「じぶん」を歴史(時間)と地理(空間)のなかに位置づけることが必要である。どんな時代に、どんな場所に生きているのか。
歴史と地理を視野にいれてゆくとき、いろいろなキーワードがあるけれど、なかでも「資本主義」はとても大きなキーワードだ。
今日(5月1日)は「Labour Day」でここ香港も祝日であるが、そんな日に、資本主義とのかかわりのなかで「仕事」ということについて少しふれておきたい。ここのところ、大澤真幸(社会学者)の著書『サブカルの想像力は資本主義を超えるか』(角川出版、2018年)を読んでいて、「仕事に宗教的な意味合いが入ってくる」という興味深い文章に触発されたことも、ここで書く理由のひとつである。
「資本主義」と聞くと、経済合理性の極みのような響きを聞き取ることになるが、実際の事情はけっしてそれほど単純ではない。
大澤真幸は、古典中の古典といわれる『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』における、マックス・ヴェーバーの説にふれながら、「仕事に宗教的な意味合いが入ってくる」ことについて語っている。ヴェーバーの説は、書名にあるように、プロテスタントの倫理のなかに資本主義の精神のベースがあるというものである。この説の「正しさ」は別としても、かんがえさせられる内容だ。
大澤真幸がヴェーバーの説のなかで焦点をあてたのが、ドイツ語の「ベルーフ」という言葉である。
この言葉は聖書に出てくる概念だという。世界史を学んだ人は知っているとおり、昔のヨーロッパでは、ラテン語の聖書しか使われていなかったところに、ルター(たち)がドイツ語に訳して、聖書をひろく一般に読めるようなものにする。そこで出てくるのが、「ベルーフ」という概念である。
このベルーフのもととなるのは、ギリシャ語の、クレーシスという概念でした。このクレーシスは「神から呼びかけられる」という意味です。難しい言葉ですが、日本語では「召命」と訳されます。
この「神からの呼びかけ」とは、具体的には各人の仕事、職業のことを指します。日本語の感覚ですと、「これは俺の天職だ」と言う時の「天職」に近い。何か自分に運命的に定められている、このために生まれてきたのだという仕事です。
…
この召命、ベルーフという言葉を、ドイツ語の聖書では職業という意味で使った。このことは非常に重要な意味合いを持った、というのがマックス・ヴェーバーの説です。大澤真幸『サブカルの想像力は資本主義を超えるか』(角川出版、2018年)
「靴職人」の例を、大澤真幸は挙げている。
靴職人である場合、靴をつくることには、さまざまな意味がある。靴がない人につくってあげるといった利他的な行為、あるいは、自分が生きていく糧として靴をつくる、など。けれども、そこに「ベルーフ」の概念がはいってくると、それらの意味をこえて、神が「おまえは靴職人として定められている」と呼びかける感覚を得ることになる。つまり、こうして、「仕事に宗教的な意味合いが入ってくる」ことになる。
資本主義には、この感覚が非常に重要だったというのがマックス・ヴェーバーの説だというわけだ。
これらにふれて、資本主義の世界で「成功」するには仕事に<ベルーフ感>がないと難しい、と大澤真幸は語っているが、確かに「お金を儲けよう」だけでは到達できないところに、<ベルーフ感>のある仕事をしている人たちをつれてゆくだろう。
なお、現在でも、自己啓発系の本などでは「宗教の信仰」にふれられることなく(「神」としてふれられることもあるけれど)、この「召命」が語られているのを目にすることがある。たとえば、それは神からでなくとも、じぶんの内側から聴こえる「calling」というような仕方で語られるのである(資本主義の「アメリカ」について、思っている以上に「宗教」の理解が肝要であることを思う)。
ぼく自身は特定の宗教を信仰はしないけれども、「仕事に宗教的な意味合いが入ってくる」というときの、この「宗教的な意味合い」をより一般化されたかたちで理解することで、ヴェーバーの説を読み取ることができる。
なお、大澤真幸はこれにつづく次の節で、「資本主義になると、すべての日が聖日になる」と、ヴァルター・ベンヤミンの説(「宗教としての資本主義」)をひきあいにだしながら展開している。
ふつう、信仰がある人にとっては「日曜日」が大切で、日曜日には日常の仕事をしてはいけないところ、資本主義になると日常の仕事こそが宗教的行為のひとつになるというのが、ベンヤミンの語るところだというのだ。
つまり、すべての日が聖なる日であり、神から与えられたものとして労働するというように、資本主義のなかではなってゆくのだという。「職業」(ベルーフ)が、神から呼びかけられたものとしての行為であるというヴェーバーの説に重ねられることになる。
このような視点をふまえたうえで、「資本主義」を見つめなおしたり、人にとっての「職業」や働きかたを考えてゆくと、視点を得るまえとでは異なった仕方で対象が現れてくる。
<欲求を解放する>ということ。- 節制や抑制ではなく、「解放する欲求」を生きること。
現在あるかたちの「消費化社会」が、地球の環境問題をふくめて、大きな「負の影響」をおよぼしている。
現在あるかたちの「消費化社会」が、地球の環境問題をふくめて、大きな「負の影響」をおよぼしている。
という状況において、この「消費化社会」をどうしていったらよいか、という解決の方向性として、その物質主義的なありかたを抑制してゆくことを考えてみることができる。今の「消費」のありかたが異常で過剰だから、節制と抑制でもって「消費」をおさえてゆこう、という解決の仕方である。「消費」への欲求はとめどないから、抑えこまなければいけない、というわけだ。
これは解決の方向性のひとつであるし、実際に「有効」でもあったりする。「もっとも」な意見であるように聞こえる。
見田宗介(社会学者)が、名著『現代社会の理論ー情報・消費化社会の現在と未来』(岩波新書、1996年)で提示した方向性は、しかし「消費への欲求」そのものを、「消費」というコンセプトをつきつめることで、解き放ってゆくというものであった。「禁欲」という道ではなく、不羈の仕方で「歓びを追求する」道である。
この方向性と方法にぼくは惹かれる。
節制や抑制や禁欲という道よりも、欲求そのものを解放するという道は魅力的である。
<欲求を解放する>という方法については、上述の本が書かれるよりも20年ほど前に、真木悠介のペンネームで発刊された名著『気流の鳴る音』(筑摩書房、1977年)に、「混沌と投げ込まれているモチーフたち」(真木悠介)のひとつとして書かれているのを見つけることができる。
「欲求の解放」とはなによりも、欲求そのものの解放である。欲求を解放するとは、解放する欲求を生きること、対象を解放し、他者を解放し、自己自身をたえず解放してゆこうとする欲求を生きることである。
真木悠介『気流の鳴る音』(筑摩書房、1977年→ちくま学芸文庫、2003年)
なお、<欲求を解放する>ということに対して、「野放図なエゴの相克」をまねくという反論がなされるだろうことを、真木悠介はあらかじめ視野にいれている。そのような反論をする人たちは、「人間が人間にたいして狼であるというホッブス的な幻想を、アプリオリに前提している」というように。(それにしても、ホッブスの著書『リヴァイアサン』に描かれるような、ホッブス的な世界観(「万人の万人に対する闘争」)は相当に根強く、人びとの内面にひそんでいるのだということを、ぼくは感じる。)
「節制や抑制や禁欲」が必要なことも生きているなかではあるけれど、それらには限界があるし、なによりも抑圧された欲求はどこかで別の抑圧に転化したり、爆発を起こすことにもなる。「サステイナブル(持続可能的)」ではない、とぼくは思う。
ぼくは、<欲求の解放>の道をえらぶ。
これは、個人としての生きかたでもある。「解放する欲求を生きること、対象を解放し、他者を解放し、自己自身をたえず解放してゆこうとする欲求を生きること」である。不羈の仕方で、<欲求の解放>を生きることである。
食べるときの「おいしさ」について。- 「おいしさ」への感度に向けて。
食事をしながら、ふと、「おいしさ」についてのことがあたまに浮かんでくる。
食事をしながら、ふと、「おいしさ」についてのことがあたまに浮かんでくる。
「おいしさ」とはどのように可能なのか。そんなことかんがえていないで、おいしいものを食べればいいじゃないか、とも思うけれど、世界のいろいろなところでそれなりに年をかさねて生きていると、「おいしさ」ということをかんがえてしまうものである。
「おいしさ」をつきつめてゆくと、そこには食べ物や料理という方向というよりは、この自分の心身にいきつく、と、ぼくは思う(もちろん、食べ物や料理をつきつめてゆく方向にも「おいしさ」を追求していく方向もある。「コーヒー」生産にたずさわってぼくとしても、そのことは重々承知である)。
自分の心身の状態によって、質素な料理もこれ以上ないほどおいしくいただけるし、逆に、どんなに手のこんだ料理も(あまり)おいしくいただけないことがある。
だいぶ前のことだけれど、中国を鉄道で旅していたときに列車のなかで食べたインスタント麺はほんとうにおいしかったし、ニュージーランドの自然のなかで食べるお米もどこまでもおいしかった。
鉄道の旅では寝台で眠り、勝手がよくわからなくて長い時間ほとんど食べずに過ごしていたところ、なにかがきっかけでインスタント麺を手にいれ、中国の人たちにまじって、片言の中国語で会話をしながら、食べたのであった。ニュージーランドでは、一日中歩いたりしたあとに、キャンプ用の小さいガスコンロでお米を炊き、自然に囲まれた環境で食べる。なんでもないものが(というとそれぞれの食べ物に失礼だけれど)、まるで心身にしみいるのだ。
ほんとうに「おいしさ」を感じたときの体験といったとき、ぼくはそんなときのことを憶い出す。
共同通信社の勤務から作家となった辺見庸の作品に、『もの食う人びと』(角川出版、1994年)があるが、『もの食う人びと』の旅で辺見庸が到達した「地点」はそんなところであったと、ぼくは記憶している。「おいしさ」は、最終的には、この「自分」によるのだということ。
通信社では北京特派員やハノイ支局長をつとめ、「現実を直視」してきた辺見庸が、バングラディシュや旧ユーゴやソマリアやチェルノブイリなどで、人びとは今何を食べて、何を考えているかを探っていった『もの食う人びと』の旅での到達点である。
「おいしさ」のことがあたまに浮かびながら、この『もの食う人びと』の旅の到達点のことも憶い起こされる。
最後は自分の心身だからといって、食べ物や料理のおいしさ追求を蔑むわけでは決してない。むしろ、逆である。自分の心身へといきつくことが、同時に、自分の外部のことへの感度を獲得してゆくことである。そんなふうにかんがえる。
問題なのは、自分の心身を忘れて、ただただ、この外部(高価な食べ物、高価な料理など)へと傾倒してゆくことである。そんなことは(ほんとうは)わかっていながら、いつのまにか、このような「外部のもの」へと依存してしまったりするものである。
不思議なもので、自分自身を忘れてしまいがちなのだ。そうして、自分の「外部」にあるものが問題なのだと信じて疑わなくなる。「外部」にあらわれるものは、見えるし、聞こえるし、「明らか」であるからである。
「おいしさ」を感じなくなったとき、ぼくたちは、食べ物や料理ではなく、まずは、自分自身を疑ってみることができる。自分自身の「おいしさ」への感度のことを。
「未来」の使いかた。- 未来は「未知」であるという前提の生きかた。
「未来」を手にいれたとき、それは人間にとって、大きな「解放」であった(古代日本人にとっての「未来」はつぎの収穫までの時間ほどであった、など)。けれども、近代・現代は「未来」を極端な仕方で、あるいは間違った方向に向けてしまうようでもある。
「未来」を手にいれたとき、それは人間にとって、大きな「解放」であった(古代日本人にとっての「未来」はつぎの収穫までの時間ほどであった、など)。けれども、近代・現代は「未来」を極端な仕方で、あるいは間違った方向に向けてしまうようでもある。
人は、<今、ここ>の生を充実させることもできるし、あるいは<未来>の目標によって今を充実させることもできるのだけれど、未来が、現在の生を抑圧したり、不安をかきたてるものとなってしまうのだ。
思想家・武道家の内田樹は、「不思議なことなんですけれど」と前置きをしながら、「未来は未知だ」と思っていない人たちのことを語っている(内田樹・池上六郎『身体の言い分』(毎日新聞文庫、2019年))。つまり、未来は「わかっている」と思っている。
少なくとも、「未来はわかっている」というような仕方で、発言し、行動している。そういう人たちについてである。「未来はわかっていますか?」という質問を正面から投げかけたら、「わからない」と応えるかもしれないけれど、言動が、「未来はわかっている」ということを前提としているかのように、見聞きできるのだ。確かに、不思議なこと、である。
ある日、出版社の女性編集者が内田樹のもとにやってきて、「30代女性のこれからの生き方ガイドブック」のようなものを書いてほしい旨を伝える。この年頃の働く女性は悩み、苦しんでいる。結婚はするほうがいいのかしないほうがいいのか、子どもは産むほうがいいのか産まないほうがいいのか、どのように老いてゆくのがいいのか、等々。
平均寿命が85歳として今が35歳、あと50年間をどのように過ごしたらよいかと訊いてくるわけだ。「正しい老い方のガイドブック」のようなものを望んでいる。そんな依頼がきたわけである。
内田樹は、びっくりして、「このような発想そのものが根本的に人を不幸にしているのだ」として、つぎのように語っている。
内田 …残りの50年をプログラムさえ正しく組めば、好きなようにコントロールできるつもりでいる。でも、やるべき仕事の日程がかっちり決まった50年間を目の前にして、その空白をただ塗りつぶしていくような生き方をしたら、それって囚人が出獄までの残り日数を数えているような人生でしょう。カレンダーを×でつぶしていくような生き方をしていて、「正しい×の付け方」を教えてくださいって言ったって、おもしろいわけないじゃない、そんなこと(笑)。
…筋書きなんてわかったら、生きている甲斐がないじゃないかってぼくは思うんですけど。…何が起こるかわからないからこそ、自分のもっている全知全能をあげて、新しく出現してくる局面に立ち向かえるわけですよね。未知の局面に遭遇する時にこそ、人間のパフォーマンスって飛躍的に向上するわけでしょう。…内田樹・池上六郎『身体の言い分』(毎日新聞文庫、2019年)
「未来」がひとつの「解放」ではなく、「牢獄」となってしまっている。「未来」というものを取り違え、「未来」の使いかたがズレてしまっている。
自分の未来にたいする不安から、未来をコントロールしたい欲求が起こり、コントロールできると思い込み、「カレンダーを×でつぶしていくような生き方」をしている。不安はなくなったわけでなく、下部ではたらきつづけ、不安とコントロールによって倍増された言動がくりひろげられる。
このようなことは「個人」に帰するだけでなく、近代・現代という時代の社会構造のうちにも、その根拠をもっているものだ(真木悠介『時間の比較社会学』岩波書店)。
「未来」をもったとき、それは、人間にとって、大きな「解放」であった。「未来」を抱くことで、どれだけのビジョンがかたちとなってひらけてきたことだろう。
でも、それは、使いかたがズレてしまうと、解放どころか、人を「牢獄」に閉じこめてしまう。
「未来」の使いかたを、まちがってはいけない。