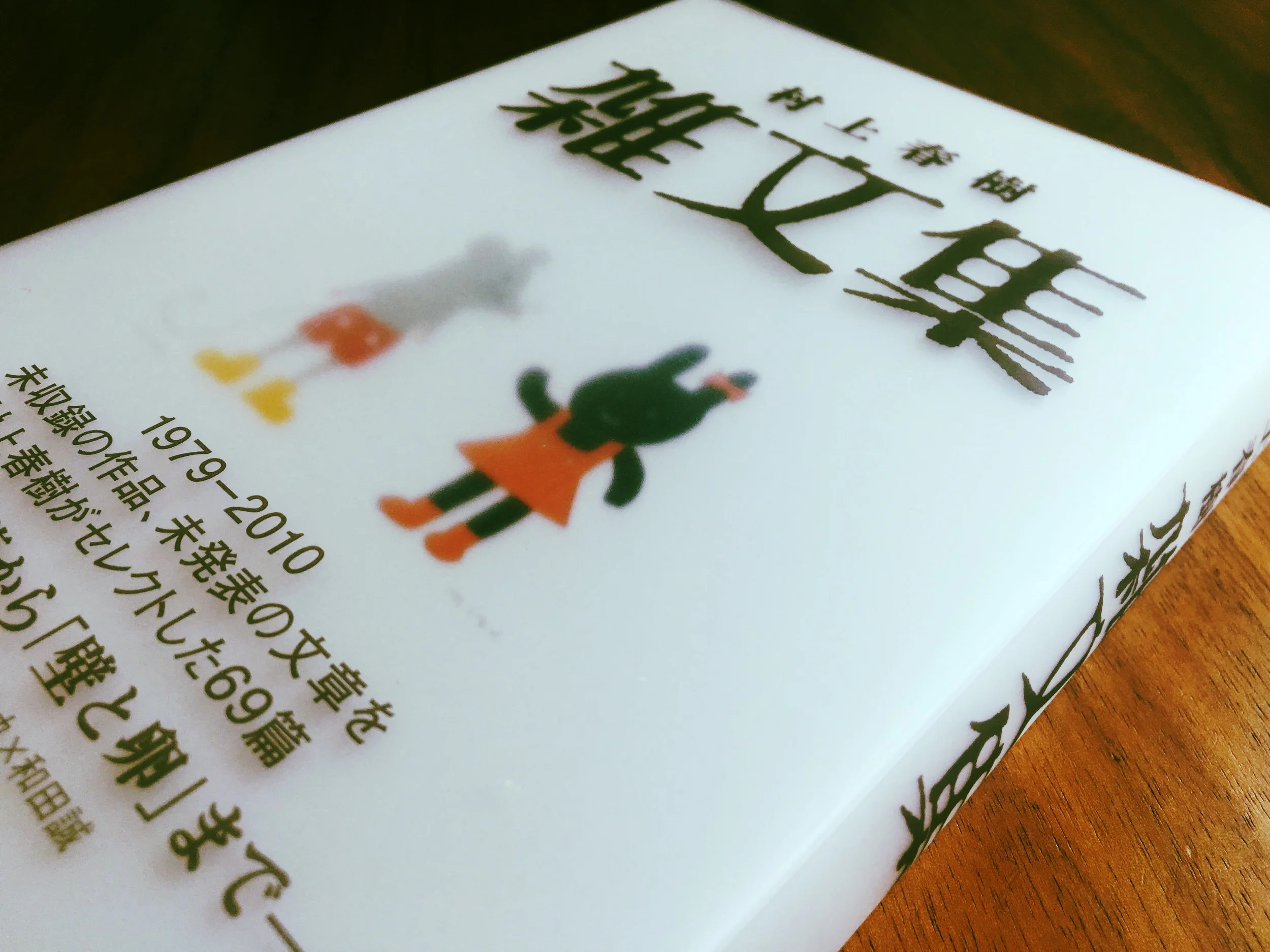じぶんの「前提とする人間像・個人像」に気づくこと。- 「理論」に深く深くわけいって学んだこと。
経済学でも政治学でもなんでもよいのだけれど、「理論」というものに深く深く入ってゆくときに、ぶつかる課題は、理論構築において「前提にしている人間像・個人像」である。
経済学でも政治学でもなんでもよいのだけれど、「理論」というものに深く深く入ってゆくときに、ぶつかる課題は、理論構築において「前提にしている人間像・個人像」である。
学問に限らず、個人や組織などでの人と人とのコミュニケーションにおいて「ズレ」が生じてくることの原因のひとつに、語る個人たちそれぞれが「前提にしている人間像・個人像」がある。
ぼくは、かつて、経済学者アマルティア・センの「理論」に深くわけいりながら、そのことを学んだ。
ひとつには、「経済学」が想定してきた人(行為者)である。
経済学は、自己の帰結状態から得られる私的利益の最大化を目標として合理的に行動する人間を前提にして、理論構築される。
近代の学問では、このような想定のうえで理論は積み上げられていくことから、いったん人間をそのように前提にして理論構築することは決して間違いではない。
けれど、いつしか、その「前提としている個人」が所与のものとなり、見えなくなり、構築された理論が「当たり前のこと」のように語られていってしまう。
アマルティア・センは、「合理的な愚か者」という論考において、経済学が前提とするこの「前提」に目を向け、人が、経済活動において、倫理観や道徳的な価値における選択をすることもある視点を導入して、内在的に経済学をひらいていくことになる。
また、アマルティア・センの理論が想定している「個人」は、自律・自律した「強い個人」であるという批判が寄せられていたことも、理論が「前提としている人間像・個人像」をかんがえさせられる。
理論が前提とし得る、「弱い個人」と「強い個人」という視点である。
詳細には入らないけれど、AさんとBさんがコミュニケーションをとるときに、Aさんは「弱い個人」を前提に話をすすめ、Bさんは「強い個人」を前提に話をすすめているのであれば、そこに会話のズレが出ることは、容易に想定できる。
このような、そもそもの「前提」としている人間像・個人像は、構築される理論や世界像などの全体を、違ったものにしていってしまう。
繰り返しになるけれど、このことは学問の世界だけにかかわることではなく、ぼくたちの日々の生活の隅々にまでかかわってくる。
そして、世界はますます多様化しており、「個人」を狭く捉えることはますます実態とそぐわなくなってきている。
このような世界において、まずできることは、じぶんが「前提」にしている人間像・個人像に気づくことであるように、ぼくは思う。
日々のいろいろな体験を通して、気づいていくことからである。
「Oldies(オールディーズ)」の音楽が交響した時代と現代。- 「Oldies」をとりまく現象を見る。
英語圏の音楽には「Oldies(オールディーズ)」と呼ばれる、一群の音楽がある。
英語圏の音楽には「Oldies(オールディーズ)」と呼ばれる、一群の音楽がある。
「一群の音楽」と書いたけれど、それはぼくのなかでの「Oldies」の感覚であって、Wikipedia(英語版)では「radio format(ラジオ・フォーマット)」というように書かれていて、(Wikipediaの記述の正確性はともかくも)「なるほどなぁ」と思う。
Oldies is a radio format that concentrates on rock and roll and pop music from the latter half of the 20th century, specifically from around the mid-1950s to 1970s or 1980s.
(オールディーズとは、20世紀後半、特に1950年代半ば頃から1970年代あるいは1980年代におけるロックおよびポップミュージックを集結させるラジオのフォーマットである。)
“Oldies” Wikipedia (※日本語訳はブログ著者)
ラジオというものが今とは異なった仕方で生活のなかに溶け込んでいる時代が20世紀の後半にはあって、そのなかに「Oldies」の音楽を届けるラジオ局がある。
1996年にニュージーランドに住んでいたころ、旅に出る際に小さいラジオをバックパックに入れ、テントを張っては、そこにラジオを立てかけて、そこからながれる「Oldies」の音楽に耳をかたむけていた。
確かに、そこには、「ラジオ・フォーマット」として、すてきな音楽の入り口が用意されていた。
「Oldies」という一群の音楽の象徴としては、1973年のアメリカ映画「American Graffiti」の世界がある。
この映画の世界は、「Oldies」という音楽世界そのものを体現するように描かれている。
映画には、1950年代半ばから1960年代にかけてのロックおよびポップミュージック、つまり、バディ・ホリー、チャック・ベリー、プラターズ、ビーチ・ボーイズたちの音楽の響きが鳴りわたる。
「Oldies」をとりまく現象として触れておきたいことは、大きく2つある。
ひとつに「Oldies」という「時代のきりとり方」があり、もうひとつに「Oldies」の音楽世界と現在の世界風景のズレのようなものである。
一つ目の「Oldies」という「時代のきりとり方」として面白い現象は、「Oldies」というラジオ・フォーマットが含む「時代」の変化である。
Wikipediaにあった記述のように、どこまでを「Oldies」として含めるか、つまり1970年代までか、あるいは1980年代までかは、時代の変遷とともに変わってきたようだ。
映画「American Graffiti」の世界のような1950年代から1960年代の「Oldies」は、ときおり「Golden Oldies」とも呼ばれてきたようで、しかし、2000年以降、「1970年代」の音楽が含まれ、やがて、「1980年代」の音楽も「Oldies」と呼ばれ始めたりしている(※Wikipedia「Oldies」)。
「近代・現代」という(経済発展の)時代の駆動力のひとつは、常に「新しさ」へと、製品を更新してゆくことである。
古いものも「リバイバル」という形で更新されてもゆくけれど、古いものは「新しさ」の装いを身にまとう。
音楽が「10年単位」で捉えられ、そこに時代の色を灯していることは面白いことだけれど、なにはともあれ、広義の「Oldies」には、1950年代から1980年代にかけての音楽の異なる色彩をひとつにまとめてしまうような力学が、2000年以降に働いてきたのである。
そのことが、二つ目の「Oldies」の音楽世界と世界風景のズレのようなものにも、つながっている。
1990年代に聴き、またときにバンドで演奏していた「Oldies」の音楽は、まだ当時、その響きは、生きている世界と交響するところがあったように、ぼくは思う。
1950年代や1960年代の音楽が1990年代の世界で流れていても、そこにはまだ、音楽と世界をつなぐ糸がつながっていた。
しかし、2018年の今、「Oldies」の音楽は、世界とのつながりを欠いてしまっているように、ぼくは感覚している。
ぼく個人としては、「Oldies」はとても好きだから、Apple Music(香港)の「Radio」のなかに創られた「経典老歌OLDIES Radio」局を選んでは、よく聴いたりしている。
ただし、そこに、今現在の「世界」とのつながりが、著しく欠けてしまっている/弱くなっているように感じるのだ。
だから、ぼくはぼくの内面の世界に、そのつながりを取り戻すように聴いている。
アメリカのベビーブーマーたちが10代を迎え、アメリカが繁栄を迎えたあの時代に生まれてきた「Oldies」。
それらの音楽の響きのなかに立ちながら、現代を見るとき、そこにある時代の落差のようなものの深淵が見える。
しかし、時代は古いものを「Oldies」に含めて定義し直しながら、それらと現代との稜線を書き換え、時代の間の深淵をもふさぐようにして変遷している。
香港で、ポピュラーな「日本食」をかんがえながら。- 「日本食」(例えば、とんかつ)の歴史を学ぶ。
香港で、ポピュラーな「日本食」を思い起こしてみる。
香港で、ポピュラーな「日本食」を思い起こしてみる。
特定の店の特定のメニューのようなものではなく、一般的な市民権を得ているものとしては、(ぼくの限定的な観察と感覚をもとに)挙げるとすれば、以下の日本食が挙げられる。
● 寿司(また刺身)
● ラーメン
● うどん
● とんかつ
この他にも、カレー、しゃぶしゃぶ、牛丼、焼き鳥、抹茶などがあるけれど、例えば牛丼は圧倒的に吉野家であったりして、多様なひろがりなどを考慮していくと、例えば、上記のような日本食が挙げられる。
また、インスタント麺の「出前一丁」は、一般的な市民権ではなく、特別な市民権を獲得している。
さらに、ここでは「お菓子」類は入れていないけれど、どこに行っても、日本のお菓子(ポテトチップスからポッキーまで)であふれている。
ぼくが小さい頃からあった、チロルチョコやアポロ、うまい棒だって、家のすぐ近くで買うことができる。
このようにして、日本食は、香港の至るところで、さまざまな形で見ることができるし、もちろん食べることができる。
現在的な香港では、「肉」and/or「揚げ物」という組み合わせは好まれるようで、香港でも好まれる「とんかつ」にぼくは興味をもち、そもそも「とんかつ」って何だろうと疑問がわく。
ぼくは肉と揚げ物は探し求めるほど積極的に食べないけれど、「とんかつ」というものに、ぼくは関心を抱いてきた。
香港に来てからのことである。
柳田國男の著作『明治大正史:世相篇』(講談社学術文庫)のなかに、「肉食の新日本式」という項目が立てられ、柳田國男は「肉食率の大激増」などにふれている。
…われわれは決してある歴史家の想像したように、宍(しし)を忘れてしまった人民ではなかった。牛だけははなはだ意外であったかもしらぬが、山の獣は引き続いて冬ごとに食っていたのである。家猪(ぶた)も土地によっては食用のために飼っていた。…ただ多数の者は一生の間、これを食わずとも生きられる方法を知っていたというに過ぎぬ。だから初めて新時代に教えられたのは、多く食うべしという一事であったとも言える。…
柳田國男『明治大正史:世相篇』講談社学術文庫、1993年
柳田國男の記述は、肉料理の詳細にまでふれているわけではない。
そこで手にしたのが、岡田哲『明治洋食事始め:とんかつの誕生』(講談社学術文庫)で、「とんかつ」そのものに焦点を当てながら、しかし「明治の洋食」という大状況を捉えている著作である。
岡田哲は、柳田國男の著作からもいろいろと着想を得ながら、牛肉の料理である牛鍋やすき焼き、それから1887年に牛丼の元祖である牛飯屋の出現などを詳細に追っている。
これらの詳細はそれぞれに興味深い研究と視点を提示しているけれど、ここでは、「とんかつ」がつくられる歴史の結論的流れにだけ、ふれておく。
…「とんかつ」がつくられる歴史は、一つのドラマを構成している。1872年(明治五)に、明治天皇の獣肉解禁があり、1929年(昭和四)に、とんかつが出現するまで、六〇年近い歳月が流れている。すなわち、牛鍋がすき焼きにかわる頃から、庶民の肉食への抵抗が揺らぎはじめていた。その後六〇年をかけた先人たちの努力の積みかさねにより、日本人好みのとんかつができあがった。…
岡田哲『明治洋食事始め:とんかつの誕生』(講談社学術文庫)
このドラマの結論的なこととして、岡田哲は、次のようなドラマの筋を挙げている(前傾書)。
① 牛肉から鶏肉、そして豚肉への変遷
② 薄い肉から分厚い肉への変遷
③ ヨーロッパ式のサラサラした細かいパン粉から、日本式の大粒のパン粉への変遷
④ 炒め焼きからディープ・フライへの変遷
⑤ 西洋野菜の生キャベツの千切りを添える
⑥ 予め包丁を入れて皿に盛る
⑦ 日本式の独特なウスターソースをたっぷりかける
⑧ ナイフやフォークではなく箸を使う
⑨ 味噌汁(豚汁・しじみ汁)をすすりながら食べる
⑩ 米飯で楽しむ和食として完成する
この変遷が、前述のように、六十年をかけてなされていく。
こうして、岡田哲はこれらをたんねんに見ながら、日本の食文化の核心にせまっていく。
これまで当たり前のように食べてきたもののルーツを辿っていく。
日本にいたときはそれほどその「ルーツ」に興味はわかなかったけれど、海外に住んで、海外でいわゆる「日本食」の受容のされ方を観察したりしているうちに、ぼくは「ルーツ」を知りたくなった。
「とんかつ」はどのようにして、今ここ(香港)にあるのだろうか、と。
じぶんの生きてきた日本文化も説明できないようでは、という思いもある。
そして、柳田國男や岡田哲の著作に目を通しながら、「じぶんは何も知らないじゃないか」と、思ってしまう。
海外に「どれくらい住んでいるか」ということをめぐる体験。- 「滞在期間の相対性」を超えてゆく。
海外に住んでいると、「どれくらい住んでいるのですか?」「来て、どのくらいになりますか?」という質問が、会話のなかで交わされたりする。
海外に住んでいると、「どれくらい住んでいるのですか?」「来て、どのくらいになりますか?」という質問が、会話のなかで交わされたりする。
そのような質問が交わされる理由として、ただ「相手を知る」ことや会話の進め方を見定めていくための情報収集ということがある一方で、ときおり、「滞在の長さ」を前提とした「相手の意見等の見定めるための<メガネ>」となってしまうようなことがある。
長い滞在をよしとする、滞在の長さの競い合いのような様相だ。
「来て●ヶ月(●年)じゃ、…だよね」というような応答のなかに、優越の響きが聴こえ、聴いている方としては肩身の狭い思いをしたりする。
そのような肩身の狭い思いの経験があるから、ぼくは、このような質問を相手に投げかける側になる場合、「ぼくが尋ねているのはそんな優越のためなんかではなくて、話をしている相手のプロフィールを知るための情報のひとつとして聴いているのですよ」という話し方と声の響きとなるように、気をつけたりする。
「滞在の長さ」ということに戻ると、それはとても相対的なものだ。
どれくらいの期間をもって「長い」と言うのかは、比較対象の長さによってしまう。
ぼくは香港に住んでまもなく11年になるけれど、11年なんて、20年や30年あるいはそれ以上いる方々にとってみれば、なんでもない長さである。
社会学者の真木悠介(=見田宗介)はメキシコに1年ほど滞在していたときのことを、次のように書いている。
旅をする人の観察について、永く住む者の目からは「よく分かっていない」というような批評を目にすることがある。わたしは直感的に、それをイヤミな言い方だと思うことがある。わたし自身、メキシコに1年位いた時に、数日だけ日本から訪れてきてメキシコのことを語ったり書いたりする人のものを、表面的だと思ったこともある。けれども10年位も前にメキシコ人と結婚してメキシコに住みついているT教授などの目からみるなら、1年しかいないわたしの観察など、数日間の旅行者のそれと同じだろう。…
真木悠介『旅のノートから』岩波書店、1994年
真木悠介は、さらに、「22歳かにペルー経由でメキシコに来て50年以上になるという…わが敬愛する大老人」を挙げて、大老人(荻田さん)のただ一つのわるいくせは、10年位しかメキシコにいないT教授のような人も、「何も分かっとらん」ということであったことを書いている。
…その荻田さんだって、先祖代々のメシーカ族の子孫からみれば「旅の人」みたいなものなのに!
そうして旅の人にしかみえない真実というものもある。…
真木悠介『旅のノートから』岩波書店、1994年
真木悠介のとる「時間軸」は、とてもひろい。
「先祖代々のメシーカ族の…」と書く真木悠介の時間軸は、この「先祖代々」というようにひろがってゆく時間に向けられているようにぼくには聴こえ、一人の人間が生きる生涯ほどの時間は、まるですべての人が「旅の人」であるかのように感じさせるところがある。
香港も、香港に長くいることで、見えてくるものもあるように思う。
少なくとも、ぼくにとっては、すぐには見えないこともあった。
しかし、旅人や短期滞在者だからこそ見えるものもある。
旅人や短期滞在者の見たものあるいは語るものが、表層的であるかもしれない。
ただし、長くいることで見える深いものごとも、見方が偏見化され固定化されてしまい、別のものを覆い隠してしまうかもしれない。
「滞在の長さ」は、その土地や環境を知るための、あくまでも、要素のひとつでしかない。
大切なことは、海外というその土地や環境に、じぶんがひらかれる仕方であり、視点や視野の豊饒さと持ち方であり、またオープンさと見方の組み合わせによる柔軟性である。
そしてそのように外部にたいしてひらかれながら(また同時にじぶんにたいしてひらかれながら)、どのようにそこの環境において他者とかかわってゆくのかということが、滞在の長さにかかわらず、大切なことのように思う。
身体の記憶として残っている「黙考」。- 小さいころに、学校で教わっていたこと。
ぼくが小さかった頃、学校(小学校か中学校かと記憶が定かではないけれど中学校のように思う)で「黙考」という時間が日課のひとつとして、(おそらく)毎日とられていた。
ぼくが小さかった頃、学校(小学校か中学校かと記憶が定かではないけれど中学校のように思う)で「黙考」という時間が日課のひとつとして、(おそらく)毎日とられていた。
「黙考」とは、字のごとく、「黙って考える」ことである。
確か、給食による昼食、お昼休み、掃除の時間が終わって、午後のクラスに入る直前だったと思うけれど、1分ほどの時間、目を閉じて「黙って考える」時間が、やってくる。
ぼくの記憶では、黙考の時間は、スピーカーから何らかの音色が流れていたように思う。
放送が入り、席に着席し、目を閉じ、音色にあわせて「黙考」する。
普通の公立の学校で、そんな具合に、「黙考」のための時間がとられていた。
当時は「何も考えない」というように指示を受けていたようにも、ぼくは記憶している。
けれども、「何も考えない」ということは、やってみるとわかるけれど、至難の技である。
美術家の横尾忠則は、かつて「坐禅」の世界にどっぶりと入っていた時期に、浜松市(ぼくの生まれ故郷である)の竜泉寺での「坐禅修行」の体験を、次のように書いている。
…「何も考えない」ことに徹しようとする。ところが何も考えないということは不可能なのである。意識がある限りぼくの心は動く。心が動くことは当たり前である。
この心の動きがぼくの本姓なのだ。生きているから心が動いているのであると、また自分にいいきかせる。
横尾忠則『わが坐禅修行記』角川文庫、2002年(原著:1978年)
横尾忠則は当時30歳頃の体験であったのとは異なり、ぼくは自我意識の形成途上のような成長段階であったけれど、ぼくも、横尾忠則と同じように、「何も考えない」ことはできずに、ただ心の動きを感じ、心の落ち着きの方へと方向性を変えていた。
それにしても、毎日の日課のうち、この「黙考」を、ぼくは身体で覚えている。
多くのことを覚えていないなかで、しかし、「黙考」のことは覚えている。
当時は目的なんかは考えずに、ただ、学校の日課にしたがっていただけのことであるけれど、30年ほど経過しても、まだ覚えているから、不思議なものである。
気がつけば、現代においては、米国を中心としてメディテーションやマインドフルネスが見直され、仕事の合間、個人の日課、米国の学校教育などにもりこまれている。
異なる文化に生きる人たちがじぶんたちとは異なる文化の事象に光をあてる。
その光に逆照射されるようにして、ぼくはじぶんの生きてきた文化を見かえしてみる。
そしてぼくも、仕事の合間に、あるいはふとしたときに「黙考」を、今でも、生活にとりいれている。
そのような体験・経験をもとに、以前であればまったく目にも入ってこなかったような著作『わが坐禅修行記』を手にして、そこに聴こえてくる横尾忠則の息づかいに耳を澄ましたりしている。
柳田国男の「生の基底」のような旅(真木悠介)。- 旅人の気もちと視力につらぬかれる生。
民俗学者の宮本常一のノート「野帖」が、研究のための旅も、シンポジウムでの対話も、読書も、宮本常一にとって旅のようなものとしてあったことを、シンポジウムなどで隣席となった社会学者の真木悠介は、<旅の方法としての学問>というように書いている。
民俗学者の宮本常一のノート「野帖」が、研究のための旅も、シンポジウムでの対話も、読書も、宮本常一にとって旅のようなものとしてあったことを、シンポジウムなどで隣席となった社会学者の真木悠介は、<旅の方法としての学問>というように書いている(真木悠介『旅のノートから』岩波書店)。
また、真木悠介は、官僚さらに民俗学者であった柳田国男にとっての「旅」も、同じ方向性においてとりだしている。
柳田国男が晩年に朝日新聞社に招かれた時、年に2ヶ月は旅行をするために休暇をほしいという条件を出して、「客員」という形式にしてもらったという。旅はそれほど、柳田の学問だけでなく生の基底のようなものであった。
真木悠介『旅のノートから』岩波書店
真木悠介は、柳田国男の名著『遠野物語』に付された折口信夫の「解説」にふれ、「…まして二十年前、若い感激に心をうるまして、旅人は、道の草にも挨拶したい気もちを抱いて過ぎたことであらう」と、遠野を歩いていた柳田をおもいうかべる折口信夫共々、生の基底のようなもとして「旅」というものがあった二人の呼応する生を見ている。
宮本常一にとって読書も「旅のかたち」であったと真木悠介が言うのと同じく、柳田国男にとっても読書も「旅のかたち」のようなものとしてあった。
柳田国男は「読むこと」について、次のように書いている。
本を読むということは、大抵の場合には冒険である。それだから又冒険の魅力がある。…
柳田国男『書物を愛する道』青空文庫
柳田国男、折口信夫、宮本常一という、日本の民俗学を牽引してきた知者たちの生の基底に「旅」を見てきた真木悠介は、このようにして、自身の「旅」を、生きることの基底のようなものとしている。
1973年、30代半ばで初めての海外としてインドを旅した真木悠介は、その後も、インド、メキシコ、アメリカ、ヨーロッパなど、海外への旅を続ける。
著書『旅のノートから』(岩波書店、1994年)という美しい書物には、1973年のインドから、1991年のスペインにいたるまで、真木悠介の旅の軌跡を見ることができる(真木悠介は、1978年に、ぼくが今いる、香港に来ている。「香港」をどのように見たかについてはどこにも書かれておらず、直接お伺いしたいと、ぼくは思う)。
真木悠介にとっての「旅」は、彼の著作の内容や文体へ影響してきたと言えるし、また学問のあいだの境界や学問という世界をとびこえてしまう生き方と伴奏してきたようなところがある。
真木悠介(見田宗介)の方法である「比較社会学」の「比較」は、海外のそれぞれの文化や社会のあいだの「比較」という空間を行き来する視点を用意しながら、それはさらに「近代と前近代」などというように、異なる時間を行き来する<比較>をも方法として獲得してゆく。
これらの方法論は、はじめから、そして意図的に、「生き方」の発掘をめざしている。
ぼくは、「生の基底」のような旅に、強くひかれる。
エルヴィス・プレスリーの名曲「Can't Help Falling in Love」。- 「名曲」のなかの<名曲>というもの。
Elvis Presley(エルヴィス・プレスリー、1935ー1977)の名曲「Can’t Help Falling in Love」(1961年)。
Elvis Presley(エルヴィス・プレスリー、1935ー1977)の名曲「Can’t Help Falling in Love」(1961年)。
日本語訳では「好きにならずにはいられない」(英語を学んでいたときに「can’t help …ing」で「…せずにいられない」という構文を習って、この名曲がまるで「例文」のように、ぼくのなかに残っていることはさておき。)。
エルヴィス・プレスリーの代表的なバラードである。
静かに曲の前奏がはじまり、そしてエルヴィス・プレスリーの、太く、深い声がつづいてゆく。
Wise men say
Only fools rush in
But I can’t help falling in love with you
…
Elvis Presley “Can’t Help Falling in Love” (※Apple Music表示のLyricsより)
「Apple Music」で、エルヴィスが歌ういくつかのバージョン(ライブ版含む)、またさまざまなアーティストによって歌われる「Can’t Help Falling in Love」を聞く。
サブスクリプションの音楽配信の楽しみ方のひとつである。
「曲」で検索して、いろいろなバージョンを聞くことができる。
20年前は、東京の街を歩いて、CD・レコード店を見つけては、そこでCDやレコードを探していたけれど、今では、手元のスマートフォンの「検索」で探すことができる。
エルヴィスの名曲「Can’t Help Falling in Love」の元の曲と言われる、18世紀フランスの曲「Plaisir d’Amour(愛の喜び)」(※Wikipedia「Can’t Help Falling in Love」参照)のカバー曲も、Apple Musicで検索すればすぐに見つかる。
歩いて見つける楽しみはないけれど、なにはともあれ、いろいろと聞くことのできる楽しみはある。
エルヴィスの名曲「Can’t Help Falling in Love」の、それらさまざまなバージョンを聞きながら、ふと、ぼくは感じる。
やはり、エルヴィス・プレスリーが歌う「Can’t Help Falling in Love」が、心にしみてくる。
そして、(ここが大切なのだけれど)それはあらゆる側面において、エルヴィスの歌声が、圧倒的に心にせまってくる。
一般的に言って、カバー曲はときに、原曲よりもよく演奏され歌われることもあるし、またそこまでではなくても、原曲に異なった光をあてることもある。
そのような光に照らされた曲の色合いを見つけることができる。
しかし、名曲「Can’t Help Falling in Love」は、やはり、エルヴィス・プレスリーの歌なのだ。
例外としてあるとすれば、ロカビリーバンドStray Catsのリードシンガー&ギタリストであったBrian Setzerが、日本の川崎で行ったアコースティックライブで弾き語りした「Can’t Help Falling in Love」は、エルヴィスの歌声がもつ何かを共有しているように、ぼくには聞こえてくる。
それにしても、やはりエルヴィスの「Can’t Help Falling in Love」に戻ってきてしまうのは、ただ、曲に対する、ぼくの「個人的な記憶のぬくもり」が理由かもしれない。
でも、ぼくは思う。
曲には、多くの人たちにカバーされていくような「名曲」がある。
そのような「名曲」のなかには、ときに、曲を創った人(たち)、演奏する人(たち)、歌う人(たち)、製作者(たち)などによる、幸福な組み合わせによって、「Can’t Help Falling in Love」と言えばやはりエルヴィス・プレスリーというような、そのような<名曲>があるということ。
「Can’t Help Falling in Love」は、1960年代から1970年代にかけて、エルヴィス・プレスリーによるショーの最後の曲として歌われていたという。
ライブアルバムなどの最後の曲に、確かに、アップテンポの「Can’t Help Falling in Love」があったりする。
ライブコンサートでの最後の曲として選ばれていた理由を、ぼくは知らない。
しかし、表面的な理由がどうであれ、エルヴィス・プレスリーにとって、この曲はやはり何か特別な響きと思い出を宿していたのではないかと、ぼくは想像する。
そして、1977年6月、エルヴィスの生涯のライブコンサートの最後のコンサートとなった舞台で、最後に歌った曲が、この名曲「Can’t Help Falling in Love」であった(※Wikipedia「Can’t Help Falling in Love」参照)。
その二ヶ月後、エルヴィスは42歳でこの世を去る。
ぼくはその42歳の年に到達し、エルヴィスが「Can’t Help Falling in Love」の歌に込めていた「何か」に思いをよせる。
民俗学者・宮本常一の「ノート」。- <旅の方法としての学問>(真木悠介)。
勉強ができる人やビジネスで活躍している人の「ノート術」や「メモの取り方」などが書籍化されたり、インタビューなどの記事で取り上げられたりする。
勉強ができる人やビジネスで活躍している人の「ノート術」や「メモの取り方」などが書籍化されたり、インタビューなどの記事で取り上げられたりする。
このようなライフハック的な方法はおもしろいものである。
さらに気になったりするのが、いわば「深い仕事」をしてきた人たちの、その「ノート」である。
例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチのノートは公開されていて興味深いものである。
社会学者の真木悠介は、名前の姓が近いことから、シンポジウムなどで隣席となる民俗学者の宮本常一の「ノート」の話を書いている(真木悠介『旅のノートから』岩波書店)。
ノートには「野帖」と太い字で書かれていて、旅先で出会われたことを書き込んでいるという。
真木悠介は文化人類学の「field note」と同じようなもので、「野帖」はこの英語の日本語訳であったかもしれないと思ったりする。
民俗学を深めていった宮本常一の、<学問の方法としての旅>が、そのなかにつめられている。
真木悠介は、シンポジウムをともにしながら、そこに<旅の方法としての学問>という見方、そしてそのような生き方を提示している。
宮本常一氏の「野帖」には、国際的なシンポジウムの報告もまた旅の記憶と同じ筆致で記入されていた。ベトナムの小さい村々に夜がどのような仕方でやって来るか。等々。宮本氏にとって、シンポジウムの対話も旅であり、読書もまた旅のかたちであったはずだ。
…<旅の方法としての学問>というものもある。学問は旅の一形態である。
真木悠介『旅のノートから』岩波書店, 1994年
「野帖」は、学問(民俗学)のための旅の記録に限らず、そのような狭い世界をつきやぶるようにして、「生きるということの旅」の記録として、宮本常一にとってあった。
思えば、アジアやニュージーランドの「旅」を通じて、ぼくがようやく「生きる」ということ、そして「学ぶ」ということに正面か立ち向かっていったとき、ぼくの「ノート」は、すべてが「同じ筆致」で記載されていた。
香港やベトナムなどの旅先で書いた日記、国際的なシンポジウム(経済学者アマルティア・センなど)を聞きにいったときのメモ、ときおりの日記、読書からの抜粋などが、ひとつのノートにおさめられていた。
学ぶことも、読書も、日々の考えや悩みも、それらが「生きるということの旅のノート」ともいうべきノートにつまっている。
そのようにしてノートに書きつけていたのは昔のことで、最近は、もっぱら、スマートフォンやパソコンにノートしている。
手書きのよさは捨てきれないから、電子ペン(Apple Pencil)をときおり使うなどしている。
生きるうえでの「マテリアル」はなるべくスリム化したいと思いながらそうしているけれど、一方で「生きるということの旅のノート」を、ボールペンで書きつけていきたいという欲望も捨てきれずにいて、ときおり、ボールペンを手に、メモを書いたりしている。
「『じぶん』という秩序がこわれる」旅。- 雑誌「旅行人」編集長・蔵前仁一の「旅」。
バックパッカー向けの雑誌「旅行人」(2011年12月に休刊し、2017年に1号だけ復刊)の編集長を務めてきた蔵前仁一。
バックパッカー向けの雑誌「旅行人」(2011年12月に休刊し、2017年に1号だけ復刊)の編集長を務めてきた蔵前仁一。
海外旅行にまったく興味のなかった蔵前仁一は、フリーのイラストレーターとグラフィック・デザイナーとして社会に出ることになる(蔵前仁一『あの日、僕は旅に出た』幻冬舎)。
その後、東京での生活に疲れ、仕事に疲れ、海外旅行にでも行こうとなったとき、同僚の「インドはおもしろい」という言葉に導かれるようにして、1982年にインドへの旅に出る。
2週間のインドの旅が、蔵前仁一の人生をまったく違うものに変えることになる。
散々な目にあってインドから日本に戻ってきた蔵前の頭のなかは、気がつけばインドのことが立ち上がる。
「インド病」と蔵前仁一の友人が指摘するように、彼は、インドに魂をもっていかれてしまった。
インド病を治すためには「インドに戻ること」という助言に動かされるように、蔵前仁一はインドに戻ることを決め、今度はいつ戻るか決めない長い旅にでる。
仕事を整理し、グラフィック・デザイナーとイラストレーターの仕事を休業し、賃貸マンションを引き払い、旅に出る。
蔵前仁一は最初の目的地を「中国」とし、ビザをとるために、最初に(今ぼくがこの文章を書いている)香港に飛んだ。
1983年9月11日のことであった。
成田空港から飛び立ったエア・インディア103便は、四時間半のフライトで、当時の啓徳空港に着陸し、そこから最終的に1年を超える旅がはじまる。
1985年3月に蔵前仁一は、初めての長い旅を終えて日本に帰国。
次の旅を考える一方で、これまでのような仕事の仕方を変えたく思い、手元にあった「タイの島で描いたインドの絵日記」をもとに出版の道をさぐる。
これが、蔵前仁一の最初の著作『ゴーゴー・インド』(凱風社)となった。
そこから、他の著作を出したり、ミニコミ誌を出したり、最終的に「旅行人」の出版社設立にまでいたる。
しかし、イメージしていたことをだいたい実現し、体力も続かなくなった蔵前仁一は、バックパッカーが減っているといわれるインターネット時代のなかで、そろそろ潮時と見た雑誌「旅行人」の休刊を決め、2011年12月に、雑誌「旅行人」は休刊となった。
そのような蔵前仁一は、「旅の不思議な作用」ということを、自身の旅の経験をふりかえりながら、つぎのように語っている。
あれは自分の中の秩序の崩壊だったと僕は思っている。
インドに行くまで、僕は自分なりの秩序をたもって生きてきた。自分の常識の中で判断し、行動していた。…
それがインドで壊れて、激しい混乱を来したのだ。…
そこで僕は、世界には絶対に正しいことなどないことを知る。…
…
自分もまた変わる。旅に出る前の自分と、旅のあとの自分は同じではない。そして、世界も常に変わり続けている。…だから、旅人は二度と同じ場所へ帰ることはできない。それはまるで長い宇宙飛行から帰ってきた宇宙飛行士と同じであり、浦島太郎のようなものだ。それが、旅の不思議な作用だと思う。
蔵前仁一『あの日、僕は旅に出た』幻冬舎
旅での体験が、じぶんの「世界」に闖入してくる。
蔵前仁一にとっては、それらが、「自分の中の秩序」を壊すことになる。
彼は、その深い経験を、また「旅の不思議な作用」を、じぶんを変えてゆく肯定的な力とすることができた。
「旅で人は変わるか?」と問うことができる。
ぼくは、旅で、人は変わることもできるし、変わらないこともできると、思う。
蔵前仁一にとっては、そしてぼくにとっては、旅で、じぶんが変わってゆく経験をしたということだけだ。
そして、それは、「自分の中の秩序がこわれる経験」である。
その解体と生成のプロセスで、じぶんが<創られるながら創る>という経験である。
雑誌「旅行人」(編集長・蔵前仁一)の宇宙。- 旅の「ディープな世界」への案内。
20年以上も前のこと、ぼくが大学生の頃、大学の夏休みにぼくは旅をした。
20年以上も前のこと、ぼくが大学生の頃、大学の夏休みにぼくは旅をした。
バックパックを背負っての海外一人旅、いわゆる「バックパッカー」の旅であった。
ぼくの心持ちとして、あるいはささやかなスタンスのようなものとして、「バックパッカー」と言い切れないようなところがあるけれど、第三者から見たら、それは「バックパッカー」以外の何者でもなかったと思う。
初めての海外への旅は横浜からフェリー「鑑真号」に乗って向かった中国の上海で、その旅ではその後、西安から北京、北京から天津、天津から神戸と旅をした。
翌年には、この文章を書いているここ香港から入り、広州そしてベトナムという旅であった。
その次の年はワーキングホリデー制度を利用してニュージーランドに住み、帰ってきた年の夏には、タイ、ミャンマー、ラオスと旅をした。
タイのカオサン通りの小さなレストランでは、テレビのニュースが、アジア通貨危機の到来、それからダイアナ妃がこの世を去ったことを伝えていた。
旅をすることの楽しみのひとつは、旅を練り、計画し、想像することにあった。
当時、旅のガイドとしては「地球の歩き方」は一般的な観光旅行のためという認識のもと、バックパッカーにとっては、英語の「Lonely Planet(ロンリー・プラネット)」が世界的に読まれており、また日本語のものとしては雑誌「旅行人」が独特のポジションを獲得していた。
東京の新宿の紀伊国屋書店でも、「旅行人」のコーナーが独特の雰囲気を醸し出していたものだ。
「旅行人」の存在は、旅好きな友人が教えてくれたように記憶している。
雑誌は、インドやアフリカなど、世界のディープな旅を扱い、安宿や出入国の状況(陸路による国境越えなど)の情報、また旅のおもしろい/ありえないような話が紙面に所狭しといっぱいにつまっていた。
雑誌「旅行人」の編集長は蔵前仁一(文書書き、編集者、グラフィック・デザイナー、イラストレーターおよび出版社社長)、著書『ゴーゴー・インド』などで知られていた。
雑誌「旅行人」で情報を得ながら、その不思議な「宇宙」にひたっていると、無性に旅に出たくなるのだった。
「旅行人」のことを、ふと思い出し、グーグルで検索をかける。
すると、なんと「旅行人」のホームページがあるではないか。。
「まだ続いているのか」という驚きと嬉しさで、サイトを探索する。
読んでわかったことは、雑誌「旅行人」は、2011年12月に、165号をもって休刊となったということ。
しかし、2017年9月、休刊から5年9ヶ月後、雑誌「旅行人」は1号だけ(つまり166号だけ)が復刊されている。
その名も、「インド、さらにその奥へ《1号だけ復刊号》」。
なにはともあれ、雑誌「旅行人」のホームページがあり、蔵前仁一編集長はご健在で、今も、いわば「異世界への旅」に出る(あるいはその周辺で集う)人たちがいることに、ぼくの心はおどる。
前身の「遊星通信」から数えて20年以上もやってきた「旅行人」の休刊の経緯については、蔵前仁一は著書『あの日、僕は旅に出た』(幻冬舎)のなかで、蔵前仁一の半生とともに語られている。
…アジア・アフリカを長く旅したときにイメージしたことはだいたい実現した。インターネットも登場し、長い旅をするバックパッカーも減ってきているというし、体力も続かなくなった。そろそろ潮時かな。
僕はそろそろ「旅行人」を休刊しようと思うようになった。
…二年ほど、ぐずぐずと迷い、…そして、ようやく休刊すると決めた。
それはフリーの仕事をいったんやめて、旅に出たときの心境とも似ていた。あのときも、旅から帰国後どうするかなにもわからなかった。だが、それをやめたことで新しい道が開かれたのだ。…また新しいなにかが始まるだろう。
蔵前仁一『あの日、僕は旅に出た』幻冬舎
1956年生まれの蔵前仁一も60歳を超えている。
蔵前仁一の人生を変えた、1982年の「インドへの旅」からも30年以上が過ぎている。
その間に時代も変わり、蔵前仁一の言うように、長い旅をするバックパッカーも減ってきているのかもしれない。
インターネットの世界は世界の距離感を極端に短くし、「旅のあり方」のようなものを、その内実において変えてきているように思われる。
けれども、雑誌「旅行人」が体現していたように、「旅」は、旅の仕方によっては、ディープな世界に入っていくことができる。
それはさしあたり「世界のどこ」ということでもあるけれど、より深いところにおいては、じぶんと世界のつながり方や(旅の)経験の仕方にあるように、ぼくは思う。
「なんでもある」香港で、じぶんの体験の「なんでも」を整理する。- 「オンラインガイドブック」(香港政府観光局)。
「なんでもある香港」を堪能すること。
「なんでもある香港」を堪能すること。
著作『香港でよりよく生きていくための52のこと』における、52のことのうちのひとつとして、ぼくは、そのように書いた。
香港にはなんでもある。
観光はもとより、香港で生活をしていくうえでは、この「なんでもある香港」を楽しむことができる。
香港に2007年の春に来てから、まもなく11年となる。
この11年のなかで「なんでもある香港」での体験をかさねてきたのだけれど、この香港の「なんでも」を整理してみようと、「香港政府観光局」のホームページサイトをひらく。
香港政府観光局のアプリはときどき使っていて、ホームページサイトはたまに参考にするくらいだけれど、以前、そこに電子の「ガイドブック」があったのを覚えていたからだ。
「オンラインガイドブック」(日本語版)として、以下のガイドブックがアップされており、手にいれることができる。
● 香港公式ガイドブック
● オールド・タウン・セントラル街歩きガイド
● 香港ハイキング&サイクリングガイド
● 香港ハイキング&サイクリングガイド(2017年版)
もちろん、英語版も英語のサイトに切り替えれば、手にいれることができる。
香港の多様性をうかびあがらせるような表紙デザインいずれものガイドブックも、「ガイドブック」という名前が示すように、いわゆる「旅のパンフレット」の域を超える内容でつくられている。
これほどの内容が、(このサイトの情報を知っていれば)こうしてサイトから簡単にダウンロードできること、それも日本語のものが揃っていることに、ぼくは個人的な驚きを得る。
なお、「香港公式ガイドブック」は日本語のみで、英語版は「BEST IN HONG KONG: A TRAVELLER’S GUIDE」というものがあり、日本語版をはるかに超える180頁越えの内容となっている。
英語サイトでは、「Hong Kong x Cruise」のガイドブック(兼広告)もある。
これらのページをめくりながら、ぼくは、まだ体験していない/行っていないところなどを確認していく。
それにしても、「オールド・タウン・セントラル街歩きガイド」と「香港ハイキング&サイクリングガイド」は、ぼくが来た11年前にはなかったものである(と思う)。
前者が対象とする、香港島の中環(セントラル)の一帯は、ビジネス街である一方で、指摘されるように「歴史やアート、グルメや文化」がひろがる場所である。
近年は特に、中環(セントラル)の隣りの「上環」にまで至る一帯に、「アート」の空間をつくりだしてきている。
また、後者は、「ハイキング&サイクリング」とある通り、「自然」、また「身体を動かすこと」である。
これら、「アート」「自然」「身体を動かすこと」は、2010年以降くらいからの、香港における「活動」の潮流をそのままあらわしている。
経済発展を主旋律としながら、香港という社会と人びとの磁場のなかにつくられてきた、あるいは押しだされるように立ち上がってきた活動たちの諸相である。
そのような側面を、香港政府観光局のサイトの「ガイドブック」を見ながら、また「なんでもある香港」の「なんでも」を整理しながら、ぼくはかんがえる。
40歳からのトンネルを抜けて。- 「40歳へのメッセージ」(糸井重里)と「試練は、ごほうび」(宮沢りえ)。
年齢・年代による生き方というもの、とくにぼくが置かれている40代の/からの生き方をかんがえてみたりする。
年齢・年代による生き方というもの、とくにぼくが置かれている40代の/からの生き方をかんがえてみたりする。
いろいろな書籍や雑誌が、年代別のテーマをあつかったりしているし、村上春樹も四十歳をひとつの「分水嶺」として作品を完成させていった。
ときに、年代別で見ることは、人びとの共同幻想ではないかと思ったりもする。
あるいは、心理学者エリクソンの有名な「発達段階論」のようなものが思い起こされる。
心理学者といえば、ユングの言う「人生の午後」ということも気になってくる。
しかし、時代は「100歳時代」に突入し、40歳の「立ち位置」も生きることのなかでは変わってきている。
また、ナマコ研究者の本川達雄『人間にとって寿命とはなにか』(角川新書)の帯に書かれた、「42歳を過ぎたら体は保証期限切れ」というコピーに、42歳のぼくはつい反応してしまう。
ともあれ、年齢・年代論は、人間であること(生物・動物としての人間、社会存在としての人間、文化に生きる人間など)の諸相が、いろいろな場面で、いろいろな仕方で、語られているのだと思う。
糸井重里は、「AERA x ほぼ日刊イトイ新聞」の企画(40歳の特集)において、「ぼくの話が40歳の誰かに届けばって」思いながら、言葉を紡いでいる。
AERAに掲載された糸井重里の「40歳へのメッセージ」は、糸井重里のあの文体で、長くはないけれど、そこに込められたもののとてつもなく大きなものを感じさせる言葉たちを、「40歳の誰か」に届けている。
きりとってしまうと、何かがうすまってしまうので全文を読むのがよいけれど、ここでは一部をきりとる。
ぼくにとって40歳は25年前。
暗いトンネルに入ったみたいで
つらかったのを覚えている。
絶対戻りたくない、というくらいにね。
…
40歳を迎えるとき、多くの人は
仕事でも自分の力量を発揮できて、
周囲にもなくてはならないと思われる存在になっていて、
いままでと同じコンパスで描く円の中にいる限りは、
万能感にあふれている。
でも、40歳を超えた途端、
「今までの円の中だけにいる」ことができなくなる。
…
「今までの円の中だけにいる」ことができなくなる。
その「理由」について、ここでは糸井重里はなにも触れていない。
「理由」は人それぞれであるし、何かやむにやまれないものが現象する仕方も、人それぞれであろう。
理由はともあれ、糸井重里は、別のコンパスで描いた円の中に入っていかなければならず、そこでは役に立たない存在だと突きつけられるのだと、自身の「暗いトンネル」の経験の記憶に降りながら、その暗い深い場所から言葉を取り出している。
彼自身もコピーライターとしての万能感がくずれていき、仕事だけでなく、夫婦関係や子育て、親の介護や自分の病気などでも大変な時期にさしかかっていく。
糸井重里は、このようななかでもがきながら、「ゼロになること」を意識するように心がけたという。
仕事においても、あるいは趣味においても。
そうして歩んできて10年後、つまり50歳のときにつながっていく。
それが、「ほぼ日刊イトイ新聞」として結実していくことになる。
現在の日本の40歳は「団塊ジュニア世代」。
団塊の世代である糸井重里は、「「食いっぱぐれることがない時代」を生きていることをもっと利用したほうがいい」(前掲リンク)と、団塊ジュニア世代にアドバイスする。
暗いトンネルをぬけてきた糸井重里は、トンネルをぬけながら「その先に何があるのか」を教えてほしかったという。
そうして、言葉たちを届ける。
言葉たちは、40歳の糸井重里に向けられた言葉であることで、そこに大きな重力を宿している。
その重力に引かれるようにして、ぼくは糸井重里の言葉に耳をすます。
シンプルな言葉たち、しかしそこに語られない言葉たちの総体の声に、耳をかたむける。
ところで、この特集で、糸井重里は、宮沢りえと対談をしている(「試練という栄養ー宮沢りえさんにとっての40歳」)。
男の厄年である40歳にふれる糸井重里に対して、宮沢りえは、最近よく言っていることとして、「試練は、ごほうび」であると語っている(上記の「第2回:試練は、ごほうび」)。
苦難は経験したくないもしれないけれど、苦しみや悲しみを経験して知っている人のほうが、豊かな人であると思うと、宮沢りえは糸井重里に向かって言葉を伝える。
「試練は、ごほうび」。
糸井重里は、この言葉に反応して、ポンと手をたたいたのと同じく、ぼくは、心のなかでポンと手をたたいた。
「試練は、ごほうび」。
とても素敵な表現だし(書き言葉として「試練は」の後に「、」が入るリズムもいい)、そう言える生き方は魅力的だと、ぼくは思う。
「考える」ことの本質について。- 論理思考、言葉(ロゴス)、分けること。
「考える」とは、その本質において「(物事を)分けること」というふうに、ぼくはかんがえる。
「考える」とは、その本質において「(物事を)分けること」というふうに、ぼくはかんがえる。
「分けること」とは、物事を論理的に分けていくことである。
だから、この見方においては、「論理的に考える」という言い方は便宜的なものであって、本質的には、「考える」ことのなかにすでに「論理」が含まれている。
津田久資は著作『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのかー論理思考のシンプルな本質』(ダイヤモンド社)で、「考える」ということを、ビジネスにおいて「競合に勝つ」という視点・焦点において、「学ぶ」ことから切り離しながら、次のように定義している。
● 学ぶ=既存のフレームワークに当てはめて答えを導く
● 考える=自分でつくったフレームワークから答えを導く
「思考力で競合に勝つ」という視点をつきつめてゆくなかで、「勝つ」ということを、「思考の成果、つまり発想(アイデア)において相手よりも優位に立つこと」とし、そこから発想において「負ける」ということのパターンとして、論理的に3つ挙げている(前掲書)。
<発想における敗北の3つのパターン>
① 自分も発想していたが、競合のほうが実行が早かった
② 自分も発想し得たが、競合のほうが発想が早かった
③ 自分にはまず発想し得ないくらい、競合の発想が優れていた
これらを言い換えて、津田は次のように簡素化する。
① 実行面の敗北
② 惜敗(「しまった」)
③ 完敗(「まいった」)
そのうえで、90%以上の敗北は②の「しまった」にあるとし(人は同レベルの「戦場」に集まる傾向を背景としている)、その処方箋として「論理思考」を立てる。
「論理思考力」をつきつめてゆくなかで、津田久資は「考える」こと、またそれを構成する「言葉」の本質にきりこんで、次のように本質を取り出している。
● 「考える」とは「書く」である
● 「言葉」とは「境界線」である
津田が指摘しているとおり、「論理(logic)」の語源は、「ロゴス(logos)」=言葉であり、言葉はその本質にして「論理」的なのである。
そのことを、津田は、「言葉」とは「境界線」であると表現している。
言葉は機能(「境界線」)として、対象を切り分けるのである。
切り分ける機能として、それは「考える」ということを本質として内包していることになると、ぼくはかんがえる。
「考える」とは「書く」であると、津田久資が述べていることに興味をおぼえ、ぼくは立ち止まる。
人が考えているかどうかを決めるのは、その人が書いているかどうかである。
アイデアを引き出すとは、アイデアを書き出すことにほかならない。少なくとも大多数の人にとってはそうである。…
本当に何かを考えたときには、そのプロセスや最終的なアウトプットについて、何かしら必ず書いているはずである。逆に言うと、それがない限り「考えていた」とは言えないのである。
津田久資『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのかー論理思考のシンプルな本質』(ダイヤモンド社)
例として、ダイエーの故・中内功がとんでもないメモ魔であったこと、エジソンの生涯3500冊のノートなどが挙げられ、逆に「少数派の例外」として「小説の最後の1行が決まるまで、ペンを執らない」作家の三島由紀夫が取り上げられている。
「書く」ことは、視覚化することでもある。
人間の文明が「視覚」を発展の原動力としながら、「視覚」文明をつくりあげてきたということを、ぼくは重ね合わせながら、かんがえてみる。
文明の発展の構造と駆動はぼくのなかでまだ漠として繋ぎあわさっていないけれど、「書く」ことで世界がひらかれてきたことは、「書く」ことの力を思えば、経験上わかるように思う。
埴谷雄高の語る「夢と現実」。- これまでの言葉や思考を<括弧でくくる>とき。
「学ぶ」ということの深い意味を体験としてわかりはじめたことのきっかけのひとつとして、経済学者であった内田義彦の著作があった。
「学ぶ」ということの深い意味を体験としてわかりはじめたことのきっかけのひとつとして、経済学者であった内田義彦の著作があった。
かすかな記憶では、大学での「国際経済学」講義の課題図書のひとつであったと思う。
社会科学を学ぶことで物事を視るための<メガネ>を変えていくというようなことを、ぼくは内田義彦から学び、その「教え」に触発されながら、ようやく<学ぶこと>を理解しはじめ、やがて、<メガネ>を変えることで、世の中が違って見えるようになることに、驚きと興奮、そして(ぼくにとっての)救いのようなものを感じた。
それまで20年間生きてきたなかで、ぼくのなかに蓄積されていた「言葉」や「考え」が、確固たるものではなく、<不確かなもの>として立ち上がってくるようになった。
ぼくが小さい頃から「違和感」を感じ続けてきたことのひとつとして、「現実(リアリティ)」、そして「夢」ということがある。
世間も大人たちも「現実を見なさい」と語り、見えないプレッシャーを投げかける。
そこで語られる「現実」ということに、ぼくは違和感を感じ続けてきたのである。
ようやく<学ぶこと>をしはじめたぼくは、いろいろな人たちの著作のなかで、多様で深い「言葉」と「思考」に出会い、これまで蓄積されていた言葉や考えを解体していくようになった。
これまでの言葉を<括弧でくくる>ことで見直し始めた頃、作家の辺見庸の著作群に出会い、辺見庸が影響を受けてきた作家などにも手をひろげていき、そのなかに作家の埴谷雄高(はにやゆたか)がいた。
「夢と現実」について次のように語る埴谷雄高に、ぼくは出会う。
…夢について、初めは誰でもそうでしょうけれども…現実の人間の生活から遠く離れた架空な、きれぎれな低次な意味しかもっていないものだと思っていた。人生の小さな装飾というぐらいにみていたのです。ところが、成長するにつれて、考え方が逆転してきて、どうも僕たちの現実自体が夢を見る見方にこそ支えられているという気がしてきた。夢を見ているその夢の枠から「僕」がでれないとまったく同じ仕方で、まったく同じ制約法でどうも僕たちは「僕」と「もの」のなかにいる。こう思えてくるとどうも夢のほうが僕たちの生を支えている素朴な原型であって、われわれのもっているこののっぴきならぬ思考法はむしろ夢に規定されている。…
埴谷雄高『凝視と密着』未来社、1969年
ここでは「夢」というものが、きれぎれなものから生の素朴な原型というものにいたるまで重層的に語られている。
「人生の小さな装飾」としての夢が、成長の過程において<括弧>くくられ、現実を包摂するようなものとして生きられ、感覚され、見晴るかされている。
それは、ぼくの生きることの経験に根ざした直感に、直接に接続される言葉の表現を与えてくれるようなものであった。
そのような言葉との出会いが、人の生の道ゆきを照らし出してくれる光源となってくれる。
「働き方」における働く人たちの内面を照らす物語。- 朱野帰子著『わたし、定時で帰ります。』を読んで。
朱野帰子の小説『わたし、定時で帰ります。』(新潮社、2018年)(正式な発売の前の「期間限定無料版」)を読む。
朱野帰子の小説『わたし、定時で帰ります。』(新潮社、2018年)(正式な発売の前の「期間限定無料版」)を読む。
本のタイトルであり、作品中にいくども語られる「わたし、定時で帰ります」ということは、デジタルマーケティング会社に勤務する東山結衣のモットーである。
18時の終業時間には必ず仕事を終えることを、三十二歳になる東山結衣は執拗なまでに実践している。
そこに、破格の受注額で仕事を引き受けようとする福永清次という新しいマネジャーが配属され、「ウェブサイトの大幅リニューアル」というプロジェクトが動き出すなかで、いろいろにドラマが展開していく作品だ。
「わたし、定時で帰ります。」という言葉に、人はそれぞれに、いろいろな記憶や感情、そして心のなかで展開する「物語」をいだくであろう。
日本は「働き方改革」のなかにあり、海外の日系企業も異文化との接点のなかで「働き方(またマネジメント)」にいろいろな問題や課題をかかえている。
この本の物語は、人それぞれに違う仕方で響くであろう「働き方」を主旋律にして展開されていく。
人それぞれに多様な捉えられ方をする「多様性」を反映するように、登場人物も多様な背景をもつ個人で設定されている。
このような物語を読むうちにぼくが感じる「違和感」は、仕事の意義や目的などが脇に追いやられていることであるが、そのことが逆に、実際に「働き方」という組織内部のマネジメントに終始しがちな仕事の日常をうつしだしているようにも見てとれる。
その意味において、(良し悪しはさておき)ある程度の働く人たちの「ありがちな目」を通じた風景を意図的に描きだした作品とも言える。
この作品はそのような日常を描きながら、職場の人たちが相互に「誤解」をしている心象風景も描いていることで、人と組織の問題の一端をつかんでいる。
そして「誤解」は、それぞれの人のいわば「偏った見方・バイアス」に絡めとられた形でつくられ、そして言葉や行動に現れる。
東山結衣は、「わたし、定時で帰ります」という<位置>にじぶんを置いたことで、そしてある意味、この「ふっきれた立ち位置」を肯定的に転換させてゆくことで、この誤解に充ちた職場空間に光明を与えてゆくことになる。
読者は「東山結衣」であるかもしれないし「東山結衣」ではないかもしれないけれど、登場人物のある程度の「タイバーシティ」のなかで、いずれかの登場人物にじぶんの心情を重ねながら、あるいは上司や部下を登場人物に重ね合わせながら、物語を読み、何かを見つけ、何かを感じることができるように思う。
登場人物のそれぞれの内面に光をあてながら、そしてそれらいずれもの感情を引き受けようとしながら、ぼくはこの作品を一気に読み終えた。
この物語のなかで、「定時で帰るなんてなんぞや/ありえない」という極と、「とにかく定時で帰ります」という極との<橋渡し>が、どのようになされ、そしてどのように結実していくかを追いながら。
村上春樹の「遠い太鼓」に呼ばれた旅。- 「空間(異国)」編:ヨーロッパでの3年。
小説家の村上春樹の著作『遠い太鼓』(講談社文庫)。1986年から1989年にかけて、村上春樹がヨーロッパに住んだときのエッセイ(記録)である。
小説家の村上春樹の著作『遠い太鼓』(講談社文庫)。
1986年から1989年にかけて、村上春樹がヨーロッパに住んだときのエッセイ(記録)である。
「四十歳」に特別な予感をいだきながら、「遠い太鼓」に呼ばれるようにして、村上春樹(夫妻)は、三十七歳でヨーロッパに旅立った。
「四十歳」への予感ということと共に、ぼくの関心をよんだのは、この長い旅が、村上春樹にとって「初めての海外暮らし」であったことである。
村上春樹は、夫妻が置かれる「立場」がとても「中途半端」であったことを書いている。
「観光的旅行者」でもなく、かといって「恒久的生活者」でもない。
さらに、会社や団体などにも属しておらず、あえて言えば「常駐的旅行者」であったという。
本拠地をローマとしながらも、気に入った場所があれば「台所のついたアパートメント」を借りて何ヶ月か滞在し、それからまた次の場所に移っていく。
その生活の様子や出来事が、まるでそれらが物語のように、語られている。
物語のように描かれる世界、筆致と文体とリズム、視点や視角はとても魅力的である。
村上春樹は、そのような生活を「孤立した異国の生活」というように語っている。
その(自ら望んだ)孤立のなかで、村上春樹はただただ小説を書きつづけ、この3年間に、長編小説としては『ノルウェイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』を書き上げることになる。
『ノルウェイの森』はギリシャで書き始められ、シシリーで書き継がれ、ローマで完成したようだ。
『ダンス・ダンス・ダンス』は、ローマで大半が書かれ、ロンドンで完成されたという。
このようにして、これらの長編小説には「異国の影」がしみついているのだと、村上春樹自身が感じるものとして、できあがったのだ。
村上春樹は、これらの作品は、仮に日本に住み続けていたとしても、時間はかかってもいずれは同じようなものが書かれたであろうと、振り返っている。
…僕にとって『ノルウィイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』は、結果的には書かれるべくして書かれた小説である。でももし日本で書かれていたとしたら、このふたつの作品は今あるものとはかなり違った色彩を帯びていたのではないかという気がする。はっきり言えば、僕はこれほど垂直的に深く「入って」いかなかっただろう。良くも悪くも。
村上春樹『遠い太鼓』講談社文庫
ヨーロッパでの孤立した生活のなかで、誰にも邪魔されずに、ひたすら小説を書く。
「なんだかまるで深い井戸の底に机を置いて小説を書いている」ようであったと、小説を書いている自分を、村上春樹は客観視する。
深い井戸の底に、垂直に深く「入って」いくことのできる<環境>を、ヨーロッパでの生活が準備し、そこで村上春樹の作品が生成する。
…結局のところ、僕はそういう世界に入りたがっていたのだと思う。異質な文化に取り囲まれ、孤立した生活の中で、掘れるところまで自分の足元を掘ってみたかった(あるいは入っていけるところまでどんどん入っていきたかった)のだろう。たしかにそういう渇望はあった。…
村上春樹『遠い太鼓』講談社文庫
さらに、後年になって、村上春樹は、ヨーロッパという異質な文化の環境で、「三年かけてこの本を書いたことによってなんとなく体得したもの」として、「複合的な目」を挙げている。
外国に行くとたしかに「世界は広いんだ」という思いをあらたにします。でもそれと同時に「文京区だって(あるいは焼津市だって、旭川市だって)広いんだ」という視点もちゃんとあるわけです。僕はこのどちらも視点としては正しいと思います。そしてこのようなミクロとマクロの視点が一人の人間の中に同時に存在してこそ、より正確でより豊かな世界観を抱くことが可能になるはずだと思うのです。
村上春樹「文庫本のためのあとがき」『遠い太鼓』講談社文庫
この文章を、村上春樹は、ヨーロッパの次に住むことになった海外、アメリカで書いている。
ときおり、もし村上春樹が海外に住まず、日本で小説を書き続けていたら、彼の小説がどのようになっていただろうかと、ぼくは勝手にかんがえてしまう。
村上春樹が言うように、日本にいても書かれたのかもしれないけれど、『ノルウェイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』以後の長編小説の深い世界を思うとき、ぼくはやはりかんがえてしまうのだ。
そしてときおり、ぼくはじぶんのこともかんがえてしまう。
もし、ぼくが、海外に暮らさずに、日本で暮らし続けていたとしたら、と。
無意味な問いと想像なのかもしれないけれど、「四十歳の分水嶺」に村上春樹が予感していたように、「それは何かを取り、何かをあとに置いていくこと」という「精神的な組み替え」が、生きることの<空間の分水嶺>において生じたであろうところに、ぼくの思考と想像をつれていくようにも、思われるのだ。
村上春樹の「遠い太鼓」に呼ばれた旅。- 「時間(年齢)」編:四十歳という分水嶺。
村上春樹の「エッセイ」は、「小説」に負けず劣らず、魅力的な文体とリズムで書かれている。
村上春樹の「エッセイ」は、「小説」に負けず劣らず、魅力的な文体とリズムで書かれている。
人によっては、小説よりもエッセイに惹かれる人たちもいる。
数々のエッセイのなかで好きな作品のひとつに、『遠い太鼓』(講談社文庫)というエッセイ集がある。
村上春樹が、1986年から3年間にわたりヨーロッパに住んでいたときの「エッセイ」である。
どこからか聞こえる「遠い太鼓」の音色に導かれるように旅立ち、ヨーロッパに住んでいたときの語りである。
文庫版で500頁を超えるこの作品の、ぼくにとっての「魅力性」の源泉は、村上春樹という人間が「生成」していくところに書かれた作品であったというところにあるように思う。
それは、とりわけ、二つのきっかけにおいてである。
- 村上春樹の「四十歳」
- 村上春樹の「初めての海外暮らし」
一つ目は、生きるということの「時間」という契機であり、二つ目は、生きるということの「空間」という契機である。
人は、(ひとまず/さしあたり)「時間と空間」のなかを生きている。
村上春樹にとって、この長い旅の契機のひとつは「四十歳」ということがあったという。
三十七歳で、村上春樹はこのヨーロッパへの長い旅にでる。
四十歳というのは、我々の人生にとってかなり重要な意味を持つ節目なのではなかろうかと、僕は昔から(といっても三十を過ぎてからだけれど)ずっと考えていた。とくに何か実際的な根拠があってそう思ったわけではない。あるいはまた四十を迎えるということが、具体的にどういうことなのか、前もって予測がついていたわけでもない。でも僕はこう思っていた。四十歳というのはひとつの大きな転換点であって、それは何かを取り、何かをあとに置いていくことなのだ、と。そして、その精神的な組み替えが終わってしまったあとでは、好むと好まざるとにかかわらず、もうあともどりはできない。…
村上春樹『遠い太鼓』講談社文庫
そのような「予感」が、三十半ばの村上春樹のなかでふくらんでいき、「精神的な組み替え」が行われてしまう前に、「あるひとつの時期に達成されるべき何か」をしておきたかったこと、村上春樹は書いている。
なお、「四十歳」ということは、三十歳で『風の歌を聴け』によって群像新人文学賞を受賞した村上春樹が、「受賞の言葉」でも語っていた時間感覚でもあった。
…フィッツジェラルドの「他人と違う何かを語りたければ、他人と違った言葉で語れ」という文句だけが僕の頼りだったけれど、そんなことが簡単に出来るわけはない。四十歳になれば少しはましなものが書けるさ、と思い続けながら書いた。今でもそう思っている。…
村上春樹「四十歳になれば」『雑文集』新潮社
『遠い太鼓』を初めて読んだのは、ぼくが三十代の頃(正確に三十代のいつかは覚えていない)であった。
ぼくの根拠のない「予感」も、四十歳というものをひとつの分水嶺のように捉えていたから、そこに親和性のようなものを感じたことを覚えている。
ぼくも四十歳を超えてみて、「精神的な組み替え」が行われたかどうか、そこで何かをとり何かをあとに置いてきたのかをかんがえてみる。
他方で、「四十歳」という分水嶺の「妥当性」のようなこともかんがえてしまう。
人間の身体を生物学的にみたときの変化ということがある一方で、「世代」(三十代、四十代、五十代…)というものが現代世界における「共同幻想」ではないかという思いももたげてくる。
さらには、「100歳時代」の到来のなかで、これまでの四十歳とこれからの四十歳は、生きるプロセスの意味合いを大きく変えてきている。
そのようないろいろな思いとかんがえが交錯するなかで、村上春樹の『遠い太鼓』の世界に、ふたたびふれている。
村上春樹は、このヨーロッパでの3年間で、小説としては『ノルウェイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』を書いた。
村上春樹の「予感」は、『ノルウェイの森』として結実していくことになったわけだ。
ぼくは、四十歳を超えて、やはり、大きな一歩、これまでと異なる一歩を踏み出すことにした。
「四十歳」という分水嶺の妥当性はともかくも、その分水嶺は「物語」として生きてきているように、ぼくは思う。
その物語を描ききれるかどうか、その物語を生ききることができるかどうか…。
村上春樹の『遠い太鼓』のエッセイは、ヨーロッパに住むことの日常の細部それぞれが物語とリズムに充ちている。
そのように日常を生きることのうちに、村上春樹の文章の魅力は生成されている。
「風のことを考えよう」(村上春樹)。- 「風」に吹かれ、惹かれ、かんがえてみる。
村上春樹のデビューから2010年の未発表の文章が収められた『雑文集』(新潮社、2011年)を読み返していたら、「風のことを考えよう」という、以前読んだときにはあまり気に留めなかった短い文章に、目が留まった。
村上春樹のデビューから2010年の未発表の文章が収められた『雑文集』(新潮社、2011年)を読み返していたら、「風のことを考えよう」という、以前読んだときにはあまり気に留めなかった短い文章に、目が留まった。
村上春樹のデビュー作品である『風の歌を聴け』の「風」のイメージに共鳴したということでは特にない(「風」という視点で村上春樹の作品を読み解いていくことはきっとおもしろいだろうけれど)。
「現代人はなぜ風を求めているのか」(見田宗介『現代日本の感覚と思想』講談社学術文庫)という問題意識と、なぜ「ぼくは」風に惹かれているのか、ということの問題意識の重なりのなかで、村上春樹の感性がどのように「風」をとらえているのかが、気になったのだ。
「風のことを考えよう」というフレーズは、トルーマン・カポーティの短編小説「最後の扉を閉めろ」という作品にあるという。
「そして彼は枕に頭を押しつけ、両手で耳を覆い、こう思った。何でもないことだけを考えよう。風のことを考えよう、と」
最後の“think of nothing things, think of wind”という文章が、僕はとても好きだった。…
そんなわけで、何かつらいことや悲しいことがあるたびに、僕はいつもその一節を自動的に思い起こすことになった。…そして目を閉じ、心を閉ざし、風のことだけを考えた。いろんな場所を吹く風を。いろんな温度の、いろんな匂いの風を。それはたしかに、役立ったと思う。
村上春樹「物語の善きサイクル」『雑文集』新潮社、2011年
「運び去っていくもの」としての風、あるいは「運んできてくれるもの」としての風があるとすれば、ここでは、つらいことや悲しいことを運び去ってくれる<風>が、想像力のなかでよびおこされているように見える。
しかし、村上春樹の「風」は、トルーマン・カポーティの「風」ー何でもないことーとは、微妙にズレているようにも見える。
村上春樹の「風」は、何でもないことに連想される風ではなく、「いろんな風」であり、いわば豊饒な風である。
自然の豊饒さに彩られた風。
「太古の始めから、風は吹いていた」と野口晴哉が感じるときの風と重なる風のようにも、ぼくには見える。
ぼくにとって、世界のいろいろなところで、「風」に吹かれた記憶がながれている。
ニュージーランドに住んでいたときは、北島でも南島でも、ぼくは海岸線や道や山を「歩く旅」のなかで、風に吹かれていた。
西アフリカのシエラレオネにおける「緊急支援」においては、ぼくが所属した団体名に「風」があったように、風のように支援を展開していた。
東ティモールの山間地で、「気流」にさらされながら、コーヒー農園をみわたしていた。
ここ香港では、海から吹いてくる風にさらされて、生きている。
「風」になぜぼくは惹かれるのだろうか、しいては、現代人はなぜ「風」を求めるのか。
村上春樹の(世界における)経験のなかでは、ギリシャの小さな島に滞在していたときの風が、風の記憶として色濃くむすびついている(ちなみに、ギリシャに滞在していたときの話は、村上春樹のエッセイ集『遠い太鼓』講談社文庫、に出てくる)。
日々、風とともに生きる場所であったようだ。
…風がひとつのたましいのようなものを持つ場所だったのかもしれない。ほんとうに、風のほかにはほとんど何もないような、静かな小さな島だったから。それとも、そこにいるあいだ、僕はたまたま風のことを深く考える時期に入っていたのかもしれない。
風について考えるというのは、誰にでもできるわけではないし、いつでもどこでもできるわけではない。人がほんとうに風について考えられるのは、人生の中のほんの一時期のことなのだ。そういう気がする。
村上春樹「物語の善きサイクル」『雑文集』新潮社、2011年
村上春樹は、人には「風のことを深く考える時期」があると書き、また、ほんとうに風についてかんがえられるのは、「人生のほんの一時期のこと」だと書いている。
1986年から3年間、村上春樹は日本を離れ、ヨーロッパに住む。
この長い旅を駆り立てた理由のひとつは、40歳になろうとしていたことであったという(前掲『遠い太鼓』講談社文庫)。
そして、ギリシャで、村上春樹は『ノルウェイの森』を書きはじめている。
村上春樹が深くかんがえていた「風」をぼくはかんがえ、記憶のなかに吹いている「風」と重ねあわせてみる。
たしかに、人が本当に風についてかんがえられるのは人生のほんの一時期なのかもしれないという思いが、思考の海を、風のようによこぎっていく。
「物語の善きサイクル」(村上春樹)。- 希望や喜びをもつ語り手であること。
「Life as Stories」(物語としての生)というテーマでいろいろとかんがえ、他の人たちがどんなことをかんがえ書いている(いた)のかを探り、発せられる言葉にこころを沁みわたらせる。
「Life as Stories」(物語としての生)というテーマでいろいろとかんがえ、他の人たちがどんなことをかんがえ書いている(いた)のかを探り、発せられる言葉にこころを沁みわたらせる。
そしてそこに「可能性」をみいだす。
頭でかんがえてきただけではなく、物語などという言葉をふっとばしてしまうような「現実」のただなかでかんがえ、それでもやはり「物語の力」を、その可能性とその方法をぼくはひたすら追い求める。
作品が出たらすぐに買って読む作家(たくさんいるわけではないけれど)のひとりに、小説家の村上春樹がいる。
生きることと物語を直接に語った箇所は今のぼくの記憶にはないけれど(そのような視点で村上春樹を読んでこなかったけれど)、村上春樹は「物語の力」を、「小説」ということに託して、いろいろなところで語っている。
物語の「善きサイクル」とよびながら、村上春樹は次のように書いている。
作家が物語を創り出し、その物語がフィードバックして、作家により深いコミットメントを要求する。そのようなプロセスを通過することによって作家は成長し、固有の物語をより深め、発展させていく可能性を手にする。…想像力と勤勉さという昔ながらの燃料さえ切らさなければ、この歴史的な内燃機関は忠実にそのサイクルを維持し、我々の車両は前方に向かって滑らかに…進行し続けるのではあるまいか。僕はそのような物語の「善きサイクル」の機能を信じて、小説を書き続けている。
村上春樹「物語の善きサイクル」『雑文集』新潮社、2011年
村上春樹の熱心な読者であればすぐに思い出すであろう「モンゴルのホテルでの奇妙な出来事」が、ここでは具体的な例としてとりあげられている。
「物語を創るー物語が(創り手に)フィードバックするー深いコミットメントを要求する」という基本プロセスのうちに成長があり、可能性や希望がうまれてゆく。
このように語られる「物語の善きサイクル」は、狭義の「物語」だけでなく、生きることの<物語>も、サイクルの型は同じであるように、ぼくはかんがえる。
そのサイクルの型が「善きサイクル」となるか否かは、もうひとつ別のことである。
「想像力と勤勉さという昔ながらの燃料」、とりわけ「想像力」ということの燃料さえ切らさなければ、生きることのサイクルは(じぶんにとって)「善きサイクル」へと進行してゆくものだと、思う。
その意味において、人はだれもが「小説家」であり、生きることの<物語>をつくっている。
村上春樹はこの文章(「物語の善きサイクル」)の最後に、じぶんは「楽天的に過ぎるかもしれない」と、一歩立ちどまって、その歩みの意味をたしかめている。
…しかしもしそのような希望がなかったなら、小説家であることの意味や喜びはいったいどこにあるだろう?そして希望や喜びを持たない語り手が、我々を囲む厳しい寒さや飢えに対して、恐怖や絶望に対して、たき火の前でどうやって説得力を持ちうるだろう?
村上春樹「物語の善きサイクル」『雑文集』新潮社、2011年
このことも、そのまま、生きることそのものに向けられる。
個人の生においても、そして、家族、チームや組織、コミュニティなどにおいても、この文章のメッセージはつらぬいていく力をもっている。
そして、どんな人たちも、その心の奥底には、希望をはぐくむ歓びの経験の記憶をもって生きている。
「読まな、損やでぇ」の本から本へ。- 河合隼雄『こころの読書教室』の語りで、心の深みに降りる。
20歳になるまで、ぼくは本という本をほとんどといってよいほど読まなかった。
20歳になるまで、ぼくは本という本をほとんどといってよいほど読まなかった。
経験とじぶんでかんがえることが大切と思っていたのだと思うけれど、今思うと、それこそ浅いかんがえであった。
経験とじぶんでかんがえることに、「本」(他者の書くもの、また語り)が加わることで、経験とかんがえること自体にひろがりと深みがでるのだ。
そんな「本の読み方」と本から学ぶ(本と共に生きる)歓びを、ぼくはいろいろな人たちに学んだ。
そのうちの一人、心理学者・心理療法家の河合隼雄は、『こころの読書教室』(新潮文庫、原題『心の扉を開く』)のようなものとして、次のように書いている。
私はできるだけ多くの人に本を読んでもらいたいと思っている。それも、知識のつまみ食いのようではなく、一冊の本を端から端まで読むと、単に何かを「知る」ということ以上の体験ができると思っている。一人の人に正面から接したような感じを受けるのだ。
「情報が大切と言いながら、現代の情報は『情』抜きだから困る」と言ったのは、五木寛之さんである。私もこの考えに賛成だ。人間が「生きている」ということは大変なことである。いろいろな感情がはたらく、そして実のところ、その感情の底では本人も気づいていない、途方もない心の動きがあるのだ。そのような心の表面にある知識のみを「情報」として捉えていたのでは、ほんとうに生きることにはつながって来ない。
河合隼雄『こころの読書教室』新潮文庫
インターネットの発展は、日々、はるかに多くの「情報」の創出をうながしている。
情報空間は「知識のつまみ食い」の機会を次から次へと、つくっている。
しかし、「知識のつまみ食い」をくりかえしてもくりかえしても、なにかが抜けてしまっているような感覚におちいる。
河合隼雄が語るように、心の表面の知識を情報として捉えても、「ほんとうに生きること」にはつながっていかないと、ぼくも思う。
河合隼雄の読書のひろげ方(アンテナの張り方)は、「尊敬する人、好きな人の推薦」だという。
ぼくもまったく同じ「アンテナの張り方」をしている。
だから、『こころの読書教室』で河合隼雄がすすめる本を読む。
4回の講義録として編集されたこの本では、それぞれの講義ごとに、「まず読んでほしい本」五冊と「もっと読んでみたい人のために」五冊が紹介されている。
河合隼雄の関西弁では「読まな、損やでぇ」の、合計20冊の本たちである。
深層心理学の専門書はなるべく避けられ、小説や児童文学・絵本などがとりあげられている。
講義は、「まず読んでほしい本」で紹介された本を読み解きながらすすめられてゆく。
「話の筋」の、いわゆるネタバレがあるけれども、それだけで「わかった」という表面的な世界ではなく、深い世界へと降りてゆくような本である(「まず読んでほしい本」を読んでからこの本を読むのがよいのだろうけれど、ぼくは先に河合隼雄の講義に耳をすましてしまった)。
「私と“それ”」「心の深み」「内なる異性」「心ーおのれを超えるもの」という講義に、ぐいっとひきこまれてゆくのをぼくは感じ、そしてこの「一冊」を読むことで、やはり河合隼雄という人に正面から接したような感覚がわきあがるのだ。
それはこころの深いところに降りてゆくような対話のようなものである。
河合隼雄はこの本を講義録をもとにしてつくられている理由として、「語りかける言葉の方が、人間の心の扉を開いて下降してゆくのにふさわしいと思われる」(前掲書)と語る。
はっと、ぼくはそこで、河合隼雄の語りにひきこまれていった理由のひとつが紐解かれたようにも思った。