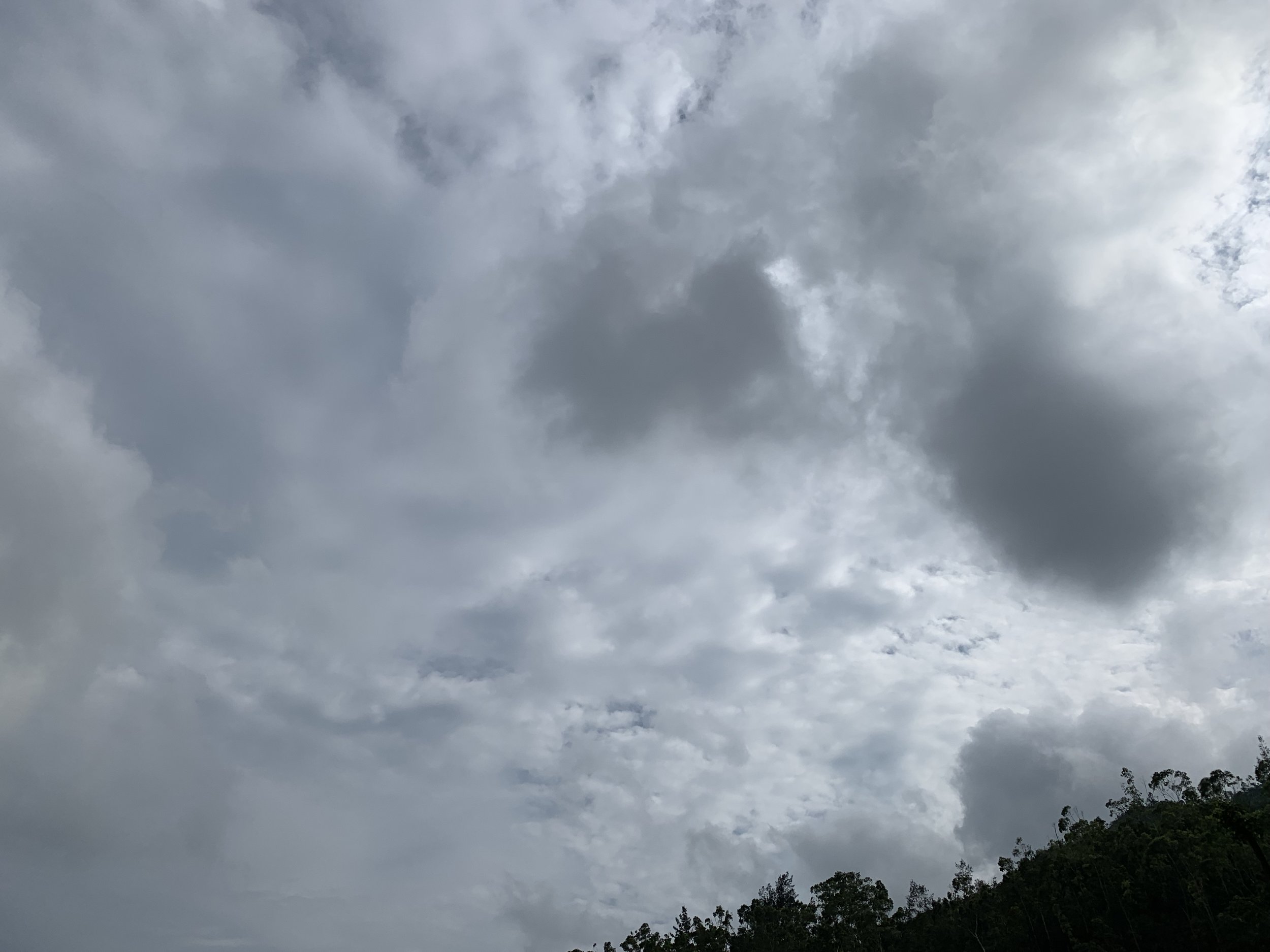「〜しておけばよかった」と思うときに。- <現在>を照らすことば。
ひとはときに、「~しておけばよかった」と思うことがある。英語をもっと学んでおけばよかった、本をもっと読んでおけばよかった、勉強をもっとしておけばよかった、投資していればよかった、等々。
ひとはときに、「~しておけばよかった」と思うことがある。英語をもっと学んでおけばよかった、本をもっと読んでおけばよかった、勉強をもっとしておけばよかった、投資していればよかった、等々。それらをせずに失われた時間をみつめながら、後悔の念を抱いたりする。「もし~しておけば」今のじぶんは今とは全然ちがっていただろうにと思いながら。
その「もし」は、抽象化された時間の長さと抽象化された行動だけをとりだしてみれば、そのとおりかもしれない。けれども、具体的な現実においては「もし」のあとにやってくるであろう結果・成果はだれもわからないから、その正しさを証明することはできない。
でも、現代人は、この「抽象化された時間」を自明のことであるように生き、「~しておけばよかった」というように「時間」を「他の時間」と取りかえ可能のように考える。
かせいだり、たくわえたり、節約したりすることの可能な「時間」、ーそこではたとえば、夜明けの時と午後の時、恋愛の時と別れの時、わたしの時とあのひとの時、そのような時それぞれの固有性、絶対性は捨象され、たとえば夜明けの30分を「浪費する」ことをやめたり恋愛の三時間を「節約」したりすることの可能な対象へと還元される。時間が他の時間のうちにたがいに等価をもちうるという実践的還元のうえに、一般化された商品交換のシステムとしての市民社会の総体は存立している。
真木悠介『時間の比較社会学』(岩波書店、1981年)
真木悠介(社会学者)は、このように書いている。
「他の時間」とたがいに等価をみる思考によって、つまり「昔のあの現実の時間」を「他の(有効な)時間」に取ってかえることのできる思考によって、「~しておけばよかった」というように思い、「浪費する」ことなどに対して後悔の念をひとは抱く。
「時間」(または/あるいは「貨幣」)を見る特定の仕方のうえに、このような思考や感覚があらわれる。もちろん、そうでなくても、純粋に、過去の言動に対して後悔することは存在するだろうけれど、はるか昔の人たちは、あの「浪費した」時間に英語をもっと学んでおけばよかった、というようには思わなかっただろう。
「~しておけばよかった」という思考と感覚が必ずしも普遍のものではないことをふまえたうえで、「~しておけばよかった」と思うときは、「~」を<はじめるとき>である。ぼくはそう思う。
後悔するときではなく、今こそ<はじめるとき>である。むしろ、機が熟したのだと見ることができる。はじめるのが「遅いこと」はあっても、「遅すぎること」はない。
じぶんが生きる「物語」のなかでスポットライトがあたる「~」である。それは、学ぶことであるかもしれない、健康にかんすることであるかもしれない、人間関係のことであるかもしれない。あるいは、生きかたを変えてゆくときであるかもしれない。
「~しておけばよかった」は、過去に向かうことばではなく、現在を照らすことば、そして未来に向けられたことばである。
少しの、「感覚」のメモ。- 「揺れる」香港で生活しながら。
ここ香港での、「逃亡犯罪人条例等改正案」に反対する抗議活動。その背景と刻一刻と動いてゆく情況はさまざまなメディアでとりあげられているので、それらに目を通してほしい。
ここ香港での、「逃亡犯罪人条例等改正案」に反対する抗議活動。その背景と刻一刻と動いてゆく情況はさまざまなメディアでとりあげられているので、それらに目を通してほしい。
メディアで報道されている情況とはべつに、もちろん、人びとの生活はつづいている。あたりまえといえばあたりまえのことではある。ぼくも、生活をつづけている。そして、メディアを通して報道されている情況と、そんなふうにつづく生活のはざまで、情況を注視する。
生活はいつもどおりつづいているように見えるのだけれども、なんとなく、あるいは何かがズレてしまったような感覚をぼくは覚える。香港に住んでいる人たちは、いつもどおり、買い物をし、外食をし、学校や仕事に通っているのだけれど、なにかが「いつもと違う」感じなのだ。どこかそわそわして落ち着かない感じもあれば、どこか静かな雰囲気もただよっている。強い雨がときおりふりそそぎ、天気が落ち着かないことも影響しているのだろうか。
そんな「感覚」は、ぼくのまったく勝手な感覚ではあるのだけれど、12年以上にわたって香港に住み、それなりにいろいろと経験してきたことをふまえての感覚である。ぼくの内面が外部に投影されているようなところもないとはいえない。だからその場所の「内部」にいるとわかりづらいこともあるけれど、でも「内部」にいるから感じる感覚もある。
香港という場所の特徴のひとつは、その場所の凝集性ともいうべきところにある。香港自体は、その中心部だけでなく隅から隅までを見晴るかすと思っている以上に大きいと感じるのだけれども、それでも、やはり地理的には小さい。経済社会活動の中心がぎゅっと中心にあつまっていて、いつでもどこにでも行ける距離感である。そんな具合に活動空間がひろがっていて、その空間のなかで日々活動し、暮らしている。
だから、「何か」が香港内で起こると、その物理的かつ心理的な影響が波及しやすい。ぼくは、体験・経験もふまえ、そんなふうに考えている。もちろん、メディアやSNSの「空間」がそこにはいりこんでくる。それらの「空間」が重なりながら、しかし、凝集性による他者や出来事とのかかわりの物理的な近さが場の雰囲気をつくりだす。この物理的な近さが香港の特徴のひとつである。
そんな香港に、強い雨がいくどもふりそそぐ。豪雨警報が発令されるほどの雨である。強い雨は雨雲とともに、香港を薄暗く映す。ときおり雲のあいだから射す陽光のような光が、どんな仕方で香港に射すのだろうかと思う。
以上、少しの、「感覚」のメモである。
書こうと思っても書くことができないとき。- 西アフリカでの「日々」を憶い出しながら。
書こうと思っても文章が書けないときがあるものである。言葉にならないときがある。
書こうと思っても文章が書けないときがあるものである。言葉にならないときがある。
たとえば、心身がほんとうに疲れているときに書けなくなったり、あるいは旅にどっぶりとつかっているときに書けなくなったりする。また、一日だけなど、ある短い時間・期間書けなくなることもあれば、比較的長い時間・期間にわたって書けなくなることもある。
ある程度長い期間にわたって「文章が書けなくなった」ときが、ぼくにはある。ただ書けなくなった(あるいは書かなくなった)のではなく、書こうと思っても書けなかったときである。
それは、2002年から2003年にわたって、西アフリカのシエラレオネに住んでいたときである。紛争が終結したばかりのシエラレオネに緊急支援を展開するNGOの一職員として活動していたときであった。
現地情勢はおちつきを取りもどしはじめているときではあったのだけれど、それでもそこでの現実と情況にぼくは圧倒され、また緊急支援の仕事に没頭しさまざまな問題・課題に直面していたこともあって、ぼくは「書くこと」ができなくなっていた。
もちろん仕事において書く仕事はこなしてはいた。報告書など、日本語と英語で書く仕事はたくさんあった。けれども、ぼくが「体験・経験していること」をその深みにおいてとらえ、言葉に表出してゆくことができなかった。
時間も、心身の状態も、「余裕がない」ということはあった。それほどに忙しかったし、支援の現場をとびまわりながら何役もこなし、マラリヤとも闘いながら、体力勝負のところもあった。さらには異文化のとまどいもついてまわる。
こんななかで、ぼくは書くことができなかった。
そのことを後悔をしているわけではない。とにかく「支援」に注力したことに、後悔はない。
また、書けないことが「悪い」ということでもない。仕事で書かなければいけないことは遂行していかなければいけないけれど、仕事を離れて書くことにおいて書けないことについて、良い・悪いということを言っているのでもない。
ただ、生きているなかではそんなときもある、ということ。それほどに、現実や体験・経験が圧倒するときがあるのだということ。でも、そんななかでも、深いところでは何かを感じているのだということ。それらは、いつか言葉になることもあれば、ならないこともあるということ。言葉になる「いつか」は、ある程度すぐであることもあれば、何年も先であることもあること。
そんなふうにして、体験・経験は、ぼくたちそれぞれの<土壌>となっていること。
ここ香港で、書こうと思っても言葉にならないなぁ、と思っていたら、シエラレオネの「あのとき」の感覚を憶い出したのであった。
自然と他者との「存在」だけを必要としている。- マテリアルな消費に依存している幸福の彼方へ。
じぶんと<モノとの関係性>を見直しているなかで、歓びに充ちた生を生きているためには、それほどモノを必要としてはいないのだということを感じる。
じぶんと<モノとの関係性>を見直しているなかで、歓びに充ちた生を生きているためには、それほどモノを必要としてはいないのだということを感じる。
もちろん、情報テクノロジーの発展によるところも大きい。本もCDもDVDも、つまり書物も音楽も映画・ドラマもデジタルになったことは大きい。でも、それでも、生きることのぜんたいを見渡しながら、歓びに充ちた生のためにはそれほど(この何十年かのあいだに、ぼくも含めた人びとが消費してきたほど)「モノ」は必要ないと、ぼくは思う。
見田宗介(社会学者)が現代の「情報化・消費化社会」をひらいてゆく論理と思想を根源的(ラディカル)に展開した名著『現代社会の理論』(岩波新書、1996年)。その終わりのほうに、つぎのように書かれている。
われわれの情報と消費の社会は、ほんとうに生産の彼方にあるもの、マテリアルな消費に依存する幸福の彼方にあるものを、不羈の仕方で追求するなら、それはこれほどに多くの外部を(他者と自然とを)、収奪し解体することを必要としてはいないのだということを見出すはずである。
見田宗介『現代社会の理論』(岩波新書、1996年)
ここでの「外部」の収奪と解体、つまり他者と自然の収奪と解体ということは、貧困の問題、それから環境・資源問題などを視野におさめている。これら「情報化・消費化社会」の<闇>を克服してゆくことの方向性と根拠を、説得力のある仕方で、また肯定的な仕方で、見田宗介は論じている。
ただ<闇>をこえてゆくためには、「ほんとうに生産の彼方にあるもの、マテリアルな消費に依存する幸福の彼方にあるものを、不羈の仕方で追求するなら」という条件がつけられている。でも、その方向性には必ず道がひらかれる。
これらの論点だけでなく、これまで生きてきた経験、またマテリアルな<モノとの関係性>を問いなおしてきた経験から、ぼくたちは「それほどに多くの外部を、収奪し解体することを必要としてはいない」のだということを、ぼくは実感している。
うえの文章につづけて、見田宗介は書いている。
…ほんとうはこのような自然と他者との、存在だけを不可欠のものとして必要としていることを、他者が他者であり、自然が自然であるという仕方で存在することだけを必要としているのだということを、見出すはずである。
見田宗介『現代社会の理論』(岩波新書、1996年)
<自然と他者の存在>だけを必要としていること。「必要」ということでふつう考えてしまうように、なにかの「ため」の、自然や他者ではない。そうではなく、自然や他者が<存在>していることだけを、ほんとうは必要としていること。
ひとの歓びや欲望などを追求してゆくと、ぼくたちはそのような実感につつまれる場におしだされるように思う。あるいは、あるとき、突如の出来事が、これまでと違った仕方で「世界」を見せるなかで、そんなことを深い実感で感じるかもしれない。
「ほんとうはこのような自然と他者との、存在だけを不可欠のものとして必要としていることを、他者が他者であり、自然が自然であるという仕方で存在することだけを必要としているのだということ」。
それにしても、すきとおるようなことばである。
「食器トレーの返却」がきざまれた心身。- 日本と海外の「あいだ」で。
ファーストフードや大衆食堂などで、食べたあとに食器トレーを返却口に返却する、という動作が身体にしみついていると、同じような状況において「返却しない」ということに引け目のような気持ちを感じる(ことがある)。
ファーストフードや大衆食堂などで、食べたあとに食器トレーを返却口に返却する、という動作が身体にしみついていると、同じような状況において「返却しない」ということに引け目のような気持ちを感じる(ことがある)。
たとえば、マクドナルドを想像してみるとわかりやすい。日本のマクドナルドで「返却する」ことを「あたりまえ」のようにしてきた身体が、海外のマクドナルドに立ち寄って「返却しない」ことが「あたりまえ」の状況におかれる。返却せずに、食べたあとのトレーをテーブルに残したままに席を立つ。
それらを片付けてくれる店員さんがいて、トレーを片付けてくれるのはわかっているのだけれども(そしてその「仕事」があるから店員さんはそこでの仕事を確保できるのだということもわかっているのだけれども)、じぶんの心身は「じぶんで返却する」意思が働く。でも、その意思をおさえて、その場その場の仕方にあわせて、テーブルのうえにトレーを残したままにするのだ。
そんな経験を海外に出るようになった最初のころだけでなく、ぼくは今でもする。「じぶんで返却する」意思がじぶんのなかで作動しはじめるのを感じることがあるのである。
「返却口」がまったくないようなところであれば返却はできないので、まったく気にはしないのだけれど、マクドナルドのように、トレーを返却する場(でも返却を求められているわけではない場)が設置されていると、頭ではわかっていても、「じぶんで返却する」モードが作動しはじめることがある。
返却がもとめられていれば、わかりやすい。そして、わかりやすいだけでなく、ぼくのなかで作動しはじめる「じぶんで返却する」モードは、それが作動する機会を得ることで落ちつくのでだ。
ここ香港でも日系のファーストフード(たとえばモスバーガー)や大衆食堂などでは「返却口」が設けられ、テーブルなどに「返却をもとめる」表示がされていたりする。でも、このシステムは「一般的」ではないから、なかなか浸透していかない。よい・わるいではなく、仕組みの違いである。
こんな具合であるのだけれど、面白い体験をした。ある大衆食堂のようなところ(日本の料理を提供する「日式」の大衆食堂)で食事を終えて、トレーを返却口に戻すように表示があるから、ぼくはトレーを返却口に戻した。返却口付近の店員さんが、笑顔で、そのトレーを受け取ってくれる。「ありがとうございます」と、ぼくに広東語で伝えながら。
ぼくも「ありがとうございます」と応答して、席にもどる。荷物をとってお店を去ろうしたところ、先ほどトレーを手渡した店員さんがやってきて、笑顔で話しながら、ぼくに「クーポン」を手渡してくれたのだ。
どうやら、「トレーを返却した」ことに対する御礼として、返却御礼としての「クーポン」である。クーポンにはそのように記載されている。「多謝您支持自助回収…/THANK YOU FOR RETURNING YOUR TRAY」というように。トレー返却への感謝としての「クーポン」を受け取ったのは、はじめてであったし、その発想にびっくりしてしまった。
再度笑顔で応答し、面白い体験の余韻を感じながら、ぼくはお店をあとにした。
そんなこんなで、ぼくはトレーの返却について考えさせられ、書いている。日本にいたときは「あたりまえ」であったことが、こうして「あたりまえ」ではないものとして日々体験される。
じぶんと<モノとの関係性>に光をあてる。- じぶんの内奥への階段を降りてゆく方法。
「トランクひとつ分の幸せ」。かたづけ士である小林易の『たった1分で人性が変わる片づけの習慣』に出てくることばである。ぼくはこのことばと、そんな生きかたに共感する。
「トランクひとつ分の幸せ」。
かたづけ士である小林易の『たった1分で人性が変わる片づけの習慣』に出てくることばである。ぼくはこのことばと、そんな生きかたに共感する。
小林易がこのことばに至ったのは、大学時代のアイルランド留学であった。3カ月の留学生活を終えて、帰国の荷づくりをはじめた小林易は、荷づくりのために、ベッドの下に収納していたトランクを出したときに自ら衝撃をうけることになる。「トランクひとつ」で3カ月生活できたこと、またモノの少ない生活のほうが充実していたこと、これらのことにである。
あなたの人生を豊かにするモノの量は、私がアイルランドに留学したときのトランクひとつ分の荷物かもしれません。トランクひとつ分の幸せこそが、いちばんステキな幸せかもしれません。
小松易『たった1分で人性が変わる片づけの習慣』電子書籍版(KADOKAWA/中経出版、2017年)
ぼくの共感は、ぼくの経験と感覚からきている。ぼくの海外暮らしも「トランクひとつ分」のようなときがあったからである。
大学時代に9ヶ月住んだニュージーランドを去るときも、それから仕事で赴任していた西アフリカのシエラレオネ、それに東ティモールを去るときも、いずれも「トランクひとつ分」(正確には、大きなバックパックひとつ分+手荷物)であった。
もちろん、シエラレオネと東ティモールはいわゆる「途上国」であり、モノの面においては情況がことなる。東京やニュージーランドや香港の街に出てショッピングをするような情況とはかけはなれている。けれども、だからこそ、いっそう「トランクひとつ分の幸せ」が見えてくることもある。
そんなぼくも、ここ香港に12年住むうちに、だいぶモノを増やしてしまった。この12年という時期は、情報技術テクノロジーの圧倒的な進展が重なったことも影響しているとは思うのだけれど、それにしても、ぼくはいつのまにか圧倒的にモノに囲まれてしまっていた。歓びに充ちたモノだけに囲まれているのであればまた違うのだけれど、そういうわけではなかった。
モノそれ自体を「悪者」にするのではなく、モノに直面しながら、じぶんと<モノとの関係性>を問うてゆくこと。
KonMari Methodも、断捨離も、ミニマリズムもそれぞれに、この<モノとの関係性>を見直すなかで、じぶんの内奥に降りてゆく方法である。モノとの関係のなかに、<じぶん>が見えてくる。そしてそこを起点としながら、これまでの「じぶん」を解体し、あらたに生成させてゆく。つまり、生きかたを変容させてゆく。
ぼくは幸いにも、じぶんと<モノとの関係性>を深く問うということを、「二重のトランジション」のなかで行っている。ひとつには、時代が変わりゆく「時代のトランジション」のなかであり、もうひとつは、ぼくの「人生のトランジション」のなかである。
これら「二重のトランジション」のなかで、ぼくは「トランクひとつ分の幸せ」をイメージとしながら、じぶんと<モノとの関係性>を根源的に問い直している。そして、それは、さまざまな<関係性>を問うことへと、ぼくを押し出してしまうのである。
矢沢永吉がツアーを一年休んだとき。- 休んだことによる「発見」。
「ほぼ日刊イトイ新聞」の創刊21周年記念企画、矢沢永吉x糸井重里の対談が興味深い。
「ほぼ日刊イトイ新聞」の創刊21周年記念企画、矢沢永吉x糸井重里の対談が興味深い。
たとえば、その「第3回:やってたら、落ち着くの」(2019年6月8日配信開始)のなかで、歌手の矢沢永吉が「一年ツアーを休んだときのこと」を語っている。話の文脈は、第3回のタイトル「やってたら、落ち着くの」にあるように、なぜ、こうして歌手としてやりつづけているのかという問いへの応答である。
矢沢永吉が歌手として「いちおう食べれる」ようになってから、ハッピーじゃないことに気づく。まもなく70歳になる矢沢は、「俺は、金じゃなくて、やりたくてやってる。…やってたら、落ち着くの」と語る。
やることの大きさではなく、それぞれの人なりに「じぶんがやりたいことが、落ち着くことが、あるか、ないか」が大切なんだと、糸井重里と「ほぼ日」の乗組員たちをまえに語るのである。
そんな発言を聴きながら、糸井重里が、「一年ツアーを休んだこと」がよかったのではないかと、問いを投げかける。
それに対して、矢沢永吉は、こんなふうに、興味深い応答をしている。
矢沢 あのときはね、なんだ、俺、気づいたら、走って走って、転がって転がって、行って行って、これじゃまずいなと思ったのよ。ただひたすらに機関車のように走って、そうじゃなくてさ、どこかの街をこう歩いていると、ちょっとあぜ道があったり、横丁があったりして、ちょっと入ってみたいなぁって思ってひょいと曲がってみたりして、これが生きてるってことじゃない?…
「道」が呼びかけてくる。それは、実際の街にあるあぜ道や横丁でありながら、心の奥深くにたたずむ<道>であるかもしれない。「生きられていないじぶん」が、心の奥深くから、呼びかけてくる。そんなふうに、ぼくはいったん読みながら、先をつづける。そして、その先が、とても興味深いのだ。
矢沢永吉は、こう語り続ける。
矢沢 で、ちょっと、今年はツアーやめる、と。やめて、逆にその横丁みたいなとこ、ちょっと覗いてみて、入ってみたらどうなるのか、発見があるかもしれないと思ったんですね。…すると、どうなったか?…なんにも発見がないことがわかった。
一年ツアーを休んで、横丁に入ってみて、「発見」を期待したけれど、そこには「なんにも発見がないこと」がわかる。矢沢は、あくまでも「ぼく」のこととして、また器用でない「ぼく」のこととして、この経験を伝えている。「そうなんだよ、人生ってそんなもんなんだよ!」、と。
糸井重里も、周りで聴いている人たちもみな、笑う。矢沢永吉も期待したように、糸井重里も、周りで聴いている人たちも、それから読者も、「発見」を期待してしまう。どんな「発見」があったのだろうと。でも、矢沢にとって、そこに「発見」はなかった。
「発見」がなかったことを聞いて、人はそれぞれに、いろいろと応答するかもしれない。「休み」の効果や「横丁」の呼びかけについて、いろいろと語るかもしれない。そのことについて、矢沢永吉は積極的に口をはさむことはしないだろう。
ぼくが思うのは、それでも、なんにも発見がないことが「わかった」ということ自体に、矢沢永吉にとっての「意味」があっただろうし、そこを転回軸として、「やりたくてやってる」という方向につきぬけてゆくことができたのではないかということである。
「そうなんだよ、人生ってそんなもんなんだよ!」と矢沢永吉が言うとき、そこには投げやりがあるのではなく、そんな人生を、そんな人生だからこそ、その過程を味わいつくしてゆくのだというところに走りぬけていく力としての潔さがあるように、ぼくにはきこえる。
<内破する>ということば。- 「卵を内側から破る」方法へ。
<内破する>ということばは、ぼくが好きなことばのひとつである。内側から破ること。
<内破する>ということばは、ぼくが好きなことばのひとつである。内側から破ること。
「内破」ということばをはじめて耳にしたのは、2000年に出版された書物『内破する知 身体・言葉・権力を編みなおす』(東京大学出版会)であったと思う。近代知を<内破>し、新たな知の地平をひらくものとして企画された『越境する知』というシリーズの「プレリュード」として出版された書物であった(※表紙に、画家・彫刻家の奈良美智による独特な「女の子」の絵がかかげられている。それがぼくを惹きつけた)。
ちょうどこの本のシンポジウムが新宿の紀伊国屋でひらかれ、当時ぼくはこのシンポジウムを聴きに足をはこんだ。この書物とシリーズの編集者であり著者の栗原彬が、シンポジウムの冒頭で「内破(implosion)」ということばについて、モチーフと説明を加えていたことを覚えている。
細かい説明を覚えているわけではないけれど、このときから、ぼくのなかに<内破する>ということばが棲みつきはじめたのである。
<内破する>ということは、ことばのとおり、外側から力を加えて破るのではなく、内側からの力によって破ってゆくことである。
いろいろなものを「外部」から変革しようとしてきた時代や社会や組織・集団や人などを見て、あるいは経験しながら、「内側」の充溢した力によって内側から破ってゆくこと、突破してゆくこと、変革してゆくことが、いっそう大切であると、ぼくは思う。
これからの社会が変わってゆくうえでも、コミュニティが変わってゆくうえでも、組織・集団が変わってゆくうえでも、そして、個人が変わってゆくうえでも、それぞれに、<内破する>ことが決定的に重要である。
<内破>ということばがぼくのなかに棲みつきはじめてからだいぶ経って、ぼくは、見田宗介(社会学者)が、「卵は内側から破られなければならない」というダグラス・ラミスのことばをとりあげて、「世界を変える方法」について書いているところに出会った(『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』岩波新書、2018年)。
外側から卵を割るのではなく、内側の生命みずからが、育ってゆくことを阻害するものがあるのであれば、卵を内側から破っていかなければならない。見田宗介はこれからの世界の「変革」の方法について、この点を強調している。
<内破する>という仕方は、ぼくが生きてきた実感としても、とても大切な方法であることを、ぼくは感じる。
さて、水俣病の場に身をおきながら実践し考えてきた栗原彬は、冒頭に挙げたシンポジウムのなかで、市民社会の「行き詰まり」は必ずしも「悪い」ものではないということを語っていた。「行き詰まり」を感じることの重要性に焦点をあてたからである。栗原彬は、「行き詰まり」は<内破への契機>になるのだと、指摘したのであった。
ぼくたちが経験する、さまざまな「行き詰まり」を<内破への契機>として生ききること。「行き詰まり」自体を豊饒に生きつくすこと。そして、<内破する>こと。じぶんの「内側」から破ってゆくこと。
「世界」はそんなふうにして、今までと違った風景をみせてゆくことになる。
<自由><平等>対<合理性>という鮮烈な視点。- 見田宗介による「現代社会」の明晰な見方。
ぼくたちの生きかたを考えていくうえで、現在(現代社会)を含む「近代」という時代を理解しておくことが、ほんとうに大切なことだと、ぼくは思う。
ぼくたちの生きかたを考えていくうえで、現在(現代社会)を含む「近代」という時代を理解しておくことが、ほんとうに大切なことだと、ぼくは思う。
現在はなにごとにおいても「個人」ということに焦点があてられる時代であり、いろいろな言説や商品やサービスが「個人」へと向けられていて、生きかたにおいても<自分を生きる>ということに光があてられる。
それはひとまず「正しい」ところではあると思うのだけれど、ただ「自分」だけをまなざすのではなく、どのような「社会」なのか、どのような時代なのか、どのような歴史的経緯のなかに自分は生きているのかなどを理解しておくことが、「自分」という存在を深いところで知り、よりよい生きかたへひらいてゆくために大切なことである。
たとえば、「<自由><平等>対<合理性>」という視点をあげてみよう。
見田宗介(社会学者)は、あるところで、日本における「近代家父長制家族」の考察に続けて、次のように書いている。
ウェーバーの見るように「近代」の原理は「合理性」であり、近代とはこの「合理性」が、社会のあらゆる領域に貫徹する社会であった。他方、近代の「理念」は自由と平等である。現実の近代社会をその基底において支えた「近代家父長制家族」とは、この近代の現実の原則であった生産主義的な生の手段化=「合理化」によって、近代の「理念」であった自由と平等を封印する形態であった…。
「高度経済成長」の成就とこの生産主義的な「生の手段化」=「合理化」の圧力の解除とともにこの「封印」は解凍し、「平等」を求める女性たちの声、「自由」を求める青年たちの声の前に、<近代家父長制家族>とこれに連動するモラルとシステムの全体が音を立てての解体を開始している。見田宗介「現代社会はどこに向かうか」『定本 見田宗介著作集 I』岩波書店
この文章は少し手を加えられ、別の著書『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』(岩波新書、2018年)にも収められている。
ここで書かれていることの主旨は、この本の第1章のある「節」のタイトルとして書かれているけれど、「<自由><平等>対<合理性>。合理化圧力の解除、あるいは減圧」ということである。
教科書的な理解では、「近代」という時代は「自由」と「平等」を理念としてきた時代であったということであるのだけれど、実際の「現実原則」は「合理性」であったということ。「近代家父長制家族」というシステムに支えられる「合理性」によって、実は「自由」と「平等」は封印されていた/封印されてきたということである。
この視点をとりいれてみるだけで、世界のあり様が<視える>ようになる。
「生産主義的な生の手段化=合理化」ということが社会のあらゆる領域、その社会に生きる人たちの内奥にまで貫徹してきたことは、いろいろに語ることができる。
ところが、経済成長による物質的な豊かさが獲得されるなかで、この「合理化」の圧力が解除、あるいは減圧してきたところに、高度産業社会を生きている人たちはおかれている。合理化の圧力の解除・減圧に伴い、「<自由><平等>対<合理性>」という図式における<自由>と<平等>が、「封印」を解除されてくるのだ。
こんなふうにして<自由>と<平等>の声たちが、社会のあらゆる領域にひろがっていきつつある。見田宗介が明晰に書いているとおり、「「平等」を求める女性たちの声、「自由」を求める青年たちの声の前に、<近代家父長制家族>とこれに連動するモラルとシステムの全体が音を立てての解体を開始」している情況を、ぼくたちは日々、目にしたり、耳にしたりしている。
また「個人」ということがこれほどに前景化してきたことも、合理化の圧力が解除・減圧してきたことと関連しているのだと思う。
「豊かな社会になって、今の若者たちは…」というように世代論的に言われることもあるけれど、今ぼくたちが直面しているのは、はるかに深いところで動いている社会の地殻変動である。「<自由><平等>対<合理性>」という図式は、そんな地殻変動を見るための、鮮烈な視点である。
山の「歩きかた」に凝縮された<教え>。- ニュージーランドの山との/山での出会い。
ニュージーランドの山をひとりでめぐっているときに、ぼくは、ぼくの「生きかた」を深いところで照らす<教え>を得た。山小屋で出会ったスウェーデン出身の女性に受けたその<教え>は、それまでじぶんが疑問視してきたことに直接に光をあてた。
ニュージーランドの山をひとりでめぐっているときに、ぼくは、ぼくの「生きかた」を深いところで照らす<教え>を得た。山小屋で出会ったスウェーデン出身の女性に受けたその<教え>は、それまでじぶんが疑問視してきたことに直接に光をあてた。
正確には、彼女が「生きかた」を説いたのではない。彼女は、ぼくに問いを投げかけたのであった。
「ジュン、あなたは道中何を見てきたの?」
流暢な英語で、彼女の真摯な声がぼくにまっすぐにとどいた。ほんとうにまっすぐな響きであった。
1996年のこと。大学2年を終え休学し、ワーキングホリデー制度を活用してニュージーランドに住むことになったぼくは、最終的に9ヶ月ほどの滞在となったうちの後半に、ニュージーランドを旅した。最初はニュージーランド徒歩縦断に挑戦し、その挑戦が中途で「挫折」したのちは、南島の山々を歩いていた。
ニュージーランドの山々はとてもよく管理されていて、トレッキングのコースに沿って山小屋がうまい具合に配置されている。これらの山小屋を移動してゆくことで、コースを完了することができるようになっている。
そんなコースのひとつを選んで歩いていたぼくは、あるとき山小屋を早朝に出発し、歩みを進め、昼過ぎには次の山小屋に到着したのであった。
つぎの「山小屋」という目的地に着くことができたぼくは、山小屋でゆっくりしていたのだけれど、夕方あたりになって、一人のトレッカーが到着したのであった。休暇でスウェーデンから来ているという彼女は、ぼくと言葉を交わすなかで、冒頭の問いをなげかけたのであった。
「ジュン、あなたは道中何を見てきたの?」
そんな問いを投げかけながら、彼女は、道中で楽しんできた、道の脇に咲く花や草木、また彼女をむかえる鳥たちがどれだけ素晴らしかったかを話してくれた。彼女が投げかけた問い、彼女の「歩きかた」とその楽しみかたに、ぼくの心の深いところに照明があてられたようであった。その光は、ぼくの「生きかた」までをも照らすほどの、まっすぐな光であった。
問いを投げかけられたぼくは、つぎ’の山小屋という「目標」に目を向けて道中をかけぬけてきてしまっていたから、返す言葉を失ってしまった。道中まったく見てこなかったわけではないけれど、道の両脇に咲く花や草木たちとすごす時間は、なるべく効率的に短縮されてしまったかのようであった。
彼女の問いとことば(とその響き)は、今でも、ぼくのなかで光源として輝きを放ちながら、ぼくの「生きかた」に光をあてている。
…「近代」という時代の特質は人間の生のあらゆる領域における<合理化>の貫徹ということ。未来におかれた「目的」のために生を手段化するということ。現在の生をそれ自体として楽しむことを禁圧することにあった。…
見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』(岩波新書、2018年)
見田宗介(社会学者)は、「近代」という時代の特質をこんなふうに書いている。
この特質は、ぼくの心身にきざみこまれていた特質である。ぼくは、「つぎの山小屋」という「未来におかれた目的」のために、現在の楽しみ(花や草木たち!)を禁圧していた。「つぎの山小屋」が達成されることに、ぼくは「充実」を得ようとしていたわけである。それはそれなりに「充実」であっただろう。
けれども、ニュージーランドの自然それ自体、それから道中に出会ったスウェーデン出身の女性の「歩きかた=楽しみかた」は、ぼくの「生きかた」へのアンチテーゼであり、「現在の生をそれ自体として楽しむこと」というまっすぐなテーゼであった。
「新しさ」ということ。- 香港の「新しい」店舗に日々出会いながら。
ここ香港では、店舗の移り変わりが圧倒的に速い。新しい店舗がオープンする。店の前に花がならび、「新しさ」の爽快さと開放性が人びとの足をとめる。
ここ香港では、店舗の移り変わりが圧倒的に速い。新しい店舗がオープンする。店の前に花がならび、「新しさ」の爽快さと開放性が人びとの足をとめる。
同じ場所に長く店をかまえていることももちろんあるけれど、その場合はその場合で、ある程度の期間ののちに「改装」され、心機一転のオープンとなる。新店舗や改装の回転速度が圧倒的なのである。この速さは、これまで住んできた東京、ニュージーランド、シエラレオネ、東ティモールでは見ることも、感じることもなかったものである。この「速さ」のなかに、香港の経済社会の本質がある。
それにしても、新しい店舗を至るところに目にし、やはり気になって立ち寄ったりしながら、「新しさ」ということを考えさせられる。
新しい店舗には、上述したように爽快さと開放性があり、お店の人たちも行き交う人たちも、どこかエネルギーに満ちているように感じる。エキサイトメントがある。でも、「新しさ」ということのなかに、「新しさ」の経験のなかに、ぼくたちは、ほんとうは何を求めているのだろうか。
見田宗介(社会学者)は、1980年代の日本の「現代社会」に身をおきながら、つぎのように書いていた。
…前近代の文明の洗練されたゆきづまりである封建社会が、「古さ」の神話で共同体の人びとを窒息させてきたこととおなじに、近代文明の洗練されたゆきづまりである現代社会は、「新しさ」の神話によって市民社会の人びとを窒息させる。…
見田宗介『現代日本の感覚と思想』講談社学術文庫
「新しさ」の神話につかれてきた社会ということは、よくわかる。1980年代から1990年代にかけて日本の社会に生きながら、そのときのことを振りかえってみると、確かに「新しさ」への衝動につかれているように感じるのである。
見田宗介は、この文章、「「新しさ」からの解放」と題された論壇時評を、つぎのように書き終えている。
<伝統>という名の衣装を脱ぎすてたときに人間は、ひとつの解放を手に入れたはずだ。<前衛>という名のモード、つねにより「新しいもの」でありつづけなければならぬという強迫観念を脱ぎすてるときに、わたしたちは、もうひとつの巨大な自由を手にいれるだろう。
見田宗介『現代日本の感覚と思想』講談社学術文庫
「新しさ」が良い・悪いということではない。それは「ひとつの解放」である(あった)のだけれど、「つねにより「新しいもの」でありつづけなければならぬという強迫観念」は、逆に人を不自由にさせる。ぼくもそう思う。
時代はその時間の針をすすめながら、<伝統>からも、また<新しいもの>への強迫観念からも自由であろうとする動きが起きはじめている。
冒頭に挙げた香港の店舗の「新しさ」については、別の観点も含めて見てゆく必要があると思うけれど、日々いろいろなところで「新しさ」に出会いながら、ぼくは考えてしまうのである。「新しさ」に何を、ぼく(たち)はほんとうに求めているのだろうか、と。
「しあわせは…」( 相田みつを)。- 香港の小道を歩きながら。
詩人であり書家の相田みつを(1924-1991)のことばに、よくとりあげられる、次のことばがある。
詩人であり書家の相田みつを(1924-1991)のことばに、よくとりあげられる、次のことばがある。
しあわせは
いつも
じぶんの
こころが
きめるみつを
ここでは「ことば」だけをひろったけれど、ぜひ、相田みつをの「書」を見てほしい。「書」のなかに、その一文字一文字、あるいは余白に、書を見る人それぞれに「何か」を感じるだろう。
ここ香港のレストラン(というより大衆食堂)で遅めのお昼をとった帰り道に、木漏れ日が射すなかを歩きながら、ふと、相田みつをのこのことばが思い浮かんだのであった。
このことばにはじめて触れたのはいつだったか。20年以上まえ、相田みつをの存在とことばをはじめて知り、読んだときにも、このことばに出会っていたような気もするけれど、定かではない。確かなのは、2010年に、東京フォーラムの相田みつを美術館での出会い(あるいは再会)である。
母が亡くなった喪失感のなかで、たまたま東京国際フォーラムの近くを歩いていたとき、なぜか、ぼくは相田みつを美術館にひきつけられたのだ。そして、そこで出会った相田みつをのことばたちに、ぼくは、ほんとうに支えられたのである。
そんなことばたちのひとつに、このことばがあった。
このことばは「あたりまえ」のことだと言われれば、そうかもしれない、とぼくは応える。
ぼくにとっては、ひとことひとこと、「しあわせ」も、「いつも」も、「じぶん」も、「こころ」も、そして「きめる」も、自明のことではないのだけれど、まずはそう応えるだろう。けれども、これらひとことひとことをいったん置いたとしても(日常意識でふつうにとらえたとしても)、この「あたりまえ」が実際にはすんなりと日常にはいっていかないところに、いろいろと考えさせられるのである。
「あたりまえ」のことであっても、頭ではわかっていても、あるいは心の奥深くにおいてわかっていても、いつのまにか、じぶんではない他者やモノに、じぶんの「しあわせ」が依存してしまっていたりすることがある。
相田みつをの「書」を見てみると、最後の「きめる」の文字が相対的に細めで、字がかすれている。わかっていても、「きめる」という動詞を日常に展開させることのむつかしさが、この文字の揺らぎにあらわれているように、ぼくには見える。
木々がゆれ、その先に海の存在を感じながら、ふと、相田みつをのこのことばがぼくの心に浮かんだのは、ようやく、このことばが語る経験をぼくが日常のなかで感覚し、生きはじめたからかもしれない。
それは、相田みつをの細く少しかすれた「きめる」の文字のように、決して力強いものではない。でも、生きる経験を積み重ねてゆくなかで、より深く感じるようになってきていることを、ぼくは思う。
レストランのメニューの「英語訳」。- 香港で出会う「可笑しさ」。
レストランのメニューの「英語訳」が結構むつかしいことを実感したのは、大学時代にアルバイトをしていたレストランバーであったと記憶している。
レストランのメニューの「英語訳」が結構むつかしいことを実感したのは、大学時代にアルバイトをしていたレストランバーであったと記憶している。
新宿駅のすぐ近くにあったそのレストランバーでアルバイトをしていたのだけれど、ときおり、英語スピーカーのお客様に料理の説明を英語でするように頼まれたりすることがあった。英語(だけ)はそれなりに勉強し、外国語の大学に通っていたぼくだったのだけれど、思うように説明できなかった。
そののちに、ニュージーランドに住みながら日本食レストランでアルバイトしていたときも、日本食とその料理の仕方を上手く説明できた記憶がない。
英語以前の問題(料理の知識不足など)もあるのだけれども、メニューや料理の仕方を「英語」にするのは、ぼくにとって、それほど容易ではなかったし、今もときおり困ることがあるものだ。
だから、人のことを笑うことができる立場でもない。でも、レストランで「可笑しい(おもしろい)」英語訳(ときには明らかに「間違っている」英語訳)に出会うと、笑ってしまうことがある。
ここ香港で出会った、レストランメニューの「可笑しい(おもしろい)英語訳」に、「fired」がある。中国語をみると、焼くとか炒めるといった意味だから、「fried」じゃないかと思って、同じメニューの他の英語訳を確認すると、やはり「fried」となっている。
「fired」の名詞は「fire(火)」であるし、動詞に一応「焼く」という意味もあるから(異なる文脈で)、100%間違っているとは言いきれないなぁ、意図的ということもありうるなぁと思いながら、しかし、やはり英訳ソフトの問題か、あるいは「fried」への変換ミスじゃないかとも思うのである。
それも一度だけの経験ではなく、異なるレストランで、いくどか「fired」に出会うのだから、考えさせられてしまうのである(また、「fired」には「解雇される」という意味合いもあるから、マネジメントや人事にかかわってきた身としても、複雑な思いもまじってくるのである)。
これはひとつの例であるけれど、レストランのメニューの英語訳をながめながらおもしろい訳に出会うのは、ぼくにとって、楽しみのひとつである。
こんな楽しみをもつことができるのは、漢字も英語も一応読むことができるからだろうと思う。漢字が読めず英語しかわからない人が、おかしい英語訳に直面したとき、なにがなんだかわからないだろう(それはそれで楽しいかもしれない)。
このような「楽しみ」も、翻訳ソフトや機能の向上などに伴い、いつかはなくなってしまうものかもしれない。
「お互いに活かし合おうというところに人間の起原がある」(見田宗介)。- 共生の時代の「足場」のひとつとして。
大澤真幸・見田宗介『<わたし>と<みんな>の社会学』(左右社、2017年)の「まえがき」で、大澤真幸(社会学者)は、大学に入学した年(1977年)に(その後の師となる)見田宗介先生との出会いを通じて「学んだこと」を書いている。
大澤真幸・見田宗介『<わたし>と<みんな>の社会学』(左右社、2017年)の「まえがき」で、大澤真幸(社会学者)は、大学に入学した年(1977年)に(その後の師となる)見田宗介先生との出会いを通じて「学んだこと」を書いている。
「生きることと考えることはひとつになりうること、人生と学問を統一できるということ、人が生きる上で直面する諸々の深刻な問題に学知を通じて対することができるということ」という決定的な学びである。
その年(1977年)、真木悠介の筆名で発表された見田宗介の二冊、『気流の鳴る音』と『現代社会の存立構造』(いずれも筑摩書房)。大澤真幸の決定的な学びに影響を与えたこれら二冊に、ぼくはそれからおよそ20年後に出会う。
それは、圧倒的な出会いと学びであった。『現代社会の存立構造』でいわばぼくの<世界>の見方が変わり、『気流の鳴る音』でぼくの<生き方>を方向付けることができた。
「真木悠介」の筆名で書かれる著作は「世に容れられることを一切期待しない」(真木悠介)ものとして書かれる著作であるけれど、ぼくを圧倒的な仕方でとらえた著作群は、真木悠介による著作群であった。
『気流の鳴る音』と『現代社会の存立構造』のあと出された『時間の比較社会学』(岩波書店、1981年)は、ぼくを深いところで<解き放つ>ものであった。
けれども、そもそも「けれども」という言い方が適切かどうかはわからないけれど、ほんとうにぼくを<解き放つ>ものであったのは、『自我の起原』(岩波書店、1993年)であったのだと言うことができる。人としての<自由>というものをまるで手に取るようにしてつかんで見ることができたような、そんな圧倒的な経験であった。
「何度この本を読んだか」という次元ではなく、『自我の起原』はいくどもいくどもひらいてきた書物である。
本を整理整頓している折にふと手にとった『<わたし>と<みんな>の社会学』のページを繰りながら、『自我の起原』という書物の、底知れない深さと圧倒的な触発性を、ぼくは感じている。
『<わたし>と<みんな>の社会学』における大澤真幸と真木悠介との対談は、『自我の起原』のコアにふれてゆく。そんなひとつの話として、地球にはもともと酸素がなかったところにまで視界をひろげてゆくところがある。
当時は酸素は有毒であったところ、有毒である酸素を生かして生きる生物があらわれる。他の生物たちは、酸素を生かすこの生物と<共生する>ことで、有毒物質である酸素にとりこまれている環境を生き延びてきたわけである。ミトコンドリアとして自己の内部にとりこんで<共生のシステム>をつくることによって。そして、「今」を生きる動物も植物も、この<共生のシステム>が展開してきたものであることに、見田宗介はことばの照明をあてる。
見田 …つまり生物進化のいちばん大きな根幹は異なった種の共生によって成し遂げられた。…つまり生物進化のいちばん太い幹は、共生から出てきたことをいま一度確認する必要があります。お互いに殺し合うのではなく、お互いに活かし合おうというところに人間の起原がある。
大澤真幸・見田宗介『<わたし>と<みんな>の社会学』(左右社、2017年)
とても力強いことばである。希望のことばである。しかも、ただのことばではなく、生物学のオーソドックスな理論のなかに足場をおくことばである。
ぼくたちのひとりひとりの身体は、その起原において、<共生>をその根幹にしている。これからの<共生の時代>に向けて、確かな足場のひとつをおくことのできる場所である。
なんどでも繰り返そう。「お互いに活かし合おうというところに人間の起原がある」のだ、と。
「知」がひらく地平。- 大澤真幸が見田宗介から「学んだこと」。
本を整理整頓するとき、ある本を手にとって、つい読んでしまうことがある。本来は「整理整頓」なのだから、効率的に動こうと思うのであれば、途中で立ち止まって読んでしまうことは避けたい。
本を整理整頓するとき、ある本を手にとって、つい読んでしまうことがある。本来は「整理整頓」なのだから、効率的に動こうと思うのであれば、途中で立ち止まって読んでしまうことは避けたい。でも、ついぱらぱらとページを繰り、ふと目がとまる。以前に読んだことを覚えている文章もあれば、ほとんど記憶にない文章もある。いずれにしろ、ふととまるところというのは、今のじぶんにとって「何か」を語っているところであるかもしれない。
そんな本の一冊に、大澤真幸・見田宗介『<わたし>と<みんな>の社会学』(左右社、2017年)がある。社会学者である大澤真幸によるシリーズ本(『THINKING「O」』)の一冊で、大澤真幸の師、社会学者の見田宗介がゲストである。
ぱらぱらとページを繰りながら、ふと立ち止まった箇所のひとつが「まえがき」であった。「まえがき」で、大学に入学した18歳の大澤真幸が見田宗介先生との出会いを通じて「学んだこと」が書かれている。
ぼくは見田宗介先生に私淑しているから、ぼくはぼくが見田宗介先生との出会いを通じて「学んだこと」という視点を重ね合わせながら読む。
ちなみに、大澤真幸が大学に入学した1977年、見田宗介は、真木悠介の筆名で二冊の書物、今では名著となっている二冊(『気流の鳴る音』『現代社会の存立構造』)を世に放っている。それらを読みながら、また見田宗介の「比較社会学」の演習に出席しながら、大澤真幸は「驚き」とともに決定的な「学び」を得る。
18歳の私が驚きとともに学んだことは、生きることと考えることはひとつになりうること、人生と学問を統一できるということ、人が生きる上で直面する諸々の深刻な問題に学知を通じて対することができるということである。
大澤真幸・見田宗介『<わたし>と<みんな>の社会学』(左右社、2017年)
大澤真幸が注記しているように、それは、恋愛や就職などの個別の悩みに人生相談的な回答を与えるものではない。そうではなく、はるかに、ファンダメンタルな次元におけるものだ。学問はときに、「<世界>の見え方を変え、人生を生き直すことを可能にする」のだと、大澤は書いている。
<世界>の見え方を圧倒的な仕方で変えることができること。これは、見田宗介(真木悠介)先生の著作との出会いを通じて、そしてとことんそれらで語られていることに降り立っていくことで、ぼくが経験し、実感したことでもある。
これらを学び得たということは、ひとつの幸福である。
そして、そのような「学び」に対してじぶんを閉じてしまうのではなく、ひらかれてあるのであれば、誰もがそのような経験をつかむことができるのである。
「人生はかくも単純で、かくも美しく輝く」(村上春樹)。- アイラ島独特の生牡蠣の食べ方を一例に。
シングル・モルト・ウィスキーの「聖地」である、スコットランドのアイラ島での旅をつづった、村上春樹のエッセイ『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)。この本のなかで、ボウモア蒸溜所のマネージャーであるジムが、島でとれる生牡蠣の食べ方(あるいは、シングル・モルトの飲み方、とも言える方法)を村上春樹に教えるところがある。
シングル・モルト・ウィスキーの「聖地」である、スコットランドのアイラ島での旅をつづった、村上春樹のエッセイ『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)。この本のなかで、ボウモア蒸溜所のマネージャーであるジムが、島でとれる生牡蠣の食べ方(あるいは、シングル・モルトの飲み方、とも言える方法)を村上春樹に教えるところがある。
島独特の食べ方とは、生牡蠣にシングル・モルトをかけて食べる、という仕方である。「一回やると、忘れられない」という、この食べ方を、村上春樹は実際にレストランで試してみることにする。
レストランで生牡蠣の皿といっしょにダブルのシングル・モルトを注文し、殻の中の牡蠣にとくとくと垂らし、そのまま口に運ぶ。…それから僕は、殻の中に残った汁とウィスキーの混じったものを、ぐいと飲む。それを儀式のように、六回繰り返す。至福である。
人生とはかくも単純で、かくも美しく輝くものなのだ。村上春樹『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)
この箇所に触発されて、アイラ島ではないけれども(ぼくはまだアイラ島に行ったことがないがいずれ訪れてみたい)、生牡蠣にウィスキーをかけて食べる、という仕方を、これまでに幾度か、実際にやってみた。
確かに、一回やってみると忘れられない。なんともいえない風味と味わいが口のなかに残るのである。これが、アイラ島で、しかもそこでつくられるシングル・モルトであったらと想像すると、「至福の時」が思い浮かぶのである。
でも、このエッセイのこの箇所がぼくの記憶に残った理由は、この食べ方に加えて、村上春樹の言明にあった。「人生とはかくも単純で、かくも美しく輝くものなのだ」という、言明である。「生牡蠣にシングル・モルトをかける食べ方」はひとつの例として、ぼくのなかに根をはったのは、「人生とはかくも単純で、かくも美しく輝くもの」ということであった。
そのような見方で人生を見渡してみると、「かくも単純で、かくも美しく輝くもの」に充ちていることに気づくことがある。もちろん、人の生はそんな気づきがあったり、気づきから遠ざかったり、また深く気づいたりと、なかなかシンプルにいかないものだったりする。あるいは、頭ではそうとわかっていても、実感がわかなかったりする。さらには、「単純」ではない方向に生きていって、思っていたものが見つからないと嘆いたりする。
それでも、やはり気づくときがある。「人生とはかくも単純で、かくも美しく輝くものなのだ」ということを。
「生牡蠣にシングル・モルトをかける食べ方」よりもいっそう単純なこと、たとえば、朝の凜とした空気に身体をさらすこと、好きな人(たち)とことばを交わすこと、水をのむこと、などなどの、いっそうシンプルなことのなかに、ぼくたちは、人生が「かくも単純で、かくも美しく輝くもの」である実体を見出すのである。
最近はじぶんのまわりの整理整頓をすすめ、モノを減らしていっているのだけれど、そのプロセスのなかで、いっそうシンプルなものごとのなかに「かくも単純で、かくも美しく輝くもの」を見つけ出すようになってきていることを、ぼくは感じる。あるいは、逆に見れば、シンプルなものごとのなかに「かくも単純で、かくも美しく輝くもの」を見つけ出すなかで、整理整頓がすすみ、モノを減らすことができているのかもしれない。
とても疲れているときに、やはり本をひらく。- 心に灯を灯し、あたためる。
とても疲れているとき、思っている仕方では休まらないことがあるものである。寝不足があきらかであれば寝れば元気になるものだけれど、寝ても何か疲れがとれないことがあったりするものである。そんなとき、逆に身体を動かすことで疲れがとれることもあるし、たとえば、読書をすることで疲れがいやされるようなこともある。
とても疲れているとき、思っている仕方では休まらないことがあるものである。寝不足があきらかであれば寝れば元気になるものだけれど、寝ても何か疲れがとれないことがあったりするものである。そんなとき、逆に身体を動かすことで疲れがとれることもあるし、たとえば、読書をすることで疲れがいやされるようなこともある。
疲れ方にもよるけれど、読書をすることで疲れをとる、という方法をぼくは採用することが結構ある。読書に疲れたときも読書で疲れをとる、という方法を採ることだってある。
読書がー仕事のように感じる人にとっては、ありえない方法かもしれないけれども、ぼくにとっては、読書がそんな役割も果たしてくれるのだ。
もちろん、どんな本でもよい、というわけではない。
数冊の本を、だいぶ前に書いたブログ「ひどく疲れた日にそっと開く本 - 言葉の身体性とリズム」で、ぼくは挙げた。そこで挙げた、下記の本は、今でもぼくにとって特別な本たちである。
村上春樹『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)
見田宗介『宮沢賢治 存在の祭りの中へ』(岩波書店)
真木悠介『旅のノートから』(岩波書店)
ここ2週間ほど、『旅のノートから』はぼくの座右に(字のごとく「座右」に)置かれ、ときおりぼくは、真木悠介(社会学者)のことばの世界に降り立ってきた。真木悠介の「18葉だけの写真と30片くらいのノート」からなる『旅のノートから』は、真木悠介にとって「わたしが生きたということの全体に思い残す何ものもないと、感じられているもの」として書かれたことばたちである。
同じように、見田宗介(真木悠介)のパースペクティブを通して宮沢賢治の生を見晴るかした『宮沢賢治』。「同じように」というのは、この名著『宮沢賢治』において、「わたしが生きたということの全体に思い残す何ものもないと、感じられているもの」という視点が、「宮沢賢治」になげかけられているように、ぼくは感じるからである。(宮沢賢治は病に倒れて、志の途中で「挫折」したのだと考えている人には、見田宗介先生による「宮沢賢治」を一読されることをおすすめする。)
「わたしが生きたということの全体に思い残す何ものもないと、感じられているもの」に彩られたことばたちが、ぼくがじぶんの内側に灯を灯すのを手伝ってくれるのかもしれない。だからか、『旅のノートから』を本棚に戻してから、いつのまにか、ぼくは『宮沢賢治』を手にとっていた。
それから、今日もとても疲れていたところ、ぼくは、村上春樹の『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』を手に取ることにしたのであった。
村上陽子さんの写真(おそらく。少なくとも「カバー写真」は村上陽子撮影)を見ているだけでも心がやすらぐのだけれど、スコットランドとアイルランドの旅に触発された村上春樹のことばのリズムに、しずかに身をゆだねる。
村上春樹は語る。ことばがウィスキーであったならウィスキーのグラスを交わすように人と人はわかりあうことができるけれど、人はことばがことばでしかない世界で、ことばの「限定性」に限定されながら生きている。でも、「例外的に」と、村上春樹はつづける。「ほんのわずかな幸福な瞬間に、ぼくらのことばはほんとうにウィスキーになることがある」(前掲書)と。
ここのところぼくはウィスキーもお酒もほとんど(まったく)飲まなくなったけれど、村上春樹の差し出してくれることばを、まるでウィスキーのグラスを傾けるように味わい、心身をあたためている。
ユングの深い洞察と鮮烈なことば。- ユングへの「予感」。
いつか読むことがわかっている本、いつかはわからないけれどいずれ読むだろうと予感のする本、読みたいと思いつつどこかで「まだ」と思う本、「そんなことごちゃごちゃ言っている暇があれば今にでも本をひらけばいいじゃないか」という声が聞こえつつもじっと「時」が熟すのを待っている本。
いつか読むことがわかっている本、いつかはわからないけれどいずれ読むだろうと予感のする本、読みたいと思いつつどこかで「まだ」と思う本、「そんなことごちゃごちゃ言っている暇があれば今にでも本をひらけばいいじゃないか」という声が聞こえつつもじっと「時」が熟すのを待っている本。
ぼくにとってそのような本に、心理学者カール・ユングの著作がある。膨大な著作群である。(Carl Jung『The Collected Works』第1巻から第18巻がまとめられたデジタル版があるのだけれど、ページ数で1万ページほどにもなる。)
少し読み始めたことがあるのだけれど、ぼくの側が「準備」できていないし、どこかまだその「時」ではないような気がして、本を閉じてしまった。
けれども、カール・ユングとその精神分析の学びを「閉じた」わけではない。心理学者の河合隼雄(1928ー2007)、ユング派の分析家ロバート A. ジョンソン(Robert A. Johnson、1924-2018)など、ぼくが尊敬してやまない知性たちを通じて学んできた。
本だけに限らず、カール・ユングに特化したポッドキャスト(英語)でもさまざまな知見にふれることができるため、ときどき聞いたりしている。
でも、ぼくのなかで「まもなく、正面から読み始める」予感がわいてきている。
そんな予感を感じさせるのに充分な「震え」を、ユングの分析手法をとりいれている実践家の著書を読んでいるときに出会ったユングのことばに、ぼくは感じたのである。
When an inner situation is not made conscious, it happens outside as fate.
- Carl Jung, Aion: Researches into the Phenomenology of the Self
内的な状況が意識化されないとき、それは外部にて運命(fate)として起こるのである。
とても鮮烈である。ユングの生涯の後年に出版された本のなかに出てくることばだ。
ユング自身の分析と説明の全体にふれたわけではないので、ここではこの細部には立ち入ることはしないけれども、引用されたこのことばを目にしたとき、ぼくの内部で、ほんとうに「震え」が起きたのであった。
そんな「震え」のなかに、まもなくカール・ユングの著作群に向き合う「予感」をぼくは感じる。
「When an inner situation is not made conscious, it happens outside as fate. 」。ほんとうに核心をついた深い洞察とすごい表現である。
人それぞれの「基層」でつながること。- 「グローバルという言葉は、僕にはあまりぴんとこない」(村上春樹)。
「グローバル」という言葉。グローバリゼーションがあたりまえのように日々語られるようになっていた2004年のインタビューで、この言葉が「あまりぴんとこない」と、小説家の村上春樹は語っている。
「グローバル」という言葉。グローバリゼーションがあたりまえのように日々語られるようになっていた2004年のインタビューで、この言葉が「あまりぴんとこない」と、小説家の村上春樹は語っている。
僕は僕の心の中に深く暗い豊かな世界を抱えているし、あなたもまたあなたの心の中に深く暗い豊かな世界を抱えている。そういう意味合いにおいては、…我々は場所とは関係なく同質のものを、それぞれに抱えていることになります。そしてその同質さをずっと深い場所まで、注意深くたどっていけば、我々は共通の場所にー物語という場所にー住んでいることがわかります。
…
グローバルという言葉は、僕にはあまりぴんとこない。なぜなら我々はとくにグローバルである必要なんてないからです。我々は既に同質性を持っているし、物語というチャンネルを通せば、それでもうじゅうぶんであるような気がするんです。村上春樹『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』(文藝春秋、2010年)
グローバリゼーションとはひとまず資本主義の運動として、経済的に世界を「つなげる」ということであり、外部に存在する客観的で異質なものをを同質に変えていくことであるということを考えると、村上春樹が語る「同質性」は、グローバリゼーションとちょうど反対の方向へとまなざされ、人それぞれの「基層」にすでに存在し、そこで「すでにつながっている」ものである。
だから「ぴんとこない」。けれどもグローバリゼーションの事情はわかるから「あまりぴんとこない」のであろう。
人と人との<つながり>のありかを、人それぞれの深いところ、ずっと深くの基層に見出す見方は、世界それぞれの土着の文化が深い基層で呼応しあっている(呼応しあってきた)様を、思い起こさせる。
「近代市民社会」は、標準化する力で「土着」を解体し、この標準化し均質化する力で「つなげる」同質性をひろげてゆく。「土着」が解体されてきたように、人それぞれに内在する<土着>も解体の力にさらされてきたのかもしれない。
けれども、人それぞれに内在する<土着>は、解体されたように見えても、解体されつくすことはない。人はだれもが「心の中に深く暗い豊かな世界を抱えている」のである。その深く暗い豊かな世界は、それを無視しようとすればするほどに、その世界からの「メッセンジャー」が幾度となく、現実の世界へとやってくることになる。
「自分を掘り下げてゆく」という仕方について村上春樹が語っているところを、別のインタビューからひろっておきたい。
…書くことによって、多数の地層からなる地面を掘り下げているんです。僕はいつでも、もっと深くまで行きたい。ある人たちは、それはあまりにも個人的な試みだと言います。僕はそうは思いません。この深みに達することができれば、みんなと共通の基層に触れ、読者と交流することができるんですから。つながりが生まれるんです。もし十分遠くまで行かないとしたら、何も起こらないでしょうね。
村上春樹『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』(文藝春秋、2010年)
「グローバリゼーションとは、無限に拡大しつづける一つの文明が、最終の有限性と出会う場所である」(見田宗介)ということは、この地球の環境・資源の有限性に真正面から出会うということである。この地球の「マテリアル」は有限である。「目に見えているもの」は有限である。
けれども、人それぞれの想像力、あるいは自分を掘り下げてゆくことで、とても深い場所に見つける共通の場所(「物語」の場所)は無限である。<目に見えないもの>はどこまでも、自由に、拡大してゆくことができる。
村上春樹の試みは、そのような、とても深い場所を掘り起こしてゆく試みである。最終の有限性と出会う場所としての「グローバリゼーション」ではなく、心の中に抱えている深く暗い豊かなの世界の無限性に出会う場所としての<グローバリゼーション>である。
「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」(村上春樹)ということば。- 修辞ではなく、ほんとうに夢を見るために。
『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』。小説家村上春樹のインタビュー(1997年から2009年)を集めた本のタイトルである。「あとがき」で、直接に本のタイトルにふれられているわけではなく、またインタビュー集の企画は編集者の方による強い提案によって実現したものだから、もしかしたら、編集者の方などが提案したタイトルかもしれない。
『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』。小説家村上春樹のインタビュー(1997年から2009年)を集めた本のタイトルである。「あとがき」で、直接に本のタイトルにふれられているわけではなく、またインタビュー集の企画は編集者の方による強い提案によって実現したものだから、もしかしたら、編集者の方などが提案したタイトルかもしれない。
ただ、「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」ということばは、2003年にフランスで行われた雑誌のインタビュー(聞き手:ミン・トラン・ユイ)のなかで、語られたものである。
…作家にとって書くことは、ちょうど、目覚めながら夢見るようなものです。それは、論理をいつも介入させられるとはかぎらない。法外な経験なんです。夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです。
村上春樹「書くことは、ちょうど、目覚めながら夢見るようなもの」『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』所収(文藝春秋、2010年)
とても素敵な本のタイトルであるとぼくは思うし、とても印象に残ることばである。
ところで、「ぼくは夢というのもぜんぜん見ないのですが…」と、村上春樹は心理学者の河合隼雄(1928ー2007)に語っている(『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』新潮文庫)。
河合隼雄は、夢を見ないのは「小説を書いているから」だと、村上春樹に応答している。とりわけ物語の世界に深く入って物語を書いているようなときは「現実生活と物語を書くことが完全にパラレルにある」のだから、夢を見る必要がないのだという。ちなみに、詩人の谷川俊太郎も夢を見ないのだと、河合隼雄は語っている。
このような見方に照らして見ると、「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」という言明はたんなる修辞というわけではなく、村上春樹にとっては「書くこと=夢を見ること」である。
さらに見る角度をかえてゆくと、「夢を見るために毎朝僕は目覚める」ことは「書くこと」にかぎられることではない。人が生きる、ということは、ひとりひとりが思い描く<夢>を生きていることにほかならない。<夢>とは、人が自身に語る「物語」である。
そのようにして、人は誰しもが、<夢>を見るために、毎朝目覚めているのである。どんな人も、<夢>の外に出ることはできない。できることは、どんな<夢>を見るのか、という選択である。
このような見方に照らすと、「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」という言明はたんなる修辞ではなく、「人が生きること=夢を見ること」という側面を正面から語ることばである。「夢から醒めるために目覚める」のではなく、「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」と、村上春樹は、正しい仕方でことばを転回させているのだということができる。